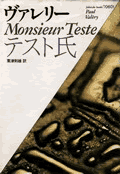
おそらく21世紀は「方法の世紀」となるだろう。そう、ぼくはずっと"予言"しつづけている。
最初は、「主題の時代ばかりがまかりとおるなんて、もうたくさんだ」という意味だった。「愛」や「平和」や「心」や「性」といった主題なら、とっくの昔に出揃っている。そんな主題を何千回、何万回もだいそれて甲論乙駁するよりも、そうした主題を動かす方法に着目したほうがいい、そういう意味だった。
方法とは道筋である。手立てである。また、「仕組み」であって「裂け目」である。主題はいつもどかっと坐っているが、方法は切れたり離れたり、くっついたり重なったりする。方法はいつも稲妻のように動いているし、割れ目のように何かのあいだにある。そのような主題と主題のあいだにある方法に注目したい。そう、考えるようになったのだ。
そのうち、科学の方法よりも「方法の科学」こそが必要ではないか、政治の方法より「方法の政治」が必要ではないか、哲学の方法より方法の哲学のほうが大事なんじゃないかというラディカルな気分になってきた。すでに映画の方法よりも「方法の映画」が映画界や映像作家を変え、コンピュータの方法よりも「方法のコンピュータ」のテスト版こそがコンピュータの業界やユーザーを革新してきたように、である。
100年前、世界と自分を見るにあたって必要なのは方法だけであると断言してみせた詩人がいた。十九世紀末のポール・ヴァレリーだ。ヴァレリーは、たとえばレオナルド・ダ・ヴィンチが芸術の方法なんぞに夢中になったのではなくて、まさに方法の芸術家たろうとしていたことを考察して、すべからく思索というものは方法の発見のほうに向かわなければならないと確信した。そういうヴァレリーの著作を通じて、ぼくはしだいに方法を感じるようになったのだ。
なぜヴァレリーは方法に注目することかできたのか。精神の正体が方法であることに気がついたからである。
不安定なものこそが生の道筋を通るということがある。その道筋になんとか気がつけば、精神がとりだせるときもある。なぜならば、精神とはその道筋そのものであり、その道筋を眺める視点が複合化されたものであるからだ。
ヴァレリーは主題として精神を選んだのであるけれど、そのうちその精神の隙間を走る方法に関心をもちはじめ、やがては精神とは実は方法そのもののことだったということに気がついたのだ。
「9歳か10歳のころ、わたしは自分の精神の島ともいうべきものを作り始めたにちがいない」とヴァレリーは書いている。そのころヴァレリーはまだ南仏の海港セートにいた。ゴーティエやボードレール(第773夜)による精神の島づくりだったろう。
やがてモンペリエ大学に入って法律を学び始めるのだが、大学が教えるものには「精神の島」がない。科学の方法や法社会学の方法ばかりを教えて、方法の科学や方法の文化がありうることは教えない。法学士を取得した直後の激しい嵐の夜、ヴァレリーはついにみずからの知的クーデターに着手して、「知性の偶像」以外のいっさいを拒否することを決意した。
この決意は、青年時代のヴァレリーがユイスマンスの『さかしま』(第990夜)を通してマラルメ(第966夜)を知ったことやポオの宇宙論『ユリーカ』を読んだことが大きなきっかけになっている。けれども、きっかけはどうであれ、その直後のヴァレリーはこの決意をまるで"国家機密"のように大事にして、前人未踏の思索に耽ることになる。
テスト氏とはそのようなヴァレリーの分身のことである。「精神」がヴァレリーであるとすれば、その精神を発現させ創発ている「方法」がテスト氏なのである。
テスト氏は、社会や人間の可塑性ということをよく知っている40歳くらいの人物だった。趣味も仕事も株にあった。株屋であることが生きがいで、株が動くのを見るのが専門だ。
フランス語では株式会社のことはソシエテ・アノニム(Socete
Anonyme)というのだが、これは直訳すれば無名会社というふうになる。テスト氏はこの言葉の意味が気にいっていた。なにしろ無名なものの複合性が株の動きでつくられているというのが、おもしろい。株は見えないのに、会社は見える。株が動けば会社も動く。けれども会社を次々に株に還元してしまえば、その会社には「生きている状態」なんてなくなっている。紙っぺらになる。
これはどうも、何かに似ている。何に一番似ているかとえば、精神にそっくりなのだ。だからテスト氏は株屋でありながら、精神の動きの専門家でもあった。
というようなことを前提にして、ヴァレリーはテスト氏によって眺められた自分を綴っていったのである。この方法は、自分とは「自分と自分のあいだ」にいるものなのだという見方をしていたヴァレリーにはぴったりだった。それにこういう綴り方をしていれば、自分はいつも自分と自分のあいだに居続けられた。ヴァレリーは小説嫌いだったのだ。
しかしヴァレリーがテスト氏を重要だとおもっていた理由は、ほんとうはテスト氏が株屋であることよりももっと大事な特徴をもっていたことにあった。テスト氏には、一定の意見も特定の主張もまったくないのだというところが大事だったのだ。テスト氏は「おもい」に従って現象を通過できるのだ。だからテスト氏が喋りはじめると、そこで語られるモノやコトがそこに混じりあい、テーブルは拡がり、街はお話のなかの空間になってしまうのだ。そういうふうにテスト氏が喋っているのを聞いていると、ヴァレリーは嬉しくなって、ついつい次のように書いてしまうのだ、「精神と精神とのあいだに立ちはだかる永劫の壁が崩れてゆくと思われた」。
ヴァレリーが『テスト氏』で示したことは、はっきりしている。精神と言葉のあいだに動めくものを描写したのだった。イメージとマネージの隙間を走る道筋を辿ろうとしたのだった。その「動めくもの」「隙間を走る道筋」とは、方法だ。
これは、編集工学なのである。いいかえればその後、アンドレ・ルロワ=グーランが推察しつづけて(第381夜)、ケネス・バーグが探そうとした動機の文法なのである(第48夜)。ヴィトゲンシュタインが苦しまぎれに「ぼけたへり」と呼び(第833夜)、ホワイトヘッドが「オーガニックな点-尖光」とみなしたものであり(第995夜)、グレゴリー・ベイトソンが「分裂生成」と名付けようとした、その当のものなのだ(第446夜)。
いや、もっとわかりやすくいうのなら、テスト氏とは、ぼくが方法の学校をはじめたときの初代校長であったのだ。
'Books > 書評' 카테고리의 다른 글
| All you know about running is just damn wrong! (0) | 2017.04.28 |
|---|---|
| アンリ・ポアンカレ 科学と方法 (0) | 2017.04.28 |
| 神々の猿 (0) | 2017.04.28 |
| 皇帝の新しい心 (0) | 2017.04.27 |
| 中谷宇吉郎 雪 (0) | 2017.04.27 |