
あらすじ
「惜しいかな後世、真田を云いて毛利を云わず」 天下一統が成らんとする戦国末期、豊臣秀吉の側近・黄母衣衆の森家に、一人の男児が産まれた。 ──彼の名は、森太郎兵衛。 太郎兵衛は、後藤又兵衛や長宗我部元親、そして立花宗茂など、強き者たちとの出会いを通じて成長し、齢十一にして大名となるのだが......。
"本意"を貫き通し、家康の前に最後まで立ちはだかった漢、毛利豊前守勝永の生涯を、仁木英之が渾身の力で描く"不屈の戦国絵巻"ここに開帳!
登場人物
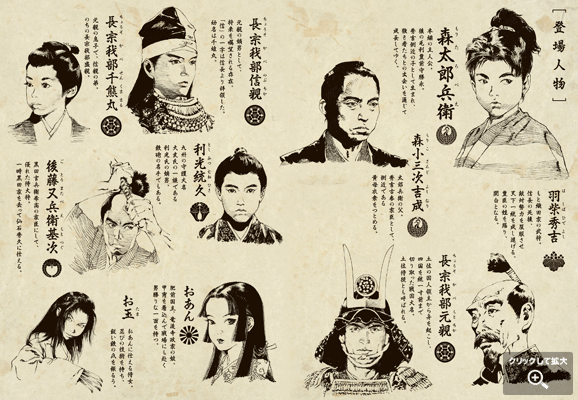
著者 仁木英之

1973年大阪生まれ。2006年、中華ファンタジー『僕僕先生』で日本ファンタジーノベル大賞を授賞し、デビュー。同作は現在も続く大ヒットシリーズとなっている。他の代表作に、『千里伝』シリーズ、『くるすの残光』シリーズ、『我ニ救国ノ策アリ』など。
Illustration 山田章博

イラストレーター、漫画家。小野不由美『十二国記』のカバーイラスト、アニメ『ラーゼフォン』のキャラクター原案、漫画『Beast of East』などを手がける。その流麗な筆致と美麗な色彩は、見る者全てを魅了する。

地獄、というのは恐ろしい場所であるらしい。生前の行いに従って閻魔の裁きを受け、その罪業が甚だしと断じられれば、永遠に等しい時を苦痛の中ですごさなければならない。
それ故に、誰もが行くことを望まない。
だが一方で、地獄は極楽にも繋がるとも彼は聞いている。地獄から遥かに昇っていけば、やがて光の射す浄土へと道が続いている。どれほど激しい罰を受けても、人はやがて償いを終えて輪廻へ戻り、解脱の機会を与えられるのだ。
毛利豊前守勝永が天王寺に敷かれた陣の先頭に立って敵陣を見回すと、水牛の大角を模した兜が陽光を受けて白く輝いている。
慶長二十(一六一五)年五月七日の夜が明けた。
天王寺から住吉、平野にかけて布陣した徳川方の大軍勢は、しんと静まり返って折敷いている。だが、一たび立ち上がればこちらを噛み砕こうと牙を剥くはずだ。戦場の見せる惨い姿を彼は何度も見てきたし、そのただ中にも身を置いた。
砕ける骨と噴き出る血が戦場を塞ぎ、死の間際にひり出される糞尿の臭いが鼻を曲げる。苦痛にさいなまれる呻きは延々と響き渡り、槍の穂先や銃弾が甲冑を貫く音はいつまでも胸に残るのだ。
そして、一方的に滅ぼされる戦場ほど酷いものはない。死は敬されず、馬蹄と草鞋の下で何度も蹂躙される。それが地獄でなくて何だ。だが、彼は三十年もの間戦場を往来してきて、理解したことがある。
地獄は美しい。
血と糞尿の悪臭に満ちたこの地獄絵図は、新しき世の揺り篭だ。死後の地獄はどうか知らぬが、この世の地獄には美しさもあるのだ。
これは滅びではない。国生みの舞いだ。
そうだろう?
勝永は霞むほどの大軍の向こうにいるはずの男に向かって呼びかけた。そして、後ろを振り返った。金色に輝く五層の天守は天下を夢見た、父として兄として、敬して愛した男たちの巨大な足跡だ。
太閤豊臣秀吉の黄母衣衆として主君に一生を捧げた父、毛利壱岐守吉成の血が自分には流れている。そして、太閤秀吉の大いなる志を守ろうとした石田治部少輔三成の心を受け継いだのも自分だ、という誇りが彼の中に満ちていた。
恐ろしいという気持ちは、もう勝永の中になかった。ただ本意を遂げる喜びだけが心に満ちていた。彼は本当に舞い始めたい心を抑えて、
「かくも集まったり二十万」
と吟じた。周囲の将兵はぎょっとした顔で大将の顔を見る。どの顔も、決戦を前にして緊張を隠せないでいた。
「大きいな」
勝永が将士を見回してにこりと笑ったので、兵たちは心配そうに顔を見合わせた。
「父上?」
嫡男の式部少輔勝家が皆の心配を代表して、探るように言った。
「実に大きいではないか」
晴れやかな顔で勝永が答える。
「それは敵が、でございますか」
「違う。我々が、だ」
息子の不安を吹き飛ばすような微笑を勝永は浮かべた。
「大坂方には数万の味方が健在だ。右府さまはいまだお城で健在。真田左衛門佐信繁どの、明石掃部頭全登どの、長宗我部土佐守盛親どのをはじめとする諸将や、古い付き合いの七手組や大野兄弟も、これまでになく晴れがましい出陣だよ」
勝永はにこりと笑い、不安げな表情を隠せなくなっていた息子の肩を叩いた。
「硬いな。戦では強いだけではいかん。柔らかくないと」
「御意にございます」
大きく呼吸をして、息子は凛とした声で答えた。
「だからそれが硬いのだ。我らは義を貫き、天下を手に入れようとする者を相手に決戦を挑む。これこそ武者の本懐だ。違うか」
勝家も弾けるような笑顔を見せた。
「これに勝るものはありません。なあ皆の衆!」
緊張に身を強張らせていた将兵たちも兜を揺らせて笑いさざめき、頷き合った。
「大きい、大きい。さらに大きくなったぞ。これで大御所や将軍の気概にも負けぬであろうよ」
勝永の麾下は三千ほどであったが、目の前の本多忠朝勢を飲み込むような喝采を上げた。
「関ヶ原の前に伏見で槍を合わせたあの男と、こうして決戦の日に相対するとはこれも縁よな。大いに遊ぼうよ」
忠朝だけではない。勝永に強き男の姿を見せてくれた立花侍従宗茂も、家康の本陣近くにいるはずだ。
勝永は満足げに呟くと、秀頼から拝領した錦の陣羽織に袖を通した。華やかな武者振りを、兵たちは眩しげに見上げている。
戦を通じて得た多くの友が大坂に集っている。生まれて初めて彼に戦を見せてくれた男、後藤隠岐守又兵衛は、一日先に逝った。華々しくこの世を後にした。素晴らしい命の終え方だ、と勝永は思った。だが自分は、そうはしない。
「太郎兵衛、お前は寿命をまっとうした後にどこに行きたいか」
「極楽に行きとうございます」
父の剽げた口調に、勝家も軽口で返した。
「俺はな、ここに居続けるよ」
「は?」
「ここは修羅の地だ。もしかしたら、地獄におるのかもしれん。だがこの地獄で、人は己の手で世を変えることができる」
「そのようなことができるのは、天下人だけではないのですか」
それはどうかな、と勝永は楽しげに言った。
「地獄の後に何が残って始まるのかを、この目で見続けてやるのさ」
「はっ! 我らが勝利し、新たな天下を作りましょう!」
勝家は嬉しそうに応じたが、勝永はそれに頷かず穏やかな表情を浮かべているのみであった。そこに、
「敵に動きあり!」
と伝令が駆けこんできた。
備えよ、と勝永が命じると、既に戦意をみなぎらせた将兵が喊声で応じる。
「新しき世を産む前に、美しき地獄を見ろよ、家康」
誰にも聞こえぬよう呟き、勝永は晴れ晴れとした表情で大槍の鞘を払った。
第一章 石合戦
一
限りなく広い湖の上に、緑に萌える竹生島が見える。盛夏の太陽が放つ激しい光を受けた水面は、目を眩ませるほどである。だが、その緑は激しくきらめく光の中でも、声高に己があることを叫んでいるかのようであった。
天正十(一五八二)年六月の蒸し暑い空気が、八百八水を集めてたたずむ近江の大湖、琵琶湖を覆い尽くしている。焦げたように黒く日に焼けた少年が、蘆原の中で息を潜めていた。
密に茂った蘆の間から望む湖面は果てしない。少年は遥かに望む島から目を離して浜に目を戻す。微かに波だち、さざめくよう明滅する水面を眺めながら屈むと、足元から無造作に一つの石を拾い上げた。手の中で形と重さを量り、捨てる。同じ動きを何度か繰り返し、ようやく立ち上がった。
数十人の子供が、湖畔の砂利を踏んで石を投げ合い、左右に駆けまわっている。二手に分かれて押し合い、やがて一方が引き始めた。
彼は蘆原にじっとうずくまったまま動かない。動かずにいると、風が耳に届く。風は浜の喧騒と水際を撫でる波音と、蘆原のそよぎを交えて彼を楽しませた。
子供たちの様子をうかがうと、一方の優勢はもはや揺るがない。頭や腕を押さえて数人が湖畔にうずくまり、声を上げて泣いている者もいる。空中をいくつもの礫が飛びかい、数人は両手を広げて組み合っていた。
勝ちに乗じている者たちの後ろには、一際体の大きな少年が悠然と足を運んでいる。歩きつつ、歴戦の武将のように破れた扇を左右にうち振り、配下の者たちを追いつかっていた。
「助左衛門、甚之丞、様子はどうだった」
少年は蘆をかき分けてやってきた年かさの少年二人に訊ねる。
「こちらに気付いてはいないようです」
助左衛門と呼ばれた四角い顔をした少年が緊張した面持ちで答えた。
「助のやつ、見つかりかけてましたけどね」
「甚は黙ってろって。お前だって俺の後ろに隠れてただけじゃないか」
そのすぐ後ろについていた細面の宮田甚之丞がからかうと、杉助左衛門は拳を振り上げた。
「やめろよ」
少年は二人をたしなめると、手の中にある石をもう一度握り直す。形は丸く小さく、それほど重くない。少年は蘆原からそっと体を出し、大きな背中に目をやった。
腕を振りかぶり、体を反らす。弓なりにしなった体から放たれた石はまっすぐに標的へと向かう。だが少年は、石の後を追うように走り出した。敵の総大将の頭に石が当たり、怒りの形相で振り向いた刹那、少年は相手の腰のあたりに組みついた。
砂利に倒れたはずみで、上を取ったはずが取り返されている。
「太郎兵衛、やりやがったな!」
石が当たった傷から、血が一筋垂れる。転げ回った時にその血が顔中に広がり、赤鬼のような形相になった敵の総大将は、拳を振り上げる。
「今日という今日は許さんぞ!」
少年は鼻っ柱に振り下ろされた拳に、とっさに顎を思いっきり引く。大きな拳と黒い頭がぶつかり、悲鳴を上げたのは総大将の方だった。太郎兵衛と呼ばれた少年はその隙に体を起こし、もう一度頭から総大将の顎を目がけて跳躍する。
鈍い音とともに仰向けに倒れた総大将を見て、配下の少年たちが慌てたように騒ぎたてた。
「き、吉兵衛さま、大事ないですか!」
そうは言うものの、総大将に奇襲をかけた真っ黒な少年を恐れたのか遠巻きに声をかけるばかりである。
「何をしている。早く太郎兵衛を捕まえちまえ!」
鼻血も垂らしながら配下たちに命ずる総大将に向かって、太郎兵衛はためらいなく突進した。だが今度は、吉兵衛の方も反撃に出た。体に似合わずひらりとその突進を躱すと、肩口を掴み足を飛ばす、すると太郎兵衛はほぼ空中で一回転して地面に叩きつけられた。次の瞬間には、馬乗りにされて喉元を扼されている。
「正面から俺に勝てるわけないだろ」
勝利を確信した吉兵衛は、口元に満足げな笑みを浮かべる。
「ほら、参ったと言え。焦げ坊主!」
二人の少年はどちらもよく日に焼けているが、太郎兵衛の方がより黒い。
「参るかよ」
太郎兵衛はかすれた声で言い返すと、吉兵衛の股間を蹴りあげた。だがその脛に激痛が走る。
「お前のやりそうなことはお見通しよ。ほれ」
吉兵衛が裾をまくると、褌の上に鉢金が結びつけられてある。
「いつも不意打ちばかりしやがって。そう何度も引っかかると……」
そこまで言った吉兵衛は牛蛙の鳴き声のような音を発してひっくり返る。勝利に驕っているうちに、顎先に頭突きを食らって目を回していた。
太郎兵衛はゆっくりと立ち上がると、周囲を見回した。いつしか、劣勢だった味方が吉兵衛とその配下たちを取り囲んでいる。その先頭に立っているのは、太郎兵衛に仕える杉助左衛門と宮田甚之丞の二人であった。
取り囲まれた方は口々に参った、参り申したと言い、太郎兵衛はそこで初めてにっと笑った。焦げ坊主にふさわしくないほどに、白い歯である。
「お見事」
「あっぱれ」
と年上の少年たちに称賛されつつ太郎兵衛は胸を張って湖畔を後にする。
「うちの若殿さまをへこませるとは、大したもんだ」
意気揚々と街に戻る太郎兵衛の前に、馬が立ち塞がった。裸馬に乗っているのは、瀟洒な鶴の文様が入った小袖を身に付けた若者だ。
「鼻っ柱の強い若だから、たまにゃああおのけに転んでお天道様を拝めばいいのよ」
と哄笑する。そう言って、若者は太郎兵衛に手を差し出した。
「播磨は神代の後藤又兵衛だ。黒田の若についてここまで来た」
「森太郎兵衛」
太郎兵衛が手を握り返すと、又兵衛は軽々と彼を馬の上に引き上げた。馬の背は、五歳の子供にすると相当高い。太郎兵衛は悲鳴こそ上げなかったが、思わず又兵衛の腰を強く掴んだ。
「不意打ちで敵の大将を討ち取る勇士にしては心細いことだ」
又兵衛が言ったので、太郎兵衛はすぐに手を離した。
「気にするなって。俺もお前くらいの時には、馬に乗せてももらえなかった。何せ家が貧しくて、父上しか馬をもっていなかったからな」
軽く馬腹を蹴ると、馬はだく足で進みだした。それだけでも、太郎兵衛からは風を切って飛ぶほどに速く感じられる。
「森っていうと、勝蔵長可どのか、それとも黄母衣衆の小三次どのか」
森長可の父の可成は浅井、朝倉との戦いの最中、近江宇佐山で戦死した。長可は十三歳にして家督を継ぐと織田信長の寵愛を受け、人並み外れた武勇で数々の戦功を立てている。太郎兵衛が黒田吉兵衛、後の長政に頭突きをかましている頃、長可は信濃平定の後に越後へと攻め込んでいる。
もう一人、又兵衛が名前を挙げた黄母衣衆の森小三次は、名を吉成という。幼い頃から美濃の野伏せりとして暮らしてきたが、秀吉に出会って人生が一変した。常に秀吉の近くに仕え、使者の任を多く任されている。大禄を与えられているわけではないが、その信任は厚かった。
「黄母衣衆」
と太郎兵衛はそれだけ答えた。
「おお、そうか」
嬉しそうに、又兵衛は体を揺らした。
「お父上には随分と世話になっている」
黒田吉兵衛は、播磨宍粟郡の山崎城主、黒田官兵衛孝高の嫡男である。人質として羽柴秀吉の治める長浜に送られ、数年を過ごした。
摂津の荒木村重の謀反に巻き込まれ、村重を説得しようとして捕らえられたが、竹中重治の機転によって救われ、村重の一件が終わってからは播磨に帰ることを許されている。秀吉の中国攻めに合わせて、吉兵衛は再び長浜に送られていた。
覇気に溢れた十四歳の吉兵衛は、たびたび城下の子弟を集めては石合戦を催している。彼に匹敵する将領は長浜におらず、大抵は圧勝するのであるが、時に太郎兵衛の奇襲にあって、痛い目に遭わされていた。
「中国攻めの首尾はどうだ」
近江の長浜はこの時主戦場になっている備州から遠く、詳細な戦況はなかなか入って来ない。故郷を後にして、遠く近江まで来ている後藤又兵衛にしても、もどかしいところである。
「わからない」
太郎兵衛はまだ五歳である。父の森小三次吉成は主君の秀吉について中国攻めに参加しているが、太郎兵衛自身はもちろん留守番である。詳しい戦況がわかるはずもない。
中国攻めは、長らく苦しめられた本願寺を鎮圧し畿内を手中に収めた信長が、天下布武を実現させるべく起こした大戦であった。天正四(一五七六)年から始まった征西は、途中荒木村重の反乱によって中断を余儀なくされながらも、着実に進められつつあった。
信長が秀吉に課したのは、播磨、因幡、備前、備中を平定し、中国地方に覇を唱える毛利を抑えることであった。秀吉と幕僚陣は毛利側の名将である吉川元春、小早川隆景と智勇の限りを尽くした戦いを繰り広げている。
そんな中でも、秀吉は時を惜しまずに毛利方の拠点を着実に攻略していた。天正七(一五七九)年に宇喜多直家を屈服させ、同八(一五八〇)年には播磨三木と但馬を、そして同九(一五八一)年には鳥取城、続いて淡路を手中に収めている。太郎兵衛の父である森小三次吉成は常に秀吉の身辺に侍り、四方の勢力との交渉に奔走していたが、幼い太郎兵衛は知る由もない。
彼は物ごころがつくなり、山や湖を駆けまわり、陽光を吸い込んだ肌は瞬く間に黒く焼けた。最近では石合戦にも参加し、すばしっこさを生かして物陰に潜み、敵の総大将に奇襲をかけることを常としていた。
「若のお守じゃなくて、先鋒で戦いたかったな」
後藤又兵衛は無念そうに呟く。彼とて二十二の若者である。
「だからと言って、石合戦に交ざるわけにもいかんしな」
「石合戦、面白いよ」
太郎兵衛は自分がもっとも楽しみにしている遊びを馬鹿にされたような気がして、頬を膨らませた。
「実際の合戦はもっと面白いんだぞ」
又兵衛は血が滾ってきたのか、手綱を緩めて馬を走らせた。太郎兵衛は慌てて又兵衛の腰にしがみつく。
「今でこそ種子島で勝負がつくご時世になってしまったが、やはり弓矢と槍をぶつけ合って功を立てることこそ男子の本懐だよ。しかし何で武勇誉れの俺が若のお守をして近江におらねばならんのだ。播磨からすぐ近くで大戦が起こっているというのに」
口惜しげに馬を叩いた又兵衛の視界に、長浜の街がはっきりと見えてきた。
「戦国の世はもう終わるかも知れないってのによ」
と唸るように呟いた。
二
又兵衛がそう感じるのは、天下にはかつてないほどに力を持った武将が現れたからだ。その男こそ、織田信長である。
後に聡明の代名詞のように扱われる信長が、阿呆のように振舞っていたのは何故か。彼は後にもしばしば見せるように、果断の裏の繊細、残酷の裏の優しさ、といったように出会う者を戸惑わせる表裏があった。
表裏の差は、言うなれば滝である。
滝は落差があるほど、そこに流れる水量が多くなるほど、激しいものとなる。落差も水量も多くなれば、滝は己の身を削ることになるし、その近くにいる者は水煙に覆われて、その正体を見極められない。
信長は若い頃、己が持つ大瀑布の正体を自分でも理解できなかったのであろう。ただ、奔放に振舞うことによってしか、その奔流を表現できなかった。
何とか家督を継いだ彼にとって幸いなことに、その激しさを戦わせる相手に事欠かなかった。遠江の今川、美濃の斎藤、越前の朝倉、伊勢の北畠、と四方と争い、睦み合っているうちに、自分がどこにいるかに気付いた。
天下である。
天が下には無限とも思える広野が広がっている。彼は己が天下という器の中で縦横に疾走している時だけ、束の間の満足を感じることができた。早いうちから天下布武という印を使いだしたのも、己の器は天下でしかあり得ないという気概の表れである。
天正十年夏の時点で、彼の前に立ちはだかっていたのが中国の毛利である。大いに自家の勢力を拡大させた名君、元就は既に世を去っていた。だが、残された吉川元春、小早川隆景をはじめとする諸将は跡継ぎの輝元を盛り立てしぶとい抵抗を見せていた。
信長は中国攻略を焦ってこそいなかったが、急いではいた。彼の意は備州にとどまらず、既に九州を視野に入れている。丹羽長秀や明智光秀に九州の古い名族の姓、惟住や惟任を与えたのは西への強い意志の表れであった。
中国攻略を任された秀吉は着実に成果を挙げており、太郎兵衛の父、小三次吉成も黄母衣衆の一人として従軍している。
だが、備中高松城で清水宗治の頑強な抵抗に遭ってその足取りは止められていた。小早川隆景配下の将である彼は、秀吉のあらゆる工作を跳ね返し、備中高松城に立て篭っている。
信長に増援を願った秀吉は、もちろん四方の情勢を知らなかったわけではない。北陸も関東も多事多難で、大軍を送ってもらえないことはわかっていた。
だが信長自身か、もしくは畿内に駐留する光秀の軍勢を回してもらえば士気は上がり、何より毛利方の士気をくじくことができると考えていた。明智光秀が一万三千の兵を率いて西上を開始すると聞いて、秀吉は胸を撫で下ろしていたものだ。
明智光秀は、信長の天下を広めるのに大きな功績があった。美濃の名家の出であり、足利義昭と信長を繋いだのは彼である。謀略にすぐれ、かつ軍を率いては強く、そして政にも長けていた。
信長にとっては実に使える男だったのである。使える者に対しては、厚く遇するのが信長の流儀ではある。足利義昭の利用価値は徐々に下がっていったが、それは信長の光秀に対する評価が下がったことを意味しない。
京に近い近江に一万以上の軍勢を持つ光秀がいることには大きな意味がある。畿内はほぼ平定されたとはいえ、小さな抵抗は各所にあった。さらに、荒木村重の反乱以降、畿内でも何が起こるかわからぬという危惧もある。
だが、秀吉への救援の必要性は、その危惧を上回った。ここで備中高松城を抜けず、中国での戦線が後退することになれば、西への道はさらに遠ざかることになる。逆に、明智軍が秀吉と合流して毛利を屈服させることができれば、中国の情勢は大いに変わる。
「明智どのは織田軍の中でも抜群の強さだ。これで毛利が負けちまったら、天下の戦は終わりだぜ。俺の槍先がどこにも届かないまま大戦が終わるなんて我慢ならねえ」
「まだまだ戦は続くって、父上は言っていたよ」
事情はよくわかっていないながら、太郎兵衛は又兵衛を慰めるのであった。
「若はここにおいていてもいいから、俺を中国攻めに連れて行ってくれないかな」
戦功は戦いのあるところにある。功は敵が強いほど大きくなり、強敵が減るほど大功を立てる機会は減る。毛利を屈服させると、残るは大友や竜造寺、島津など九州の雄たちが雪崩を打って信長に屈服するのではないかと又兵衛は心配していた。事実、大友は既に信長に誼を通じていると噂になっていた。
又兵衛の焦りは日に日に募るばかりであった。
琵琶湖に面した長浜城は西の戦場がうそのように静まり返っている。秀吉は城下に商人を呼びよせ、信長にならって楽市を敷いている。四方から集った商人が市をなし、賑わいがまた人を呼ぶ。
市では怪しげな鍋や肉の屋台に交じり、焼餅の店もあった。
「おい、太郎兵衛。餅でも食うか」
又兵衛は馬を下りると、芳しい香りを振りまいている焼餅を求めて太郎兵衛に渡した。醤油の匂いに釣られて唾が湧き出し、太郎兵衛は大口を開けてかぶりついた。
「俺は酒を呑む。呑まないとやっとれんわ」
小袖をまくると、太い綱をより合わせたような筋肉が露わになった。太郎兵衛の父の小三次吉成は槍の名手であるが、小柄で一見貧相に見える。だが又兵衛は体も大きく、腕も太い。太郎兵衛はそれが珍しくて、思わず指でつついていた。
「おお、びっくりした」
急につつかれて、又兵衛は驚いて杯を落としそうになった。
「この腕は中国無双だ。俺に槍をつけて無事だった奴はいないぞ」
と力を入れてみせる。荒縄のような筋肉がぐりぐりと動いて、太郎兵衛は目を瞠った。
「槍も刀も力がなければ自在には使えぬからな。お前はまだ幼くて槍など持つのは先の話だろうが、鍛えておけよ」
誇らしげに腕を叩くと袖の中にしまった。
二人がのんびりと茶屋の軒先に座っていると、若者の一団が道一杯に広がって歩いて来る。よく見ると、石合戦の相手方である。太郎兵衛に気付いて手を振る者もいたが、又兵衛の顔を見て、ついと目を逸らせた。
「そんなに怖がらなくてもいいじゃないかよ、なあ」
「何かしたの?」
「喧嘩を売られたら買わずにおれなくてね。年下の者が相手でもちょっと強めにやってしまうんだ」
照れ臭そうに頭をかく。数十人からなる若者たちの群れに、町の人々は因縁をつけられないよう微妙に距離をとってやり過ごしている。その集団がふいに足を止めた。
「おい」
中心にいたのは、又兵衛の主である黒田吉兵衛であった。だが又兵衛は杯を空けながら軽く頭を下げたのみであった。
「何故俺に加勢しない。お前が護衛をしないからそこの子供に不意打ちを食らったではないか。俺の臣下であるなら拳骨の一発でもやっておけ」
吉兵衛はきつい口調で命じる。だが又兵衛は、聞くなりげらげらと笑いだした。
「加勢でございますか。戦場のことなれば、いくらでも加勢いたしましょう。ですが吉兵衛さまのそれは遊びではありませんか」
言葉は丁寧だが、口調は明らかに嘲っていた。
「それに、これなるはたとえ遊びとはいえ敵の総大将の懐深く踏み込み、その背後をとった真の勇士です。戦場においては年も位も関係ない。その武勇は吉兵衛さまなど足元にも及ばぬ天晴なもの。そのようなもののふに辱めを与えることはできませんな」
と言い放つ。
「お前、主君に喧嘩を売っているのか」
「勘違いされては困ります。俺が仕えているのは官兵衛さまであって、あんたじゃない」
又兵衛は既に、立ち上がっていた。戦いに飢えた若者の肉体は喧嘩への期待に膨れ上がっているように、太郎兵衛には見えた。
吉兵衛も子供の中では相当に大柄だが、又兵衛とはまとう気配が全く違っていた。
「喧嘩なら買いますよ」
「城下でそんなみっともない真似ができるか!」
「みっともない目に遭うのは吉兵衛さまだけですな」
吉兵衛は忌々しげに又兵衛を睨みつけ、城の方へと去っていく。一応は国元からの使いという名目で来ているので、宿は城内の一角にある。又兵衛が声を抑えて笑いながらその背中を見送っていると、大路の向こう側から悲鳴が聞こえた。
「おい、あれ黄母衣衆じゃないか」
遠くから見ると黄金色に見える甲冑に、体を覆わんばかりの母衣を背中に結わえた姿は、秀吉側近の証である。母衣とは竹を編んだ物に大きな布をかぶせ、後方からの矢防ぎと指物の役割を持たせたものだ。使い番の証として派手な色の布を使い、秀吉の周囲に侍る者たちは鮮やかな黄色の母衣を与えられている。彼らは秀吉の手足となり、四方への使者となって交渉を任されている精鋭たちであった。
その一人として太郎兵衛の父も働いている。長浜では黄母衣の姿を見れば問答無用で道を空けねばならない。まして馬を疾駆させているとなれば大事が起こっていることは間違いない。そんな時に馬蹄にかけられたと訴え出ても、それは馬前に立つ方が悪いとされた。
「父上だ!」
矢のように城に駆け込んだ騎馬を見て、弾かれたように太郎兵衛は立ち上がった。
三
織田信長が死んだ。
街の人々がそれまでの平穏をかなぐり捨てて荷物をまとめ、逃げまどう姿を見て、
「天下人ってのは大したもんだな。一人死ぬだけでこの騒ぎになるのか」
と又兵衛は感心していた。だが太郎兵衛は怖かった。前の日まで穏やかに笑っていた町の人々が血相を変えて荷を車に積み込んでいるのだ。
「こりゃあ荒れるぞ」
又兵衛は太い腕をぱちんと叩いた。
長浜の町に走った衝撃は、当然として城中の人々の動揺を誘った。中国攻めに参加していたが負傷し、一足先に長浜に帰ったのを契機に城を任されていたのは、木村定重である。
近江蒲生郡の土豪で、秀吉が長浜に赴任してからその家臣となった。親子三代にわたって秀吉に重用され、子の重茲は豊臣秀次の家老となり、孫の重成は大坂城で秀頼の側近として仕えることになる。定重は城の警戒を厳にするとともに、諸将に如何すべきかを諮った。長浜を守る兵は数百に過ぎない。
「右府(信長)さまに変事があったこと、確かに耳には入っていたが」
明智光秀の軍が、信長の宿所であった京の本能寺に攻め入ったとの報は、京に近い長浜に翌日のうちに伝わってはいたが、誰もが確信を持てないでいた。
木村定重は秀吉と何とか連絡を取る方策を探ったが、もし毛利方に使者を捕えられでもしたら主君の命も危うい。
「わしが直接行く」
と周囲には打ち明け、実際にそのように準備もしていた。
光秀は信長の勘気に触れて意気消沈し、恨みを抱いていたとの噂もあるが、秀吉は有名なものだけで二度も信長を激怒させている。その度に家臣たちはひやひやしたものだが、それで秀吉が信長を裏切るなどと思ったことはない。従って城内の諸将は、
「日向守(光秀)さまには昔からの謀があったに違いない」
との結論に達した。
光秀ほどの将であれば、信長の守りが手薄になる機会をじっと待っていたに違いない。だが、直属の軍勢だけで信長亡き後の混乱を収められるとは考えられない。兵力をどこからか持ってこなければならない。
定重たち長浜の留守居たちがすべきことは二つに一つであった。秀吉の主力が中国から帰ってくるまで待つか、乾坤一擲の一撃を加えて華々しく散るかである。
「そのような無駄死にを筑前さまが喜ぶとは思えない」
定重のその一言で、突撃して散華するという策は却下された。
「殿は命の張り方を知らぬ男を嫌う」
秀吉は自ら志願して死地に身を置いたことがある。浅井朝倉の両軍から挟み撃ちを食らった際の、金ケ崎の退き陣である。一歩間違えば命を落としかねない一か八かの戦場であった。
秀吉は見事に賭けに勝ち、名声と信長の信頼を得たものだ。一貫して無駄死にを避け、勝負どころで無謀にも見える賭けに出る主君と共に働いてきた定重は、長浜を自滅させるような挙に出るわけにはいかなかった。
留守居の諸将にはもはや、秀吉本人の指示を仰ぐ他に名案は浮かばない。
だが、連絡をとろうにも街道筋には光秀の手が回っているはずであるし、彼の麾下とみなされている丹後の細川藤孝や大和の筒井順慶も動き出しているのは間違いない。彼らが東西の連絡を断とうとするのは自然であるし、その壁を越えるのは決死行になるに違いなかった。
そこに使いが駆けこんできた。
秀吉近侍の黄母衣衆の一人、森小三次吉成である。体は小さく色は黒く、大柄で色白な木村定重とは対照的である。だが、その体から発せられる闘気ともいえる気配は、兵たちの目を伏せさせるほどのものであった。
吉成は備中高松から馬を乗り継ぎ、休みもとらず駆け続けてきたというのに、泰然として慌てた様子も見せない。
そして定重たちは、秀吉から与えられた命を見て絶句した。
「これから数日のうちに姫路にとって返して京に入るゆえ、長浜留守の者たちは日向守が軍勢を差し向けてくれば無理せず逃げよ」
とあった。数日、というのは当然秀吉がこの書状をしたためてから、ということだから京に入るのはあと二、三日のうちだ。
「筑前さまは気でも違ったか。備中から京まで何里あると思っているのだ」
「数日で帰ると仰ったからには、必ず行うのが我が殿ではないか」
吉成の言葉には揺るぎがない。
「……それもそうだ」
定重も頷く。
「日向守さまの動きはどうか。筑前さまは掴んでおられるのか」
「わからん。ただ、変事を知って数瞬の後には京へ戻られることを決められ、我ら黄母衣衆には畿内の諸軍に伝令に向かうよう命じられた」
定重には備中と京の距離の他に、さらに大きな懸念があった。
「そもそも殿は、毛利に対する援軍を右府さまに求めるほどに苦戦しているではないか」
秀吉の手元には三万の軍勢がいる。だが、四万を超える毛利軍に対するために、信長は光秀を備中に向かわせようとしていたのだ。
「なのに退き陣がうまくいくのか……」
「そこは殿のお手並みだ」
吉成も秀吉がどのような手を打って毛利の目をかすめ、三万もの軍を西に向けるのか見当もつかなかった。ただ、やると言うまでの数瞬で、秀吉の頭に何らかの名案が浮かんだと信じるしかない。
実際、秀吉は大きな博打に出ていた。
備中高松城を守る清水宗治が腹を切って城を開けば、講和を受け入れようと申し入れたのである。忠誠を尽くした将を見殺しにするのは小早川隆景も吉川元春も受け入れがたかった。だが、四万の軍勢をもってしても、秀吉に勝てるかどうか自信もなかったのである。
秀吉の申し出に、ついに毛利方は乗った。
使いに立っていた安国寺恵瓊は、当時、信長が足元をすくわれることを予測するほどの炯眼の持ち主であったが、それでも秀吉の堂々たる態度に騙された。
むしろ、秀吉の態度の変化に安堵していたほどである。ともかく、秀吉は薄氷を踏むような思いで、清水宗治の切腹を見届け、かつ飢えきった城内の兵に施しを与えた。その様は悠然として、恵瓊も後に秀吉に面会した際激賞して見せたほどである。
ともかく、毛利との講和を成立させた秀吉は全軍に、東へ向かい、姫路に着くまで全速力で駆けよと命じた。飯も食うな夜も寝るなという無茶な指示である。この命を受けた秀吉軍の動きも見事であった。
このような命を受けたからには、やりきらねばならんし、成算があるから言っているのだと将兵が信じるほどに秀吉という将は一目置かれていた。
そして瞬く間に退き陣の態勢を整えると、秀吉は整然と東へ向けて軍を動かした。当時の街道は狭く、大軍を一斉に動かすには向いていない。伏兵を置かれてはひとたまりもないが、表面上は平然と、撤退ではなく作戦の一環として移動していると全将兵が姫路に至るまで信じ込ませていた。
もちろん、使者を先行させて街道脇の村々に炊き出しをさせ、全力で駆けさせたのは言うまでもない。将兵もこの男についていれば、飢えることなく走れるとわかっているのである。
通常、行軍速度は一日六里程度である。しかし、六月六日午後に備中高松城を後にした秀吉軍は、途中に難所の船坂峠があり、さらに豪雨にみまわれたにもかかわらず、六月八日中には姫路に達していた。特に備前沼城から十八里を駆け抜けた速さは、尋常ではない。
姫路に着いた秀吉は、ついにその意図を明らかにした。
四
長浜城に残された将兵たちは、昂る期待と不安に顔を見合わせていた。
天下様として君臨しつつあった信長が、こうもあっさりと世を去るとは誰も思っていなかったほどに、その存在は大きくなっていた。
「戦になる」
顔を合わせれば、男も女もそう囁き合った。それも、これまでとは違う、天下を奪い合う大戦だ。もちろん、歓迎する者もいた。
「腕が鳴る!」
後藤又兵衛は、自分もその大戦に参加できるものと思い込んでいた。播磨の将、黒田官兵衛孝高の息子、黒田吉兵衛の随員として長浜に来ている。孝高は秀吉の信任が厚く、又兵衛はその武勇を孝高に高く買われていた。
「俺が行かなければ始まらん」
とすら、又兵衛は太郎兵衛に豪語していた。だが、秀吉軍が姫路を発したとの噂が流れても、長浜には何の命も下されなかった。
「どうなってるのか、お城の様子を訊いてくれんか」
苛立つ又兵衛は、大きな体を折り曲げるようにして太郎兵衛に頼みこんだ。だが、石合戦では表情一つ変えず総大将の背後をとった太郎兵衛が、あからさまに嫌な顔をした。
「できない」
とにべもなく断ったのである。
「どうしてだよ。お前の父君は黄母衣衆なんだろ」
「お勤めのことを訊くと叱られる」
「ああ……」
確かに、と又兵衛も納得はできた。黄母衣衆が扱うのは、秀吉の帷幕の中でも、もっとも秘密を要するものである。子供であっても、漏らすことは許されないのは当然であった。だがこれで諦める又兵衛ではない。
「なにも俺は秘密が知りたいというわけではない。陣に加わりたいだけだ。そう言ってくれんか」
「言えない。自分で言って」
太郎兵衛は又兵衛が戦に出ると活躍しそうということくらいはわかるが、怖い父にものを頼むにはどうすべきか知らない。
又兵衛は森家の門を叩き、秀吉から預かった命を城に伝えてようやく一息ついている吉成を訪ねた。
「筑前守さまはどこで日向守を叩くおつもりか」
と思い切ったことを訊く。
「それは私の思慮の外だ。たとえ知っていたとしても、あなたに教えるわけにはいかない」
「わかっています。ですが、この大事を前にして槍を振るえないことは武門の恥。どうしても教えていただきたい。教えていただけぬのであれば一人京に上って馬前に馳せ参じ、筑前守さまに願って先鋒となる所存です」
「ご随意に」
吉成はすげなく応じる。
「言っておくが、武門の務めとは何か。それは主命を奉じて全うすることである。目の前に戦があるからといって功に逸り、一騎駆けの無謀に憧れることこそ恥と心得られよ」
六尺はありそうな大柄な又兵衛の前では、吉成は実に小さく見える。だが太郎兵衛は二人が向き合っている姿を見ているだけで、これは父の方が強そうだと感じた。
「あなたは黒田官兵衛どののご子息に従ってここに参られた。主君の子を守りきることは、戦場で敵の首を挙げることに何ほども劣らない。その務めを捨てて一騎駆けを望むなど、それは匹夫の勇であって武門の誉れではないのだ」
吉成に諭されているうちに、又兵衛の首は徐々にうなだれてきた。
「我らは中国攻めに加わっている者たちの家族、そして質に送られている者たちを連れて長浜を出る。東の七尾山に築いた出城にこもり、殿の援護を待つ」
「では戦は」
「手出しされぬ限り一切せぬ」
二人の間に沈黙が流れ、太郎兵衛は覗き見を止めて屋敷の外に出た。
石合戦は当分なさそうであった。長浜の町は間近に迫った戦の予感に、興奮を抑えきれないように見えた。
足軽たちは具足を身につけ、騎馬武者の下知に従って城の各所へと駆けていく。商人は商品を売り切ると早々に市を後にして去った。町の人々も年寄に先導されて城へと入っていく。
長浜は光秀の城、近江坂本にも京にも近い位置にあり、いつその軍勢が攻め寄せて来るかわからない。留守を任された諸将は、長浜を捨てることを決めていた。
つまらないな、と石を蹴りながら太郎兵衛は路地の端を歩く。指物もない一人の武者が辺りをうかがうように馬を進めていた。怪しい奴、と礫を一つ拾って、大きく振りかぶる。体と腕をしならせて力一杯投げると、礫は騎馬武者の鉢金に当たってしまった。
がん、と鈍い金属音がして武者はよろける。慌てて身を隠した太郎兵衛であったが、すぐに襟首を掴まれた。
「何しやがる」
と面頬の下から怖い顔で睨みつけてきたその武者は、太郎兵衛の顔を見て拍子抜けしたような表情になった。
「俺だよ、俺」
その声は後藤又兵衛のものであった。
「出陣?」
父に行くなと諭されたはずの又兵衛が戦装束なのを見て、太郎兵衛は首を傾げた。
「勝手に行くのさ」
「そんなことしていいの?」
太郎兵衛が無邪気に訊くと、又兵衛もきまりの悪そうな顔をした。
「駄目なんだがな、今は天下の大事だ。小三次どのには叱られたが、こんなところで若殿のお守をしているくらいなら、槍をとって名を揚げる方がよほどお家のためになる。要は惟任日向守の首級を挙げればいいのだ!」
自分に言い聞かせるように叫ぶと、黒塗りの大槍を掲げて見せた。忙しげに街路を行く町人たちがぎょっとした顔で又兵衛を見上げ、関わり合いになるのを恐れるように早足で駆け去った。
「では行ってくるぞ」
からからと笑うと、又兵衛は長浜の大路を堂々と一騎進んで出立しようとした。だが馬首を廻らせ太郎兵衛のところへ戻ってくると、
「お前はどうする」
と訊ねた。
「どうするって?」
「一緒に来ないか。戦場に行くのに供回りも連れて行かないのはみっともない。かといって、吉兵衛さまの耳に入ったらまたやかましいことを言われるに違いないからな。それに、俺が武功を立てたらその証人となる者がいる」
そう誘われて、太郎兵衛の心は波立った。
「お前がこれから強い武者になるには、戦場を知らねばならんぞ」
太郎兵衛はまだ五歳であるから、もちろん戦場は知らない。だが石合戦に何度も交わるうちに、本当の戦場を見たくなっていた。父は秀吉について四方へ出征して家にいることの方が少ないし、勤めのことは一切口にしない。
ただ、父は城持ちでも何でもなく、屋敷も桧皮葺のあばら屋に住んでいるというのに、城内の者が父を軽んじることはなかった。秀吉配下の猛者達はもちろん、その同輩ですら吉成を訪れると丁重な物腰で用件を伝えていく。
城下では知らぬ者もいない将領が、親しく父に接しているのは太郎兵衛には誇らしくもあり、また謎でもあった。その秘密が戦場にあるのだろう、と漠然と考えているのみだ。
その戦場を又兵衛が見せてくれるというのだ。もちろん太郎兵衛は、本当の戦場がどのような場所か、まだ知らない。
「行く!」
と弾けるように答えると、又兵衛は嬉しそうに頷いた。
五
又兵衛は城外の茂みに潜み、何かをじっと待っていた。
「小三次どのは決して口にせぬだろうが、黄母衣衆は筑前さまの傍に侍るのが務めだ。長浜への使者の任を終えれば必ず本陣に戻るだろう」
その後をつけるのだ、と又兵衛は舌舐めずりをした。やがて黄色の母衣を背中にはためかせた一騎の武者が、長浜の町から駆けだしてくる。馬を乗り換えた吉成が、急ぎ西へと走り去った。
「俺たちも行くぞ!」
又兵衛は勇躍して馬に跨る。太郎兵衛も後鞍に跨らせてもらった。吉成は馬を巧みに操り、街道を疾駆していく。又兵衛は懸命に馬腹を蹴ったが、瞬く間にその姿を見失った。
日は暮れて、あたりは闇に包まれ始める。この当時、鎧を身に付けた武者は恐ろしくもあり、一方で金の成る木でもあった。戦死者から武具をはぎ取り、流通させる市がどの町にもある。
一人で、しかも子連れで街道を彷徨う武者など狩りの対象でしかない。農民、といっても戦国の男は大なり小なり実戦の経験がある。弓も鉄砲も槍も、一人前に使える者が多かった。
そして又兵衛の前には、二十人ほどの男たちが弓と槍を構えて立ち塞がる。
「身ぐるみ置いていかれよ」
脅しの口上も堂々としたものである。太郎兵衛は闇に光る白い目を見て震えあがったが、又兵衛は怖じることなく、
「筑前さまの軍を見なかったか」
と逆に訊ねる始末である。
「その甲冑と槍を渡せば教えてやる」
男たちはじりじりと包囲を狭めてくる。又兵衛はしばらく鼻をうごめかして周囲の匂いを嗅いでいたが、
「よかった。火縄の匂いはしない」
嬉しそうに太郎兵衛に告げた。太郎兵衛も慌てて鼻をひくつかせてみるが、確かに晩夏の湿った土の匂いが漂っているばかりで、煙硝の気配はない。
「ここは見なかったことにしてやる。俺のめでたい出陣を、お前らのような百姓の血で汚すのも下らない。追い剥ぎは戦に敗れて疲れた者を狙うべきで、俺のような勇士を狙うのは命を縮めるだけだぞ」
頭目らしき男はそれに答えず、
「やれ」
と一言命を下した。十数本の矢が唸りをあげて飛び、又兵衛の巨体に迫る。数人が駆けよって、槍を一斉に突き出した。だが鏃の一つも、槍の一本も又兵衛に届くことはない。鏃は全て地に叩き落とされ、槍を突き出した者たちの首は宙を飛んでいた。
「俺はやめろと言ってやったからな。恨むなよ!」
咆哮をあげた又兵衛が槍を投げると、弓を構え直していた者が一人、絶叫もあげずに倒れ伏す。首を飛ばされた男たちの槍を次々に拾い上げ、四方に投げるとその度に賊の命が消え去った。
最後に一人残った頭目は悲鳴をあげて逃げ出すが、又兵衛は馬を走らせて蹄で蹴散らした。大刀を抜いて一閃させると、男は闇の中でも鮮やかな血しぶきを上げて絶命する。
「戦に出ようという武人から物取りをしようというのだから、仕方ない報いだと思えよ」
愛用の槍の穂先をあらためて刃こぼれも歪みもないことに満足した又兵衛は、はっと何かに気付く。
「筑前さまの行き先がわからないままではないか」
がんがんと槍の柄で己の頭を殴った又兵衛は、街道の先を見やりながら思案に沈んだ。
「お、こりゃいかん」
数百人の軍勢が街道を北へと駆け抜け、又兵衛は慌てて身を隠した。桔梗の旗印を押し立てた明智の軍勢が近江の諸城を落とすために軍を送りこんでいるらしい。六月九日の日暮れを迎え、長浜から京へ続く街道には人影もない。
「長浜や佐和山は日向守に取られるだろうが、戦場になるのはもっと西なのかもしれんな。とりあえず京まで行って宿をとろう」
又兵衛は口惜しげに舌打ちした。
「どういうこと?」
「京の前には摂津がある」
又兵衛たちは馬を走らせて佐和山に入っていた。近江の国で後に彦根と呼ばれる地域の城は佐和山にあり、後に石田三成が改築する以前の、素朴な山城である。町は琵琶湖畔に広がり、湖東を走り遥か東北へと連なる東山道の物資を中継する拠点となっていた。明智の軍勢は城に入っているが、町は静まり返っている。
「摂津衆の主力は高山右近と中川清秀の両将だが、この二人の動きが見えない」
大坂、摂津は、織田軍にとってある種の鬼門である。
かつては石山本願寺が拠点とし、長年にわたって信長の西進を妨害し続けた。そして荒木村重の謀反によって、中国攻めはさらに遅れたものだ。
信長も秀吉も、摂津衆の扱いにはかなり神経を遣っていた。秀吉は中川清秀と義兄弟の誓紙を取り交わしたほどである。これは二人の親密さを表すというより、微妙な距離を示しているといってよい。
摂津が明智に与すれば、秀吉の中国大返しは意味をなさなくなるのは間違いなかった。
「丹羽越前守さまと三七信孝さまが堺におられるが、軍を離れられているとの噂だ」
三七は信長の三男信孝のことで、丹羽長秀が後見人としてついていた。又兵衛は知る限りの近畿の情勢を話し続けるが、もはや幼い太郎兵衛の頭では理解できない。
「要は、もともと摂津にいる連中がどちらにつくかで、話は大きく変わるということだ」
摂津は辛うじてわかる。京の南にある、海沿いの町で商いが盛んなところだ。だがわからないことがある。
「摂津の人たちはどうして迷ってるの。悪いのは右府さまを殺した人でしょ?」
「さ、それが大人のずるいところさ」
ことさら分別臭い表情を作って又兵衛は太郎兵衛の頬をつついた。
「大義名分を口では言いながら、裏で損得を考える。かといって損得だけでもないのが困ったところだ。結局は、建前と損得をはかりにかけて、どちらに傾くかと考えているのさ。傾いた先が見苦しいか華々しいか、それだけの違いだ」
「又兵衛はどっちなの」
ふいに太郎兵衛が訊いたものだから、又兵衛は意表を衝かれた顔になった。
「俺か? そうさな……」
しばらく考えていた又兵衛は、
「常に華々しい方を選んでいたいね。筑前さまのようにさ」
「筑前さまは華々しい?」
「そうさ。官兵衛さまがいつも言ってる。あの方は顔は猿だが、その背中に太陽を背負ってらっしゃるとな。俺から見れば、官兵衛さまだって十分すごいんだが、その殿が言うんだから間違いないよ」
そうか、と又兵衛は合点がいったように手を打った。
「月と太陽じゃ勝負にならんよな。筑前さまが太陽なら日向さまは月みたいなお人と官兵衛さまは仰っていた。どちらも空に輝くが、その光はあまりに違う。この戦、勝ったぞ」
わはは、と満足げに笑うと馬の尻に鞭を当てた。
「やっぱりよくわからない」
太郎兵衛は懸命にその背中にしがみつく。もしかしたら明日にも戦場とやらを目に出来るかと思うと、胸が高鳴るのであった。
六
六月十日の夜になって、二人は京に入っていた。相変わらず羽柴軍も明智軍もどこにいて何をしているのか、人によって言うことはばらばらであった。ただ、どうも秀吉の動きに比べると光秀の動きが後手に回っていることは又兵衛にもわかった。
「やはり京を巡って戦うのかな」
天下分け目の戦いとなると、やはり京の奪い合いという印象が又兵衛にはあった。彼も昔話にしか聞いたことはないが、近年でもっとも激しい戦は、応仁年間に京で繰り広げられた。
「京には何があるの」
「そりゃあ……御所があるからな」
当時の皇室は名目上の権威こそ残ってはいたが、貧しさも極まっていた。そんな中、各地の大名に位階を授けたり古今伝授などの古くからの技能を生かして何とか日々を暮らしているのである。
父、信秀の代から引き続いて信長が助けの手を差し伸べたので、朝廷の財政はやや改善していた。だが天下を争う戦の目的が御所か、と言われると又兵衛にもよくわからない。
「それだけ?」
「じゃあ太郎兵衛はどこで戦になると思うんだよ」
又兵衛はむっとしたように訊ねた。だが太郎兵衛にわかるはずもない。京も大坂も彼にとってははるか遠い世界だ。
「やはり京にいよう。日向さまは公方さまに近かったお人だ。天下に号令をかけるとなれば京を押さえようとするはずだし、筑前さまはそれを許さないはずだ」
それに、光秀の居城である近江坂本は京に近い。京を落とされることは、城の喉元に刃を突きつけられるのと同じだ。
京には秀吉と共に黒田家が昵懇にしている豪商の今井宗久の別邸がある。そこでもう一度四方の情勢を探ってから、戦場を見極めるつもりであった。
だが、単騎で槍を提げて街道を行く又兵衛の姿を見ても、誰何する者もいなかった。これには又兵衛も奇妙に感じた。
「もはや戦は終わっているのか?」
と首を傾げつつ進む。京の町に入っても気味が悪いほどに静かで、市で商いをしている者もいない。かといって、日向守の名で出されている高札もなく、誰が京を支配しているのか又兵衛にもわからなかった。
清水寺近くにある今井宗久の別邸を訪れると、当主は堺の本邸にいて不在であった。それでも佐和山にいるよりは情勢もはっきりわかる。宗久の留守を守っている若い商人は、信長が死んだという騒乱の中でも落ち着いているように、又兵衛には見えた。
「商いは何が起こるかわかりませんから。右府さまが日向守さまに弑されたのも、驚きではありますがあり得ぬことではないので」
そう言って、又兵衛に知る限りのことを教えてくれた。
「昨日、筑前さまの本隊は既に尼崎の手前まで到達しているとのことです」
「尼崎……。ということは姫路でしばし休まれたということか」
「はい。尼崎は摂津の西の入り口にあたります。筑前さまは姫路で兵に休みを与え、同時に摂津衆、大和衆の動きを見極められたようです」
中川清秀、高山右近といった摂津衆は、羽柴と明智を秤にかけ、どちらに命運を託すか決断を下したという。
「筑前さまの御運は尽きていない、ということか」
という又兵衛の言葉に商人は頷いた。
「日向守さまがひそかに頼りにしていた細川幽斎、与一郎忠興のご両人、瀬田城の山岡美作守さまなど全て、与力を断りました」
「日向守さまは随分備えがおろそかだったのではないか」
又兵衛は驚きを露わにした。
「日向守さまは思いつきで主君を殺したのではないか。これでは畿内に誰も味方もいないまま、兵を挙げたことになるぞ」
又兵衛は聡明な印象の光秀が破れかぶれの挙に出たとは今でも信じられない。
「もしや、北陸の上杉や四国の長宗我部との密約でもあったのでしょうか」
「その気配はありません。上杉は柴田さまが防いで一進一退の攻防が続いておりますし、長宗我部は丹羽越前守さまの征討を前に防備に忙しいはずですから、海を渡る備えなどないでしょう」
太郎兵衛は退屈になって、庭へと遊びに出た。長浜の屋敷は、必要なもの以外は何もない。茶も歌もやらない吉成は、小ぢんまりとした庭に駄馬を数頭飼っていた。
「このご時世何があるかわからんし、何が役立つかわからん」
というわけで、太郎兵衛の知る庭は馬小屋の建つ獣臭い一角である。
だが、京の今井邸の庭は別天地であった。美しく刈り込まれた松と波をかたどった白砂に、苔で覆われた石が配されている。
「これは海を表しているのだ。水を一滴も使わず、大海を表す。数寄者というのは面白いことを考えるものだ」
太郎兵衛の後ろに、一人の男が立った。聞き憶えのある声だ。
「こんなところで何をしている」
叱っているわけではないが、太郎兵衛がぎくりとするのも無理はなかった。父の親しい友人である山内猪右衛門一豊の声だったからである。
彼は秀吉配下の中で特に吉成と親しい男だ。岩倉織田の重臣であった父を持つが信長に攻められて没落し、後に信長に拾われて秀吉の与力につけられていた。妻の千代、弟の康豊も含めて家族ぐるみの付き合いがある。
「えっと……」
太郎兵衛がこれまでの経緯を頭の中でまとめ、訥々と話し終えるまで猪右衛門はじっと待っていた。
「又兵衛が連れて来てくれたのか。困った奴だ」
猪右衛門は縁に腰を下ろした。
「男子たるものいずれ戦には出るのだから、行くなとは言わん。だが、戦に出ていいのは戦えるだけの力を持ったものだけだ」
「見ているだけでいいって」
「鉛玉も鏃も飛んでくる。少しでも道に迷えば、野盗の類が潜んでいるのだぞ」
と猪右衛門は脅かす。
「野盗は又兵衛がやっつけてくれた」
「あやつの槍に勝てる者はそうそうおらんが、今は一人の武勇ではどうにもならんことも多いからな」
太郎兵衛はこのまま長浜に帰れと言われるのではないか、と身を縮めていた。京に至っても、まだ戦場は目にしていない。
「そういうことなら、俺と筑前さまの本陣に行くか。そこなら安心だろう」
それは気乗りがしなかった。本陣には父がいる。
「何だ、叱られることを怖がっているのか」
微かに笑みを含むと、頬にある大きな傷が形を変えた。天正元(一五七三)年の朝倉攻めの際、顔に鏃を受けながら敵将を組打ちの末討ち取った。猪右衛門武勇の証である。
「猪右衛門さんはどうして京に来たの」
「ああ、俺はお役目をいいつかってな」
秀吉は変を知るなり、すぐに数人の側近を東へ走らせた。そのうちの一人が猪右衛門であったのだ。彼は、かつて瀬田城の山岡氏に仕えていたことがある。
瀬田の山岡氏は南近江を拠点とする国人領主で、それほど大きな勢力を張っていたわけではない。だが柳生や甲賀衆との関係が深く、諜報に力を入れていた信長に重用された。山岡家当主の景隆も、次の天下は信長であろうと見当をつけ、懸命に忠勤に励んだものだ。
だが、秀吉か光秀につくか、という予測はつきがたかった。
もともと足利将軍家や六角氏に近い立場だった山岡景隆が、光秀側についても何ら不思議はない。そこで景隆の人物をよく知る猪右衛門を派した、というわけである。
「だが、俺が行くまでもなかったよ」
世の流れを見極めた山岡景隆と甲賀衆は、瀬田橋を切り落として光秀の誘いを断って見せた。
「心配していた摂津衆も明石どのの説得で筑前さまへの与力を約束したしな」
「明石?」
「ああ、太郎兵衛は知らぬだろうが、摂津の高山どのを動かしてくれた切支丹武者だ」
先ほどから聞こえている調子外れの歌は、明石掃部頭のものであるらしい。
明石掃部頭全登は、備前美作の出である。宇喜多家の家老として活躍している明石景親の子で、熱心な切支丹である。彼は同じ切支丹である高山右近の説得を秀吉から命じられ、急ぎ畿内へと走っていた。
「そちらの方も、うまくいったようだ」
猪右衛門の表情は明るい。
そのうちに、調子外れの異国の歌は終わり、障子が荒々しく開けられた。やたらと縦に長い人だ、と太郎兵衛は思った。
「猪右衛門どの、ご子息かな」
声が大きい。だが歌声の聞きづらさに比べると随分と耳に心地よい通る声だ。
「俺のではないよ。小三次どのの子だ」
へえ、と感心しながら全登は太郎兵衛を抱き上げた。腕は細いが異様に長く、腕と体の間に出来た隙間から落ちそうになる。
「小三次どのは長浜にお住まいではなかったか」
この人も父を知っているのか、と太郎兵衛は驚いた。天下の武士はみな父と顔見知りなのではないか、と思えるほどだ。
「太郎兵衛というのか。お前の父御には随分と世話になっている。宇喜多家をはじめ我が明石家など備前衆が筑前さまに投じる際には、何度か使者に立ってくれた。織田家の使いだからどれほど嵩にかかってくるかと思いきや、実に丁重に我らを扱ってくれたものだよ」
全登は太郎兵衛を庭に下ろすと、
「私は備前に戻るよ。筑前さまが大返しをして毛利が追ってくる気配は今のところないが、いつ変心するかわからん」
と猪右衛門に告げた。
「次に会う時は筑前さまが天下さまにおなりかな」
「そう簡単にはいかんだろうが、右府さまに近づくだろうな。ともあれ、ご武運を。さんたまるや!」
全登は二人に向かって十字を切ると、下手な歌をがなりながら去って行った。
七
又兵衛と太郎兵衛は結局、京の今井邸に二日滞在した。今動くのは危険だと猪右衛門が強く諌めたこともある。京が静かであったのは、光秀が厳しく警戒していたからではあるが、又兵衛を見逃したようにどこか浮足立ってもいた。
太郎兵衛の戦を見たいという願いも、目を血走らせている大人たちに気圧されて消し飛んでしまっていた。
今井宗久たち京や堺の豪商たちは既に秀吉に軍配を上げていたが、だからといって光秀も彼らを敵に回すわけにはいかない。秀吉方の人間が京にいても、みだりに屋敷に踏み込むことは避けていた。
もちろん、京から大坂へ向かう街道は全て封鎖されている。京にいることは黙認されても、堂々と参陣する者を通すとは思えなかった。
「筑前さまはもう富田まで来ているそうだ」
富田は摂津高槻にあり、京のある山城国とは目と鼻の先である。
「そこで軍容を整えて一気に攻勢に出るのであろう」
秀吉は軍を疾駆させたとはいえ、そのまま明智軍に突撃させるような真似をするはずがなかった。
「もはや戦が終わった後の手はずを整えられているだろうな」
という猪右衛門の予想は半ば当たっていた。この戦を私戦と責められることのないよう、周到な手を打っていたのである。それが、織田信孝を総大将とすることであった。
秀吉は信長の晩年には麾下の四天王と目されるまでになっていた。だが、もともと織田家の重鎮である柴田勝家、尾張守護の斯波氏家臣であった丹羽長秀、美濃の名族の出である明智光秀の三人に比べると家格が随分と落ちる。
秀吉はそんな自分の出自に箔をつけるためと、強面の先輩を懐柔するために柴田と丹羽から一文字ずついただいて羽柴と名乗っているほどだ。
しかも丹羽長秀は信孝を戴いている。信長の長子で、資質ももっともすぐれていると目されていた信忠は、本能寺の変の後、村井貞勝らと共に二条御所に立てこもった。だが明智の大軍を防ぎきれず、奮戦の後に世を去った。
次男の信雄が伊勢から伊賀を越えて京に向かっているとの報もあったが、織田家に恨みのある伊賀の国人衆たちに阻まれて、秀吉の本陣とはまだかなりの距離がある。
「ここは三七さまと五郎佐どのに全軍を率いていただきたい」
秀吉は丹羽長秀に対し、軍の全てを譲ると申し出た。これには、普段秀吉を猿め猿めと罵っていた長秀も驚愕した。
「何の面目があって筑前の軍に命を下せようか」
と固辞した。
信孝と長秀は、四国征伐のために堺に本陣を置いて出征の準備を進め、あらかた備えも終わったところで岸和田城主の蜂屋頼隆の接待を受けていた。既に万を超える軍勢の編制が終わり、ほっとしていたところで変事が起きたのだ。
信長の死が伝わった時に、信孝も長秀も堺にいなかったのは痛かった。兵たちは動揺し、明智軍が既に天下の全てを掌握したような風評も流れていた。商人たちはいち早く正確な情勢を捉えて落ち着きを取り戻したが、足軽たちはそうもいかない。
信孝と長秀が堺に帰りついた時には軍勢の多くが逃げ散ってしまい、数分の一になっている。もちろん、彼らが大いに恥入ったことは言うまでもない。
そこに秀吉からの申し出であった。
「わしが総大将になるのは筋目として致し方なし。だが富田に集結している軍の多くが筑前の下知に従って働いてきた者たちである。指揮は筑前が執るべし」
信孝は秀吉にそう言い渡し、長秀も承知したので軍はこれまで通り秀吉が率いることになった。
「さすが殿だ」
話し終えた猪右衛門は感心したように首を振った。
「全軍を失って、天下を得る好機を失いかねない。だが、ここで三七さまと越前守さまが引いてくれれば、織田家筋目として正しく軍を進めることができる」
全てが後手に回る光秀に対し、水際立った手回しの良さであった。
「決戦はしばらく後なのか」
猪右衛門ですらそう思うほどの、京の静けさであった。
八
織田軍精鋭同士の正面衝突である。兵の練度も、与力につけられた将の才にも大きな差はなかった。
光秀には斎藤利三や伊勢貞興などの勇将がいた。兵力に二倍以上の差があり、しかも兵たちの士気が上がらぬ中で互角に渡り合ったことからも、光秀の力量はうかがい知れる。実際、戦の途中までは羽柴軍の損害の方が多かった。
だが、決定的に差があったのが、総大将の断であった。
光秀は、京の手前に引いた防衛線に自信を持っていた。秀吉の猛進には驚いていたが、光秀も同僚が時折見せる目を驚かせるような戦術を知らないわけではない。期待していた大和の筒井順慶が一切の助けを拒んだことは驚いたが、摂津や大和の諸将が情勢によってはいかようにも態度を変えることはよく知っていた。
秀吉を京に入らせず、畿内の諸将を何とかこちらに寝返らせれば、まだ勝機はある。光秀は湖東の諸城、近江の南半分を押さえて持久戦に持ち込むことも考えていた。既に天下人として名乗ることは諦め、足利義昭を担ぎ出すべく使者も出している。
秀吉はそのような悠長なことに付き合うつもりは毛頭なかった。
「こりゃ大事に遅れちまう」
焦った又兵衛はとるものもとりあえず、戦場になると思われる山崎へと馬を走らせた。だが、怪我人や逃げ惑う村人を目にはするものの、又兵衛たちは戦場にたどり着くことは中々できなかった。
途中で中川家中と思しき足軽の一団には出会った。慌ただしく光秀の行方を訊ねると、
「なんでえ、あんた明智縁故かい」
欲に目が眩んだらしい足軽が槍を向けようとするが、又兵衛は一喝した。
「先ほど名乗っただろうが。俺は日向守の首を狙ってるんだよ!」
「そういうことなら」
足軽たちは東を指した。
「まだ残党はかなり残っているみたいだべ。日向守もまだ見つかっていないようだ。精々手柄しな」
もはや近江は残党狩りの場と化していた。佐和山、坂本、長浜の諸城を守っていた明智方の将は逃亡するか降伏したが、もちろん又兵衛も太郎兵衛もそのことを知らない。
「山に入るなら落ち武者狩りに気をつけろよ。このあたりの百姓、隠れてはいるが金目のものを狙って血眼になってるっぺよ」
又兵衛はその話を聞くなり、馬を走らせた。
「どこへ行くの!」
風に負けないよう大声を出さねばならぬほど、又兵衛は馬を急がせている。
「日向守は城のある坂本に帰ろうとするはずだ!」
「どの道を通るかわかるの?」
「そんなのわからねえけど、人目につかなくて一番近い道を通るはずだ」
戦場となった天王山、山崎のあたりは摂津と山城の境となって山がちな地形である。そこから近江坂本に急ごうとすれば、桃山の南を掠めて、近江と山城を隔てる深い山並みに入ってしまうのが得策だ。
「見つけられるのかな」
「それこそ武運だろう」
落ち武者狩りと思しき農民たちを一喝して退けながら、山の中に分け入った。道は狭くなり、身ぐるみ剥がされた武者が無念の形相で倒れている。もはや馬も走らせることはかなわず、又兵衛は槍を担いで身軽に山道を走る。
一刻も走り続けていただろうか、突如銃声が轟いた。又兵衛は太郎兵衛の首根っこを押さえて地面に伏せる。
「痛いよ!」
「死ぬよりましだろ」
又兵衛は地面に伏せてわずかに顔を上げ、周囲の気配を探った。
「山一つ向こうだな」
そう言って駆け出す。太郎兵衛も慌ててその後に続いた。深草を抜けて小さな尾根筋から顔を出すと、又兵衛は足を止めた。眼下には小栗栖の本経寺の伽藍が見えていた。
太郎兵衛も下を覗くと、粗末な具足姿の男が数十人、木立の間を抜けて走っていく。作りの粗い足軽用の槍や、竹槍を持っている者もいる。鉄砲を担いでいる者も二人ほど見えた。
「誰かを追っている……」
その先から怒号が響いてきた。又兵衛は慎重に近づくと、目を瞠った。
「どうも名のある武士の一団らしい」
取り囲まれている方は数人が倒れ、生き残った者たちも傷が深い。みな兜は脱げ落ち、髪を振り乱して必死の形相である。その中央にいる者たちだけが、端坐していた。
「日向守だ……」
「間違いないの?」
「遠目で見たことはあるから、多分」
又兵衛は舌舐めずりをして槍を担ぎ直した。
「殿、早く!」
一人の武者が叫び、それを合図にするように百姓たちが襲いかかった。斬り合いになったが、疲れのためか武者たちは瞬く間に討ち取られていく。だがその時、光秀がすっと立ち上がった。
百姓たちは気圧されたように動きを止めた。光秀はすっと空を見上げた。血と泥にまみれているのに、透き通るような笑みを浮かべていた。太郎兵衛は思わず又兵衛の袖を掴んだ。
「魔王とも称された主君の首をとり、数日といえど天下に覇を唱えた。泥の中に首を落とされることは無念ではない。本意である!」
堂々とした声だ。だが次の瞬間、太い竹槍がその胴を貫いていた。光秀の威風に圧されていた百姓たちも獲物に群がる野犬のように襲いかかる。その様子をじっと見つめていた又兵衛は、
「行こう」
と太郎兵衛を促した。太郎兵衛はどういうわけか、馬に跨って京に帰るまでの間、涙が止まらなかった。
しばらくして光秀が討ち取られたとの報が京にもたらされた。武勇筆頭である明智秀満は反撃を企てたものの、琵琶湖南岸の打ち出の浜で奮戦した後に坂本に戻って自害し、斎藤利三は堅田に潜んでいる際に捕まり、斬首された。
「もはや大した首は残っておらんだろう。戦は終わりだ」
又兵衛はがっくりと肩を落とした。
「俺たちは一歩ずつ遅かったんだ。大坂に着いた時には摂津の情勢は定まり、山崎に着いた時には決戦は済み日向守を見つけた時にはもう落ち武者狩りに囲まれていた」
「そうだね……」
太郎兵衛の脳裏には、光秀の最期が焼きついたように鮮明に残っていた。
何十、何百という死体が、周囲にはあった。無念に目をむき、歯を食いしばり、泥を掴んで息絶えていた。父が仕える人が、こうならなくてよかった、と安堵していた。
「負けなくてよかったね」
全くだ、と又兵衛も頷いた。
「敗れた者たちがいるから、武功を立てる者がいる。俺はどちらかを選べと言われたら、やはり功を立てる方を選ぶ。生きて勝ってこそ男だ。だがそうなるためには、戦に出なきゃならん。天下を争う戦に間に合わず、こうして死んだ者たちを拝んで回るのは、ここで倒れているより情けないことだ」
又兵衛はそう言って太郎兵衛を姫路に置くと、備前へと帰った。父の吉成は家に帰るなり、太郎兵衛の頭に一発拳骨を食らわせたが、それ以上は何も言わなかった。

第二章 猿伯と狸王
一
信長の仇をとる、ということは天下一統の大志を受け継ぐことに他ならなかった。その役割を果たすはずである嫡男の信忠は、本能寺の変の際に二条御所で壮絶な討ち死にを遂げている。残る信雄や信孝には、癖の強い諸将を率いるだけの力はない。
そうなると、世間の注目は信長の将領で誰が織田家中を導く立場につくか、ということになる。織田家の四巨頭といえば、柴田勝家、丹羽長秀、明智光秀、そして羽柴秀吉であった。光秀は秀吉に滅ぼされ、丹羽長秀は本能寺以降大きく評価を下げた。
北陸にいて弔い合戦に間に合わなかった柴田勝家だが、彼には北陸の上杉という強敵と対峙していたという言い訳があった。何より、秀吉を嫌う者たちの衆望が勝家に集まるのは自然な流れであった。
「殿は天下さまになりなさる」
山崎の合戦の後、太郎兵衛の頭に強烈極まりない拳骨を食らわせた後、吉成はそう言った。それからというもの、吉成は少しずつ勤めの話を太郎兵衛にするようになっていた。
「殿は天下さまになる。だが、道はまだ遠い」
「どれくらい?」
「山を越えて、さらにもうひと山越えるくらいに遠いのだ。だが殿は、いかに険しくとも山を乗り越えていかれるだろう。俺らも殿に置いていかれぬよう、懸命に走らねばならん」
吉成の言う通り、黄母衣衆も信長の生前よりも多忙となっていた。
「一緒に行きたい」
そう太郎兵衛がせがんでも、
「戦える力もない者が戦場に行くことは許さん。留守居には、九左衛門を置いていく。彼を師として己を鍛え上げるのだ」
吉成には権兵衛吉雄、次郎九郎吉隆という弟がいて、兄の側に影のようにつき従っている。兄と共に若い頃から秀吉に仕え、吉雄は槍の、吉隆は弓の名手である。特に吉雄は喧嘩も強く、太郎兵衛に印地打ちを教え込んだのも彼である。妻の露は、太郎兵衛の弟、権兵衛を産んで間もなく、病を得て世を去っていた。
犬飼九左衛門は吉成が伊勢長島の一向一揆攻めをしている最中に陣借りを申し出てきて知り合った男で、武芸にも兵法にも詳しい男であるが、太郎兵衛は彼が苦手である。無口で、いつも三白眼を光らせて吉成の傍らにじっと座っている、というのがこの男の印象だった。
「鍛えてもらうなら甚之丞か助左衛門がいい」
二人なら石合戦の時から配下として使っているから、接しやすかった。太郎兵衛は遠慮がちに願ったが、吉成が耳を貸すことはなかった。
「甚之丞たちには仕事がある」
「じゃあ九左衛門さんにはないの?」
「お前を鍛えるのが仕事だ。九左衛門がいいと言うまで、先日のような勝手は許されぬ」
吉成は怖い顔でそう言い渡した。父に厳命されては、太郎兵衛も逆らえない。九左衛門は、
「幼き日々にこのように鍛えることが許されるのは、豊かな者だけだ。甘ったれてはいけませぬ」
と釘を刺した。
「百姓どもは貢租を絞り取られ、働き盛りを兵に取られて日々懸命に生きるのみ。侍も明日にはどうなるかわからぬのが戦の世だ。こうして己を磨く時を与えられたことを神仏に感謝するのですな」
太郎兵衛は何も言い返すことができず、うなだれるのみであった。
結局、秀吉が柴田勝家を賎ヶ岳で破り、織田の家臣団の中で最も大きな力を得たことは、父が数カ月ぶりに家に帰るまで知らなかった。
天正十一(一五八三)年四月に勝家を破った秀吉は、本拠を大坂へと移した。中国攻めの足がかりとなっていた姫路は天下に号令するには西に過ぎ、かつていた近江長浜は手狭である。
「大坂は天下の礎とするにいい場所だ」
秀吉は吉成にそう語っていた。
かつて石山本願寺を攻めた際に、秀吉は大坂の持つ地の利を痛感させられた。北には淀川、東には生駒の山地、南に四天王寺あたりまで続く上町台地と、一段低くなったあたりから巨大な低湿地帯が広がり、そして西には大坂湾がある。信長ですら、ついに正面からの攻略を行わなかったほどである。
吉成は秀吉の命を受け、大坂城の普請を監督する一人として働いた。もちろん、秀吉も多忙の合間を縫って現場に顔を出し、たまたま来ていた太郎兵衛に、
「おい小三次とこの童よ、この城大きかろう!」
とはしゃいだ声をかけたこともある。
石山本願寺を土台とした新しい大坂城は、南に四天王寺や一心寺といった大伽藍があり、それらが出城のようになっている。堺や平野といった豊かな商人町も近く、各地との往来にも便がいい。まさに天下を指呼の中に入れた秀吉にふさわしい地といえた。
だが、もちろん大坂に本拠を構えただけで秀吉を天下人というわけにはいかない。名目だけと皆が理解しているとはいえ、織田家は信長の孫の三法師秀信が継いだ形となっているし、子である信雄も健在だ。
柴田勝家の後援を受けていた信孝は、勝家の滅亡の直後に自害させられた。信雄が危機感を抱いたのは当然のことである。秀吉は信雄を懐柔すると見せかけて、その実追い詰めていた。追い詰められた織田の御曹司がどこを頼るか、秀吉にはお見通しであった。
「忙しくなるぞ」
翌年までひたすら犬飼九左衛門に矢、槍、刀、組打ちの鍛錬をさせられていた太郎兵衛は、天正十二(一五八四)年の三月になって、久しぶりに父に言葉をかけられた。
「ついて来るか」
と父が言ったものだから太郎兵衛は声をあげて喜んだ。
「だが見るだけだ」
吉成は釘を刺す。素直に太郎兵衛は頷いたが、それには理由があった。鍛錬では、毎日九左衛門には気を失うまでしごかれるのだ。どのような天候であろうと、庭が泥沼になろうと雪が積もろうと、九左衛門は厳しい鍛錬を太郎兵衛に課す。
「戦は人を選ばぬ。だが死に時は選べる」
これが九左衛門の口癖であった。
「死に時を選ぶには相応の腕と時を見極める目がいる。あなたはまず腕を身につけなさい。目のつけどころはそのうち小三次さまが教えて下さる」
そんなわけで、戦う力を身につけるべくまだ七歳の太郎兵衛は鍛え抜かれているのであった。いつも半死半生まで追い込まれ、石合戦で頭に礫を食らってもべそ一つかかない太郎兵衛が何度も号泣するほどだ。
「戦場で死ぬのが嫌なら鍛錬で泣け」
九左衛門は主の子の涙を見ても一切手を抜かなかった。そのうちに太郎兵衛も、戦で命の遣り取りをする者たちは生半可ではないと理解するようになった。父も、
「腕を試そうなどと思うな。その代わり、俺がいいと言うまでは逃げてはならん。戦に行けば俺がお前の将だ。従わねば斬る」
と怖い顔で繰り返した。
これには逆らう気はなかった。戦では将と軍規が絶対であると叩きこまれている。何故命に従わなければならないか、と太郎兵衛が父に訊ねると、
「死ぬからだ。良き将の命は軍を勝たせ、悪き将の命は人を死なせる。我らは良き将についているのだから、従えばよい」
と言下に返ってきたものだ。
二
秀吉が天下の覇者と認められるためには、どうしても屈服させておかなければならない男がいた。
「三河の狸を何とかせねばならぬな」
吉成の屋敷を訪れていた秀吉は、ぼりぼりと膝を掻きながら言った。天下に手が届く立場となっても、秀吉はこっそりと吉成のもとを訪れることがあった。上等な衣も脱ぎ捨て、野良着のような格好で、褌もあらわに寝転がっているのだ。
太郎兵衛はそんな老いた小猿のような姿を見ても、侮るようなことはなかった。何より怖い父が誠を尽くして仕えている相手なのである。
「どう思うか」
そう秀吉が呟いている時、吉成が何か言うことはまずなかった。疾風の速さで無数の策が主君の頭の中を往来しているのだ。
徳川家康は信長の同盟者として遇され、その死後も別格の扱いを受けてきた。織田家の今後を話しあう清洲会議に参加しなかったのは、彼が家臣ではなく信長と同格の大名であり、家臣団の会議に出席するのが適当でなかったからである。
秀吉が家康をどのように見ていたか。
「大博打を打てる者」
と吉成には漏らしていた。賭けが始まるごとに金を張るのが博打の達者とは限らない。場の流れを見て、ここぞという時に大きく賭ける。
「三河どのが持つ賭け金はわしに比べれば随分と少ない。だがあの男が張ってくる時は、何か勝算あってのことだ。用心せねばならん」
一刻あまりも唸っていた秀吉は、
「なしくずしに家康を賭けに引きずり出し、万全の態勢を整える前に完膚なきまでに叩いてしまえばよい。光秀や勝家を倒して北陸、近江を手に入れてから、わしが動員できる兵力と財力は家康を大きく上回った。こちらの賭け金が潤沢なうちに、相手の持ち金を根こそぎ奪ってしまえればよいのだが……」
掻きすぎた膝は真っ赤になり、血が滲んでいる。だが秀吉は気にせず、吉成もじっと聞いているのみだ。
「信雄さまが三河どのと結ぶ方が好都合なのだが、それはそれで難が大きくなるのう」
膝の傷に気付いたのか、ひゃっと腰を浮かせた姿は、天下人とは思えぬ。庭から覗き見ていた太郎兵衛に剽げた顔をして見せた秀吉は、睾丸を下帯からはみ出させて寝てしまった。
吉成はそっと立ち上がって部屋から出ると、屋敷の外で自ら番を始めた。そんな父の姿を見て、この秀吉という男は大したものなのだな、と太郎兵衛は感心するのであった。
信雄は、信孝が腹を切らされて恐怖を感じているところに、父の居城があった安土を追われたものだから慌ててしまった。
庇護を求められた家康は、実に穏やかに同盟相手の子を迎えた。それによって、賭けに引きずり出されるという様子はなく、整然と押し出してきたことに、かえって秀吉が驚かされたほどだ。
しかも家康は、瞬く間に秀吉包囲陣を組み上げた。
「狸め、機をうかがっておったな」
「紀州の根来衆、雑賀衆はもともと我らと険悪です。かつて本願寺のあった場所に殿が巨大な城を築かれることで、圧力をかけられていると感じていたのでしょう」
秀吉の舌打ちに、黒田官兵衛が答えた。
「銃卒の数が厄介だ」
「それだけではございません。四国の長宗我部は、殿が四国征伐を考えていると説かれて家康と手を組むことを決めたようです」
「長宗我部元親は総見院(信長)さまと誼を通じるために光秀を仲介役とし、三好や十河を討ち果たすことを望んでいたな。わしは元親が四国を支配するのは織田家のためにならぬと、逆に長宗我部征伐を進言していたから、さぞや憎んでいることだろう」
元親からすれば、秀吉が天下を取るなど絶対に避けねばならぬ事態であるし、他方家康にとっては、元親が淡路に渡り、雑賀衆らと共に大坂をうかがう姿勢を見せるだけで十分な圧力をかけることができるのだ。
北陸の佐々成政は柴田勝家側についていたものの降伏し、越中一国を安堵されていた。だが心情的には秀吉を嫌っていたし、このまま座していてはいずれ秀吉が軍を向けて来るという恐怖と常に戦っていたから家康の誘いは好都合であった。
関東の北条は、もし家康が滅ぼされれば次は自分だという恐れを持っていたから、これも誘いに乗った。見事な手際である。両者の対決は、先手を取らせると見せかけて秀吉の意表を衝いた家康の優勢から始まった、といってよい。
「小三次には紀伊守を任せる」
「適任と存じます」
ということで、吉成は池田恒興との連絡に忙殺されることになった。
信長の乳兄弟である恒興はかつて大坂を任されていたが、秀吉に請われて城を譲り渡して美濃にいる。
もちろん、彼にも家康からの誘いが行っている。同僚であった柴田勝家が死に、丹羽長秀が逼塞しているのは、秀吉が主家を簒奪し、信長の遺したものを乗っ取ろうとしているのだと家康側の使者は説いた。
恒興の従兄は滝川一益であり、一益は秀吉をよく思っていない。彼からもしきりに家康につくよう、使者が来ていることを吉成は掴んでいた。
吉成の任務は、それを打ち消して恒興を秀吉の側につけておくことである。
「ただひたすらに、誠で押せ」
秀吉は吉成にそう命じていた。もとより、吉成もそのつもりである。他家との交渉は、誠だけで通るものではない。時に偽り、恫喝し、かと思えば下手に出ることも必要である。だが秀吉は吉成にそのようなことをさせなかった。
「公明正大の先に道がある。もちろん、他にも道があることは知っている。だが殿がその道を行けと命じるなら、行く」
太郎兵衛を伴った吉成は、山伏姿である。当時の山伏はただ諸国を放浪して修行したり勧進、祈祷をするだけでなく、諜報にあたる場合もあった。街道ではない山間の道を知っているからであって、街道が封鎖されても往来が可能であった。
美濃の稲葉山城は、吉成にとって懐かしい場所である。
「このあたりで俺は生まれた」
太郎兵衛は物心の付いた頃には長浜にいたから、美濃を知らない。長浜から見える東の山なみを越えれば美濃だと知ってはいたが、身近な場所ではなかった。
「いいところだ。山も川も美しくてな」
昔語りなど珍しい、と太郎兵衛は父を見上げた。
「しがない野伏せりくずれだった俺が、殿と出会った場所だ。もっとも、初めてあの容貌を見た時は、小鼠が衣を来て里に出てきたと大笑いしたものだがな」
森家は尾張大江氏の流れを汲むと自称しているが、本人もその真贋など気にしていない。猿面の若武者として名を揚げつつあった秀吉と出会い、その人柄と能力に全てを賭けようと決意した。脛も丸出しで秀吉と共に駆け回った山谷が広がる、美濃の天地である。恒興の政は行きとどいているようで、城下は賑わっていた。だが、東西の緊迫した情勢を映しているのか、人々の様子はどこか浮足立っている。
山伏も一人で歩いていると怪しまれるが、幼子を連れているだけで随分と人の見る目は優しくなった。何度か誰何されたものの、城門まですんなりとたどり着いた。
「門付けはいらんぞ」
と怖い顔をする番兵に名乗ると、番兵は表情を強張らせて門内へと消えた。
「門付けに間違われるくらいなら、上出来だ」
「中へどうぞ」
番兵の代わりに出てきた恒興の家老、片桐半右衛門が丁重に出迎えた。太郎兵衛は客間に留め置かれ、吉成は一人山伏姿もそのままに恒興の前に出た。特に相手をしてくれる者もおらず、太郎兵衛は退屈して座り、やがて畳の上に寝そべった。
こうした怠惰な姿も、実に久しぶりのことである。犬飼九左衛門は昼夜問わず太郎兵衛の傍におり、鍛錬だけでなく普段の挙措にまで目を光らせていた。細かく叱りつける、というのでもなかったのだが、緊張を常に強いられて心の休まる暇もない。
たまにはこうやって連れ出してもらえたらいいな、と太郎兵衛は大の字を楽しむ。首を横に向けて畳に耳をつけると、部屋を一つ隔てて向こうの広間の声が微かながら聞こえてきた。
堂々とした声は、はじめ恒興のものかと太郎兵衛は思っていた。だが、その声は紀伊守さまと恒興に呼びかけている。家で聞く重く暗い父の声とあまりに違うことが面白く思えて、太郎兵衛は畳に耳をつけながら一心に聴き始めた。
「筑前にもはや理はない」
苦々しげに恒興は言っていた。
「明智を攻め滅ぼしたのは正しい。右府さまに刃を向けた大罪がある。その仇を討つ先兵になることは、我が誉れでもあった。筑前なら右府さまの無念を晴らし、天下布武の想いを三法師と共に成し遂げてくれると信じていた」
それがどうだ、と扇子で脇息を叩く音がする。
「権六を攻め滅ぼした上に、三七に腹を切らせたではないか。それは誰の、何に対する咎か」
溜めていた怒りを爆発させるような恒興の口調である。
「筑前さまの想いに一寸の狂いもございません」
吉成は静かに、しかしよく通る声で言い返した。
「織田家を盛り立て、天下に安寧をもたらすという清洲での議に従って、殿は動いております」
「では何故、主筋の若者に腹を切らせたのか。三七は将として至らぬ点は多々あったろうが、それは我らが支えていけばいいだけの話だ。権六は三七を盛り立てていただけで、誰かに反逆を企てていたわけではない。あれほど激しく攻め立てて殺すのは、やり過ぎだったのではないか。筑前は苦楽を共にした僚友を皆殺しにするつもりか!」
太郎兵衛が思わず畳から耳を離すほどの声量である。
戦国の武人は喧騒激しい戦場で四方に命を下すため、声が大きい。恒興も例外ではなかった。太郎兵衛のいる部屋の梁が微かに震えている。
「主筋とは」
空気の震えが収まるのを待つかのように間を置いて、吉成が話し始めた。
「どなたを指すのでしょうか。清洲において、筑前さま、紀伊守さまをはじめ、将領の皆さまは三法師さまを右府さまの後嗣として定められました。これには、権六さまも同意されたはず」
そこで一旦言葉を切る。激しい反論がないことを確かめたのか、吉成は言葉を継いだ。
「諸将によって後嗣と定められた三法師さまに軍を向けることは、即ち織田家への反逆であります」
恒興が苛立たしげに扇を開き、そして閉じる音がした。
「三法師さまの後見として差配することは、筑前さまの務めであります。殿は三七さまが清洲の議を軽んじていることに目を瞑り、家老たちに諮ってことを穏便に済ませようと心を砕かれました。ですが、家老たちに罪を着せて殺し、出奔するとは三七さま不覚悟の極みとしか言いようがありません」
「だが三河は筑前の横暴を天下に喧伝し、四方に味方を募っているぞ。筑前の専横を憎む者たちが誘いに応じつつある」
それこそ不義の兵である、と吉成は初めて声を大きくした。
「右府さま亡き後、筑前さまが恐れられたのは、不義が横行して戦乱が激しさを増すことでした。そのために、三法師さまの下に同心して四方を安らげ、権六さまが望む通りに長浜も南近江もお贈りし、お市の方さまが障りなく嫁げるよう心を砕かれました。これもひとえに、諸将が順逆を違えないための気配りではありませんか」
確かに、信長麾下の諸将が最終的に三法師を戴くことに同意したのは間違いない。だが幼い三法師に頭を下げることは、その後見である秀吉を拝礼するのと変わりなく、反発を強める者がいても不思議ではなかった。
恒興はつい、諭すような口調になっていた。
「筑前は将としての力量、人にすぐれている。だが、三法師の後見というだけで天下を動かそうというのは、あまりに乱暴だ。三介(信雄)が家康と手を組み、西に兵を向けたら、どのような口実をつけてこれを迎え撃つのだ」
「大義あるのみです」
吉成は静かに答えた。
「総見院さまの跡を継ぐのは誰なのか。議によって決した三法師さまなのか、ほしいままに国を捨て、東国に助けを求める三介さまなのか、紀伊守さまの正しき断を願います」
しばらく、恒興は黙っていた。
「わしは、総見院さまと深い縁を持ち、栄えるも滅ぶもその力一つと信じてついてきた。誰が刃向かおうと背こうと、常に総見院さまの側に立っていた。だから此度のことも、その心のままに働きたい」
長い沈黙の後、小さな声で恒興は言った。
「三河さまを最後まで盟友とし、禄を与える臣下としなかった。それは家中に入れるべき者にあらず、とお考えだったからだ。決して低く見ているわけではない。むしろ高く評しているからこそ、家中に入れてはならぬお人だった」
その家康のもとに、信雄は走った。
「三介は、右府さまが望まなかったことをなそうとしている。となれば、わしはそれを止めるのみだ」
恒興は立ち上がる。
「筑前には、与力いたすゆえ心配はいらぬと伝えよ」
吉成はその言葉を聞くなり、さっと平伏して礼を述べる。
「三河は戦うとなるとこれ以上ない難敵だぞ。かつて己を従えていた今川を滅ぼし、甲斐武田の圧力を退け続け、ついには勝った男だ」
「承ってございます」
平静を装っていたが、父の声に安堵の気配が漂っていることに太郎兵衛は気付いていた。話が雑談に移るのに合わせて、太郎兵衛はそっと畳から耳を離した。
三
無事に務めを果たした吉成であったが、秀吉のもとには戻らなかった。そのまま恒興の与力として働くように、という命が下っていたからだ。黄母衣衆は単騎で使者の任に当たることもあれば、数百の郎党を率いて秀吉の左右を守る務めも果たす。
「殿は我らにも行けと命じられました」
吉成の弟、権兵衛吉雄、次郎九郎吉隆に率いられた手勢も到着した。
「身命を堵して紀伊守さまをお守りせよと」
律義者として通る森兄弟の口上を聞き、恒興も表情を和らげた。
「質も誓紙もいらぬから、小三次たちを陣に置いてくれ、とは筑前も随分とお人よしになったものだ」
恒興は秀吉からの書状を見せた。
「殿は紀伊守さまに裏をかかれるなら、それで本望だと仰っていました」
秀吉につく、と言い渡した恒興に対する反応は様々であった。安堵した者もいれば、不安や不満を表す者もいた。だが恒興は吉成の説いた大義を前面に押し出し、三刻以上かけて家臣たちを説得しきった。
日は暮れ、太郎兵衛は昼寝から起こされてここにいる。
「それにしても筑前の人たらしめ」
恒興は扇をぱちりぱちりと開いては閉じた。
「この癖は総見院さまにもあった。考え事をしているとこうするのだ。声をかける者をその場で斬り捨てるような凄味を放ちつつ、一人広間で四方への策を練っていたものだ。長く近くにいたわしは、いつしかその癖を真似るようになったものだ」
だが、上っ面だけだ、と苦笑する。
「わしは仕草を真似るのではなく、その果断さを真似るべきであった。そうすれば、天下が以前にも増して騒がしくなることもなかっただろうに」
「人の資質は真似ることはできません。己が作り上げていくのみです」
「これは異なことを言うものだ。筑前の傍にいながらその言い草は得心がいかん。真似て強くなったではないか」
恒興は杯を傾けながら、首を振る。
「筑前は柴田権六の豪も総見院さまの果断も、真似て身につけているぞ」
「それは……」
「まあ、真似をして使いこなすだけの力がなければ、わしの扇のようになってしまう。おい太郎兵衛、人を見る時は筑前のようでなければならんぞ」
笑みを含みながら、恒興は言った。
天正十二年三月十三日、恒興は吉成を東美濃の森長可のもとに走らせた。
恒興の女婿であり、長く信長に仕えてきた彼にも、秀吉は黄母衣衆の尾藤知宣を派していた。長可は十五の年から最前線で戦い続け「鬼武蔵」と異名をとる豪の者である。
しかも東美濃を領し、信雄と家康の連絡を断つために必ず味方につけておかねばならなかった。尾藤は恒興の動向次第だと考え、吉成の説得の行方を固唾をのんで見守っていたが、説得が成ったと吉成から告げられて安堵していた。
長可は恒興の去就を見て、はっきりと秀吉に味方すると言明し、そのように準備を進めていた。これによって、美濃は秀吉方となったのである。
「おい、小三次。子連れで来たのかよ」
知宣は小柄な馬にまたがっている太郎兵衛の姿を見て驚愕した。
「何事も鍛錬だ」
「鍛錬ってお前……」
呆れ果てた知宣は我に返ると、家康が既に清洲城に入っていることを告げた。
「早いな……」
秀吉の言っていた通り、最初からこの戦が行われることを予想していたかのような動きである。尾張の中央である清洲に本陣を置けば、伊勢、伊賀を領国とする信雄との連絡が断たれる心配がなくなる。
「恐ろしいのは、東海と畿内で一斉に攻勢に出られることだ。武蔵守さまは犬山城を攻め取られるおつもりだ」
「それはまずい」
恒興も同じことを考え、犬山城へと軍を率いて向かっている。二人の黄母衣衆から報告を受けた長可は、すぐさま小牧山城を攻め取ることを提案した。
「小牧山と犬山を結ぶ線を押さえられれば、家康の背後をとることができる」
「ですが、三河守は恐らく何らかの手を打っているはず」
「だが動かねば美濃は孤立する。何もせず恥をさらすわけにはいかない」
森長可は二十七にして歴戦の勇者である。その断に迷いはなかった。
「この戦、よほど気合いを入れてかからんと勝てぬ。三河の鼻を明かすのは相当なことだぞ」
長可はすぐさま出陣を命じ、知宣も軍監とし督戦の任につくことになっていた。吉成と太郎兵衛は恒興が陣を出している犬山に向かおうとしたが、知宣は、
「太郎兵衛は大坂に帰しておけよ。激しい戦になるぞ」
と諌めた。
「激しい戦だから見せるのだ」
「人の子育てに口を出す気はないが、生きていればこそ子も育つというものだ」
知宣は子を早くに病で亡くしている。
「生死は神仏のみがご存知だ」
と吉成は取り合わず、太郎兵衛は大坂に帰れと言われなくてほっとしていた。
四
長可の決断も軍の動きも、決して遅いものではない。だが家康はそのさらに上を行く。金山を出た長可の軍がどこを目指すかを知るや、すぐさま小牧山城の兵を増強したため、長可は小牧山城手前の羽黒に布陣するほかなかった。
恒興は両軍の動きを見て顔をしかめた。
「三河は天から我らの動きを見ているのか」
と勘繰りたくなるほどの用意の良さである。
「伊賀衆を押さえているのは大きいのでしょう」
「こちらの動きを読まれているとしたら」
十七日の早朝になって気付いた恒興は、扇をぱちりと鳴らして閉じた。
「勝三は危ういぞ」
青ざめた恒興はすぐさま全軍を動かして長可の後詰めに回ろうと試みた。だが、物見の兵が急を告げる。
「徳川勢は羽黒に至り、武蔵守さまの側面を衝いています」
「遅かったか!」
恒興は犬山から軍を動かそうとしたが、諸将が止めた。
「ここで勝三を失って戦に勝てるとは思わぬ。それに婿も助けぬ舅という評判は立てられたくないのでな」
恒興は小牧山から家康を引っ張り出すことができれば、逆に勝機があると考えていた。だが、立て続けに戻ってきた物見の報告からは、家康が行う盤石の指揮しか聞こえてこない。
「勝三は無事か」
しきりに気にしていた恒興だが、何とか脱出して金山城に逃れたと知って胸を撫で下ろした。
「これは筑前が出て来るほかないだろうな」
吉成は恒興の言葉に頷いた。既に秀吉は二万の軍を編制し、東へ向かう準備を進めていた。家康が恒興の想像をはるかに上回る速さで尾張に兵を集中させている以上、五分に戦えるのは秀吉本人しかいない。
「また天下分け目か。筑前も忙しくて気の毒だ」
冗談めかすが、恒興の目は笑っていない。
「ここで敗れると、前途は厳しくなるぞ」
そして吉成に対し、
「これ以上の与力は必要ない。わしと勝三の戦いぶりを見て、もはや監視など必要ないことがわかったであろう。筑前が来れば、わしと勝三で先鋒に立てるよう願い出るつもりだ。おそらく勝三もそう考えているであろう」
と告げる。吉成は、太郎兵衛を伴って恒興の本陣から退出した。その足で、金山城へと吉成たちは向かったのである。
家康は小牧山城の周囲に土塁を築き、濠を巡らせて要害とするため工事を急いでいるという。だがそのおかげで、長可は命拾いをしていた。
金山城での長可はむしろ不自然なほどに明るかった。吉成たちを歓迎し、酒宴まで開いて見せたのである。敗戦で落ち込みがちな城内の雰囲気を変えようとしているようであった。
「三河はさすがの采配であったよ」
長可が小牧山を望む羽黒に陣を敷いたと見るや、家康は酒井忠次と榊原康政に兵を授け、その背後を襲わせた。
「気をつけてはいたのだが、三河方の動きが一切見えなかったのだ」
その隣では、軍監の尾藤知宣が悄然とうなだれている。
「俺がもう少し気をつけていれば、このような苦労を武蔵守さまにさせることもなかったのに。軍監として派されている意味がない」
と嘆く。
「なに、勝敗は兵家の常だ。総大将の俺がしくじったというだけの話だ」
長可は豪快に笑い飛ばした。
「三河守は小牧山を拠点に筑前さまを待ち受けるつもりだ。そうなれば先鋒はかなりきつい務めとなる。それを俺がやる」
恒興の予想通り、長可もそう考えていた。
「同じ恥は二度とかかぬ。二度目は死ぬ時よ」
さらりとそう言う。太郎兵衛は何故か、その言葉を聞いてぞくりとした。幼いとはいえ、人の死様はいくらでも目にする。戦場の真っただ中に立ってはいないが、路傍には戦で倒れ、飢えに力尽きた無残な死体がいくらでも転がっている世の中だ。
だが、太郎兵衛にはあまりにも遠い話である。自分も父も、言葉を交わしている誰かであっても、次の瞬間命を飛ばしているなど想像もつかない。
まして、これほどさらりと死を口にする人間を前にしたことがなかったので、驚いたのである。
「武人とはあんなものだ」
吉成は呆然としている息子に、そう言った。
二人は金山城を辞して、大坂へ帰った。街道筋は新たな戦を前に隊商の列が行きかっている。秀吉が主力を率いて東に向かうとの報は得ていたので、吉成は途中で合流するつもりでいたのだが、結局大坂に戻って復命することとなった。
「小三次、息子の初陣には早いだろやい」
忙しいにもかかわらず、秀吉は吉成をわざわざ書院に呼んで様子を聞いた。
「馬子です」
「馬子にも早いわ」
いつも吉成が感心するのは、数多いる家臣の家族にどのような者がいるかすら、秀吉は記憶していることであった。これも信長が秘かに持っていた技能である。秀吉は妻のねねと夫婦喧嘩をした際に、主君が仲立ちをしてくれたことにいたく感激していた。その時の様子を、吉成も近くで見ている。
秀吉が吉成たち側近の家庭にまでやたらと興味を持つようになったのは、その直後からである。それにしても、多忙を極めているのによくそんな暇があるな、と驚くほどに、誰にどんな子が生まれたなどということまでよく知っていた。
「おい太郎兵衛、石合戦では中々の働きぶりらしいな」
といきなり言ったので、吉成は驚愕した。
「そうなのか?」
息子に思わず訊ねていたほどである。太郎兵衛の方はというと、驚いて瞬きを繰り返すばかりであった。
「戦も政も見た目ではないぞ」
秀吉はそう言うと、ききき、と笑った。
「お前も幼子という見た目で敵陣に近付き、黒田の吉兵衛を討ち取ったそうだな。石合戦でのこととはいえ、大したものだぞ」
吉成は拳を振り上げかけたが、秀吉は手を振って止めさせた。
「息子の武勲を叱る道理はあるまい。しかも、吉兵衛についてきた後藤のせがれの馬に便乗して山崎にまで出張っていたそうではないか。その時いくつだ」
問われた太郎兵衛は手のひらを開いて突き出す。
「勇ましや、勇ましや」
秀吉は立ち上がると太郎兵衛に近づき、その手を掴んで大きく振った。太郎兵衛はその手の感触にはっとなる。槍を握ることで出来るたこが、手のあちこちにできていた。小さいが分厚く硬い手は、父にそっくりである。
「小三次がよしと言えば、すぐにでも使ってやる。なあ、お前の息子は何ができる」
「ですから、馬子です」
「馬子として働けるなら、父の傍にいて馬の世話をしているがよい」
再びききき、と笑った秀吉はまさに猿の素早さで立ち上がる。
「次の戦は尾張じゃ。懐かしいのう、小三次」
吉成が返事をしかけた時には、もう秀吉の姿はなかった。
五
秀吉の動きは、吉成が予想していたよりもやや遅かった。
犬山城に入ったのが三月二十七日。そして、森長可が徳川方の奇襲に遭って壊滅した羽黒からさらに南、小牧山に近い楽田という場所に本陣を張ったのが、四月五日であった。
吉成と太郎兵衛は秀吉の本陣に従っている。黄母衣衆は四方の武将と連絡を密にするため、蜂のごとく忙しく陣を出入りしていた。
池田恒興との連絡を任されている吉成と森の手勢は、命を受けることなく本陣にいたが、ただじっとしていたわけではない。頻繁に秀吉に呼び出されては何やら策を聞かされていた。その間、太郎兵衛は吉成の馬の世話を続けている。犬飼九左衛門には馬の扱いも当然やらされているので、馬子になれと言われても驚きはしなかった。
「殿は中入りを行うそうだ」
吉成は出立の準備を太郎兵衛にさせながら言った。
「中入り?」
「三河国の中へ秘かに軍勢を入れるのだ」
家康が森長可の攻勢を蹴散らして小牧山城に持久戦の構えを敷いたのは、当然理由がある。大坂に対する包囲陣が効果を発揮するのを待つためである。
四国の長宗我部、北陸の佐々成政、紀州の根来、雑賀、伊賀の織田信雄は、それぞれでは秀吉に勝つことはかなわない。
「三河守どのも、独力で勝てるとは思っていない」
「勝てないのに戦に出るんだ」
馬の世話をする手を止めて、太郎兵衛は顔を上げた。主の気配に、馬は嬉しげに鼻を鳴らしている。
「あの方のしたたかさはそこにある」
吉成は愛馬の鼻を撫でてやりながら、険しい表情となった。
「独力どころか、実は関東の全力を挙げたとしても殿には勝てぬし、まして大坂を落とすことなどできぬ。殿は全ての力を注げば小牧山の守りを破るし、そのまま岡崎の城まで攻めいることも無理ではない」
「じゃあそうすればいいのに」
「それが中入りだ」
秀吉は家康が持久戦の構えをとれば急戦を仕掛ける、という相手の裏をかいたものになるはずであった。羽黒の戦いで敗戦を喫した森長可はもちろん第一陣の先鋒を願い出た。
だがこれを退け、自分を先鋒とするように秀吉を動かしたのは、池田恒興であった。
「勝三は気が逸り過ぎている。家康の本拠となればどのような備えがあるかわからん。ここはわしに任せて欲しい」
と求められれば秀吉も異論はない。ただ、一つだけ条件をつけた。
「万事、これある小三次と相談して兵を進めていただきたい」
そう指示したのである。恒興はもちろん、嫌な顔をした。
「疑っているのか」
「とんでもない」
床几から跳びあがらんばかりの勢いで秀吉は手を振った。このような動きをすると、随分と道化めいて見える。そこが人に愛され、また苛立たせた部分ではある。恒興は戦場においてこのように剽げた気配を出せる秀吉を、大したものだと認めていた。
「紀伊守どの、この戦は天下の今後を占う大切な一挙となり申す。戦乱が長く続くか、天下泰平が成るか、全てはこの中入りにかかっておるのです」
顔を真っ赤にして訴える。
「小三次はわが黄母衣衆の中でも特に古くからわしにつき従い、その心はわが心を映すが如くであります。勝三どのにも、同じく黄母衣の尾藤知宣をつけて万全を期しております。どうかここは、わしの言葉に従っていただきたい」
膝をついて懇願するがごとくされては、恒興は逆らえない。
「……わかった。何も小三次を嫌って言っているわけではない。この挙がならねば、天下は三河と筑前で分かれ、将来に大きな禍根を残すであろう。わしには右府さまや筑前のように、天下を見据えて戦うことはできぬ。言葉に従おう」
感動を面にあらわして、恒興は自陣へと戻って行った。
立ち上がってその背中を見送った秀吉の表情は、既に平静なものへと戻っている。恒興と従者たちが陣から出たと報告を受けると、そこでようやく床几に腰を下ろした。
「随分と気負っておられる……」
秀吉はため息をつく。
「触れれば破れそうなほどに張り詰めているな」
主君が独言する時は、黙っている。吉成はそのように心得ていた。付き合いはもう三十年近くになるが、秀吉の口が勝手に動いている時は、策が猛烈な勢いで生みだされ、頭の中を駆け巡っている時である。
斥候がひっきりなしに本陣に駆け込み、情勢を告げていく。
羽黒で森長可の部隊を壊滅させた家康は再び小牧山の城塞の中へと引き返し、楽田に布陣する秀吉の大軍を見ても微動だにしない。
「家康の旗本どもはどうしている」
秀吉が斥候に訊くと、やはり動きはないとの答えである。
「このまま終わるとは思ってはおるまい。小三次、お前は紀伊守さまの動きに用心し、事あれば久太郎とよくよく相談するのだぞ」
そう言い含めた。久太郎は秀吉の薦めで信長の小姓となり、何事もそつなくこなすことから「名人久太郎」と異名をとった堀秀政のことである。この時齢三十一にして、その将才は天下に轟いていた。信長に仕えていた際には一向一揆などと激戦を繰り広げ、その後は秀吉につき、山崎、賎ヶ岳どちらの戦場でも大きな功を立てている。
家康の本拠、岡崎城への奇襲は、四段構えで行われることになった。第一陣は池田恒興をはじめとする総勢六千。第二陣は森長可を筆頭に三千、第三陣は堀秀政ら三千、そして第四陣に中入りの総大将、羽柴秀次、田中吉政ら六千。計一万八千の大軍を秘かに東進させて小牧山を迂回し、三河へと至るつもりである。
四月七日払暁、秀吉は楽田から銃隊を出してさかんに小牧山へと撃ち掛けた。猛烈な銃火と煙を見て、家康方も撃ち返してくる。その喧騒に紛れて北へと向かった中入り部隊は、まずは無事に春日井へとたどりついた。
だが、家康は秀次軍の中に間諜を送りこみ、その動きを掴んでいた。小幡城は小牧山から見て南東にあり、岡崎へ至る街道筋を掌握できる位置にある。家康がひそかに小幡城に入ったことを、秀吉も恒興ら中入り部隊も知らなかった。本軍は小牧山から動いていないと考えて攻勢を見せつつ、恒興たちは岩崎城の攻略に取り掛かっていたのである
岩崎城は小牧山の西南にあり、岡崎への途上にある。無視して進むのが常道であったが、何故か恒興ら第一陣は足を止め、猛然と城に攻めかかった。
六
戦闘は既に始まっていた。岩崎城を守るのは、丹羽氏重である。まだ十六歳の彼は、小牧山で家康に従っている兄の氏次の留守を守っていた。城に残る兵はわずか二百で、恒興ら第一陣六千とは敵するべくもない。
だが彼には、戦わねばならない理由があった。
氏重の父、氏勝はかつて、信長に仕えていたが、謀反の疑いをかけられて追放された。家は没落して故地である尾張の丹羽荘に逼塞していたところを家康に引き立てられたのである。
「三河守さまのために功を立てるべし」
というのが父子の合言葉となっていた。だが、六千の兵を相手に無謀な戦いに出ることに、家臣たちは反対した。
「三河守さまの本陣で氏次さまが存分に戦われ、氏重さまはこの城を守りきれば十分ではありませんか」
そう言って止める。彼らは氏重が血気に逸っているように見えたのである。だが、氏重は兄からの使いで恒興たちが何を狙って南下しているのか知っていた。そして、兄たちが秀吉方の奇襲部隊を追っていることを、掴んでいたのだ。
「ここで一戦を挑み、奴らの目をこちらに引きつければ兄上の功もさらに大きくなる」
初めて心中を明らかにすると、兵たちは勇躍した。二百の兵しかいないので、銃の数も二十ほどしかない。だが彼らは果敢に恒興の陣営に近づいて、撃ちまくったのである。
小さな城に少ない兵を相手にする気は、恒興の方にはなかった。だが、一弾が恒興の愛馬に当たり、彼は落馬してしまったのである。
「小童め、命を無駄にするか!」
恒興は城にいる丹羽氏重をもちろん知っている。その父とは信長の臣下として轡を並べて戦ったこともある。それだけに、怒りは大きかった。
当然、吉成は岩崎城を落とすという恒興を強く諌めた。
「我らが落とさねばならないのはこの城ではありません。岡崎城です」
「わかっている。だが馬を撃たれて落ちたままでは幸先が悪いではないか」
そう恒興は言い張った。
「無駄に一日を過ごしては、家康に気付かれます」
吉成も、よもやその家康が小幡城に入っているとは思っていない。だが、羽黒に布陣した森長可に襲いかかった手腕を見れば、周囲の気配を油断なく探っているに違いないとふんでいた。
だが、どれほど諌めても、
「時間はかけぬ」
の一点張りで押し通されてしまった。秀吉の意向を受けている軍監扱いだといっても、恒興はあくまでも秀吉の同盟者である。まして、織田家での序列は長らく恒興の方が上だった。吉成としても、あまりに強くは言えない。それでも、
「この城にこだわるのであれば、先陣を勝三さまか久太郎さまに譲るべきです」
と迫った。
「小三次はわしを侮るのか!」
そう一喝されればそれ以上は吉成も引き下がるしかない。ただ、急ぎ秀吉と堀秀政に使いを送るしかなかった。
太郎兵衛は吉成の馬子という名目で、この陣にも従っている。吉成は馬の手入れをする息子の姿をじっと見つめていた。何か叱られるのでは、と太郎兵衛は内心ひやひやしていたが、父は何も言わずただ背後に立っている。
戦闘は始まっていた。
激しい銃声と喊声が陣の外から聞こえているが、本陣は静まり返って音もない。恒興は陣頭に近いところまで出て、城攻めの下知を行っている。
「俺も死なねばならんか……」
父が物騒なことを言ったので太郎兵衛は驚いて振り返った。
「負けているのですか」
「まだ勝敗などついておらん」
苦々しげな表情である。
「叔父上、どうなんですか」
と太郎兵衛が吉雄に訊くと、
「勝とうが負けようが、死のうが生きようが存分に戦うだけだ」
と重い声で答えるのみであった。
九日に入って攻城戦が開始された。すぐさま落ちると思われた岩崎城はなかなか落ちない。氏重は二百の兵を一団とし、銃兵で一斉に撃ち放っては突撃し、すぐさま城の中へと引き返すという戦法を繰り返した。
攻める側は、相手は小勢であることから意気が揚がらない。
「勝ちが見え過ぎても、人は戦わぬ」
太郎兵衛は何とも答えようがなく、馬の手入れを続けている。
「お前は大坂に戻れ」
ふいにそう命じた。
「嫌です」
太郎兵衛は手を止めず、即座に拒んだ。
「馬丁としてつき従った以上、主と馬から離れないのが務めです」
「心憎いことを言う」
吉成もそれ以上帰れとは言わなかった。
「これから真の戦場を見ることになる。心しておけよ」
その言葉は、間もなく真実となった。
七
岩崎城は間もなく落城し、丹羽氏重は城を枕に討ち死にした。だが、恒興は岩崎城を落とすのに半日をかけ、最後は森長可の助勢を受けたほどに手間取った。第三陣の堀秀政と第四陣の羽柴秀次は恒興を待つために、守山で戦況を見守っていた。その注意が岩崎城に向いていたところに、家康方が襲いかかったのである。
秀次軍に襲いかかったのは、榊原康政、丹羽氏次ら四千五百。中でも氏次は、弟の見事な最期を耳にして戦意に燃えていた。
すっかり戦見物の気分となっていた秀次軍の混乱はひどかった。瞬く間に本陣を切り崩され、秀次は近習たちの多くが討ち死にする中をようやく単騎で脱出できたのみである。
城を落としてほっとしていた恒興は、背後から家康軍が襲いかかったと聞いてようやく己の過ちに気付いた。
「久太郎はどうしている」
恒興は自軍をまとめて北へと反転しつつ、森長可と共に秀次軍を救おうと考えた。第三陣の堀秀政は戦上手であるが、不意を衝かれては危うい。だが、伝令の兵は秀政の見事な指揮ぶりを伝えてきた。
「三河の奇襲を退けただと」
さすがの名人ぶりを発揮した秀政は、秀次の残兵を収容すると、勝ちに乗じて押し寄せてきた三河方を引き付け、一斉に発砲して怯ませると槍衾を敷いてその鋭鋒を挫いた。
「これで一息つけるか」
と恒興は胸を撫で下ろしたが、家康はその次の手を打っていた。
榊原勢が敗走を始めるや、小幡城を出て長湫(長久手)へと出陣した。四千ほどの兵を率いたのみであったが、凄まじい勢いで恒興と長可の軍を両断した。堀秀政は奇襲部隊を破ったところで家康自身が出てきたと見るや、楽田へと引き返す。
もはや戦機は去ったと判断したのである。
だが、恒興と長可は退路を家康に押さえられた形となって、陣を敷かざるを得なくなった。彼らが布陣した長久手は、長湫と表された。湫は湿地を意味し、軍を動かすには不利な地である。
「東海一の弓取りは大したものだな」
恒興も歴戦の将だけに、その陣構えの見事さには感嘆するほかなかった。
野戦においては、どこに陣取るかが何よりも重要である。相手の動きを封じ、攻守に優位となるには地勢の見極めと敵の機先を制することが何より肝要だ。
「我らの虚をついて後詰めをかく乱し、奇襲が完全なものとならなくても二の手、三の手を用意している。しかも陣を構えれば鉄壁の構えだ。あれを見ろ。右府さまが長篠で武田と相対した際を思い出させるではないか」
瞬く間に組み上がった陣は強固な柵をめぐらし、その間からは無数の銃口がのぞいている。こちらから攻め寄せれば無数の死者が出ることは明らかであった。しかも、「湫」に陣を敷いた恒興と長可は、迅速に軍を動かせない。
だが恒興も長可も、ただ先手を取られているだけではなかった。恒興の子の池田元助を右翼、森長可を左翼に置き、恒興は後詰めとして徳川方に対する。そして恒興は、吉成に秀吉への使いを依頼した。
「三河守が城を出ている今こそが好機だと伝えてくれ」
家康がおり、しかも要塞と化した小牧山城を落とすのは至難の業であった。だが、今家康が率いているのはわずか数千。楽田には二万の秀吉直属の精鋭が揃っている。
「こちらに自ら出てきたということは、筑前とは直に遣り合う気はないということだ」
恒興はそう見ていた。
「我らの奇襲はもはや失敗した。だが治兵衛の軍を壊滅させてさらに我らの前に鉄壁の陣を敷くということは、天下に何かを知らしめようとしているのだ」
吉成は恒興の言葉が理解できず、首を傾げた。
「何か、と言いますと」
「触れるな、と言っておるのだ」
「触れるな?」
「我らに触れると痛い目にあう、と示すつもりだ。筑前はそれを許してはならぬし、許せば将来に禍根を残す。その根を絶つのは今しかない。我ら九千の兵の命が生きる術は、そこしかあるまい」
「殿に後詰めに入るようお願いして参ればよろしいのですね」
「違う」
恒興は頭を振った。
「三河方が山から下りて攻めかかってきた機を捉え、全力で攻めるように言うのだ。後詰めではなく、側面から衝いて三河の首を挙げるのだ」
「しかし……」
もし楽田から南下して長湫に急行すれば、小牧山から三河方の主力がその背後を襲う恐れがあった。そうなっては、前後から挟撃されて大損害を蒙る。
「そうならぬように我らが三河の裾を捉えて放さぬわ。ここで奴の首を挙げておけば、十万の兵の価値がある」
吉成は頷くほかない。
「では、弟たちを置いていきます」
「心強いな。粗末にはせぬぞ」
恒興は、さあ行け、と吉成たちを送り出した。
太郎兵衛に馬をひかせて後鞍に乗せると、吉成は馬を走らせた。長湫の湿地帯を抜けて北上しようとしても、周囲は徳川方の部隊が布陣して道が容易に見つからない。
すると不意に、数人の兵が茂みから出てきた。
「どこのお方か」
言葉に三河訛がある。吉成は躊躇いなく馬腹を蹴ると、兵の間を走り抜けようとした。吉成は巧みに手綱をさばくが、長湫の田は湿って馬の足がとられる。
「太郎兵衛、走れ」
この日の吉成は槍を持っていなかった。後ろから追いすがる兵たちに向かって抜刀し、太郎兵衛にそう命じる。
「い、いやだ!」
「もはや馬もない。馬丁のお前に仕事はない。あるとすれば、俺に代わって殿に紀伊守さまの言葉を伝えることだ」
太郎兵衛は男たちの中に躍り込む父の姿に背を向けようとしてどうしてもできない。逃げ出すかわりに、太郎兵衛は礫を握っていた。石合戦のように、手にあった石を見つける暇はない。泥をかぶった石は小さな手に余る。
だが腕をしならせて太郎兵衛は礫を放った。
父に槍をつけようとしていた足軽の頭に当たると、首が歪んで田の中に倒れ伏した。太郎兵衛は続けざまに礫を投げると、数人の兵がたて続けに倒れた。だが、一人が太郎兵衛に気付き、茂みに向かって何かを喚く。
耳朶を貫く轟音が響き、鉄棒で殴られた衝撃が全身に走る。泥の中に顔を突っ込んだことに気付い時には何者かに体を押さえつけられていた。必死で顔を上げると、父がやはり組み伏せられている。首をかかれそうになったところで、何者かが制止していた。
「殺すな!」
と叫びつつ、今にも吉成を刺し殺そうとしていた足軽の槍を叩き落とす。
「へ、平八郎さまだ」
足軽たちは怖れをなして吉成から離れる。
黒い肥馬に乗っている大柄な男は漆黒の甲冑を身につけ、穂先が三尺近くありそうな大槍を提げている。鹿角の兜から覗く目は大きく炯々と光り、泥まみれの吉成と太郎兵衛を見下ろしていた。
「筑前さまの黄母衣衆とお見受けする」
そして男は馬を下り、丁寧な口調で本多平八郎忠勝と名乗った。武人の名乗りであるから、もちろん吉成も名乗る。もはや手向かうことも叶わぬことを見てとった吉成は、泥だらけでありながらも、威儀を正して忠勝に対していた。
「そちらの馬丁の印地打ちはなかなかのものでした。あれほど的確に急所に当てることができれば、戦の役に立つでしょう」
と太郎兵衛を誉めた。吉成は頷いたのみで応えない。忠勝は長湫一帯を見下ろせる色金山へと二人を連れて行った。捕虜を追いたてる、というのではなく、あくまでも客人を遇するような忠勝の態度である。
そして彼が吉成を案内したのは、金扇の旗印の真下であった。弔いの場みたいだ、と太郎兵衛は何故かそう思った。皆が重苦しく押し黙り、うるさいはずの足軽ですら、ここでは静まり返って控えている。
陣の中央に行くほど、息苦しくなっていく。男たちが具足の間から放つ臭気と、篭手の合間から見える所々欠けた指先が恐ろしいのではない。彼らが見つめる陣の中央から、ずっしりと頭にのしかかるような重い気配が流れ出しているのだ。
「殿がうかがいたきことがあると申しております」
そう言って忠勝は幔幕の外へと出てきた。中には数人の男がいる。太郎兵衛はさすがにその中には入れてもらえず、忠勝と共に外で待つように命じられた。
幕の間から、陣の中央に座る男の姿が見えた。丸い体つきをした初老の男である。だが頬は少年のように赤く、目はぎょろりと大きくて、柔和な笑みを浮かべているようにも見える。
思わずじっと見つめてしまった太郎兵衛に、その男は気付いた。
「弥八郎、その童は誰か」
と傍らにいた目付きの鋭い男にゆったりとした口調で訊ねる。弥八郎と呼ばれた男は、
「これある黄母衣衆の馬丁との由でございます」
と軋んだ声で答えた。弥八郎とは家康の参謀の一人、本多正信のことである。
「馬丁か。戦はあらゆることを教えてくれるから、悪くない考えだとは思うが、あれほど幼き子を連れてくるのはどうかな。物事には時宜というものがある」
家康は吉成に向かってやんわりとたしなめるように言った。だが吉成はやはり何も答えない。
「まあよい。そこで平八郎と遊んでおれ」
細められた眼から放たれた温かな光に、これが秀吉と五分以上に戦った男なのかと信じられない。
「いつしか天下に泰平が訪れ、お前のような幼子が何の憂いもなく遊べる日が来ればよいな」
家康はつと立ち上がり、太郎兵衛と忠勝の肩を抱いた。堅肥りの体は頑丈そうで、肩に置かれた手のひらは硬く厚かった。
「お前たちが槍を合わせることのないよう、わしらの代で何とかできればよいのだがな。戦の世も長く続いて、これからもまだまだ労が多そうだ」
そう言うとまた床几に腰を据えた。秣の匂いのする男だ、と太郎兵衛は思った。だが、幔幕が閉じられた瞬間に、全身が震えだした。あれがこの陣を覆う重みの正体だ、と気付く。
「どうした?」
忠勝が心配そうに太郎兵衛を覗きこんだ。
「わ、わからない」
ただ、あの家康という男が恐ろしかった。父が足軽たちの槍に囲まれた時も確かに怖かったが、それとは全く異質な、父が幔幕から二度と出てこなくなるような得体の知れなさが、あの柔らかな表情にはあった。
「怖い……」
と歯の根が合わずただ震える少年の肩を抱き、心配ない、と忠勝はあやした。
「危ういところであったが、よく戦ったぞ」
いかつい顔に似合わぬ、優しい声である。甲冑に使われる皮革の匂いが、震える太郎兵衛を少し安心させた。だが、太郎兵衛は幔幕から目を離せないでいる。恐ろしいのに、気になる。だがもう、決して見たくない怪物がそこにいる。
「そうじゃない」
やっとのことで声を絞り出した太郎兵衛の肩を抱いたまま、忠勝は陣の外に出た。
「よしよし、腹が減っているのだな」
空腹と恐怖のせいで気が動転しているとでも思ったのか、忠勝は自陣に太郎兵衛を連れて行った。父から引き離されるのは嫌だったが、家康の幔幕の近くにいるのはもっと恐ろしかった。
「ここにいれば怖くない。殿のおわすここが、浄土なのだ」
忠勝の声はあくまでも温かく、その手は力強かった。
「浄土?」
「そう。いくら筑前さまが強かろうと、殿の目が届くところで我らを打ち負かすことなどかなわぬこと。殿がある限り、三河から東は安泰であるし、俺がいる限り、殿は無事なのだ」
不思議な感覚だった。太郎兵衛にはあれほど恐ろしい家康という男が、忠勝には限りない安心を与えている。
「さ、ここが我が陣だ」
忠勝が連れているのは、わずか五百ほどの本多の郎党であった。家康の本陣の盾になるように、すぐ前に布陣している。ちょうど飯時であったのか、兵たちは立ったまま湯漬けなどを掻きこんでいる。忠勝の姿に気付くと、みな椀を持ったまま頭を下げた。
「そのまま食え。平八郎、一杯この子にやってくれ」
すると、忠勝の子、平八郎忠政が粥をなみなみと注いで太郎兵衛に渡してくれた。太郎兵衛より少し年かさの少年だが、忠勝とよく似た顔をしている。他の男も無表情で、太郎兵衛には一瞥をくれただけで何も言わない。
「父というのは、同じことを考えるものだ。俺にはすぐわかったよ。馬丁という名目で、息子に戦場を見せたかったのだろう」
と忠勝は目を細める。
「親子を見間違えることはない」
忠勝に食えと促されて太郎兵衛はさらさらと腹に流し込む。戦場の飯はもう慣れたもので、味は自陣で口にするものと何も変わらない。
「うまいか」
湯漬けに美味いも不味いもない。
「同じ」
と答えると忠勝は苦笑した。
「敵味方に分かれても、湯漬けの味は変わらんか」
腹が満ちると、恐ろしさは随分と減った。父は気になるが、いきなり殺されたりすることはなさそうだった。家康方の陣は静かだった。太郎兵衛が父とともにいる秀吉の本陣周辺はいつも、どこか賑やかな印象があった。
「筑前さまはお祭りで、殿は浄土だからな。静かなのは当たり前だ」
太郎兵衛の感想に、忠勝はそう経を唱えるように言った。
八
やがて、太郎兵衛は呼び戻されて、父と共に家康の本陣に留め置かれることになった。
「わしの手並みでも見ているがいい」
と家康は何を誇るでもない口調で言った。家康の本陣からは、池田恒興と森長可の陣が一望の下に見渡せた。山の下にいる時には、家康方の様子が何もわからなかったのと対照的である。
家康が下した命は、兵糧をとらせよ、攻めかけよ、という二つだけだった。後は何も言わず、床几に座って黙っている。周囲の幕僚たちも何も言わない。物見が時折、周囲の様子を報告していくが、家康は軽く頷くこともしないで静かに前を見ている。だが、家康が視線を動かしたり、手を軽く動かすだけで人が動き、軍が動き、そして人が死んでいった。太郎兵衛は何度となく、悪寒に似た震えを感じていた。
いつしか、太郎兵衛の相手をしてくれていた本多忠勝の部隊が姿を消している。
「平八郎さんたちがいない」
太郎兵衛が空になった陣を指差すと、吉成は口惜しげにくちびるを噛んだ。
「平八郎は大した男だぞ。ここから見えないところで働くのが惜しいな。筑前さまがどれほどの兵を率いていようと、平八郎の率いる五百を破るのは難しかろうて」
家康の傍らに立っていた神経質そうな男が言った。
「弥八郎、聞き苦しい」
主君にたしなめられて、本多弥八郎正信は慌てて口を噤んだ。
攻めかけよ、と命じられた家康方の諸軍は静かに、しかし凄まじい速度で長可軍に襲いかかっている。その先鋒の旗印は、白地に「無」と大書してあった。
「小平太は気負い過ぎておらぬな」
激しく双方から銃弾が飛び交い、情勢は互角に見えたが、左右から回り込んだ部隊が側面から森隊に攻めかかる。すると「無」の旗が再び前進を始め、長可の本陣へと突きこんだ。
喊声が風に乗って聞こえてくる。銃声が響くたびに、誰かが血しぶきを上げて倒れた。騎馬武者が二人組み打って地面に落ち、その背中を大槍が貫いていく。
武者たちは敵の首を掻き切るために悪鬼の表情となり、郎党は傷ついた主の首級を守ろうと束になって敵を押さえ込む。思わず目を逸らしかけたが、陣にいる誰一人として、戦場から顔を背けている者はいない。当然、吉成もそうであった。
これが武者の務めだ。
その横顔が言っていた。これが真の戦場なのだ。男が功を立て、名を揚げる場なのだ。太郎兵衛は吐き気を抑えて、再び戦場を見た。
半刻の間激しく揉み合っていた両軍であったが、急に森隊が潰走した。何が起こったのかと太郎兵衛が固唾を飲んで見ていると、
「森武蔵守長可どの、討ち取りました!」
との報がもたらされた。太郎兵衛が横目で父を見ると、あくまでも平静を守っているが、微かに奥歯を噛みしめているのが見えた。戦場の様相は一変した。あれほどの豪勇を感じさせた森長可の軍勢は今や逃げ場を求めて右往左往しているのみであった。
長可が討ち死にし、森隊が壊滅したことで、後詰めの恒興が軍を前に進めてきた。だが、勝ちに乗じた徳川方は余裕をもって迎え撃つ。
「紀伊守に攻めかかっているのは伝八郎か」
「はい。助勢はどうされますか」
家康の問いに頷いた本多正信は、次の下知を求めた。
「助勢は不要だ」
永井伝八郎直勝は、かつて家康の長子である信康に仕えていた。信康が信長から嫌疑をうけて命を絶つと一度は隠棲したが、その武勇を惜しまれて再び出仕している。率いている部隊は忠勝と同じく千に満たないが、錐のように池田隊に突撃して存分に蹴散らしている。
「紀伊守さまの動きが悪いな」
吉成はぽつりと呟いた。
「当然のことだ」
耳ざとく聞きつけた正信が意地悪く声をかけてきた。
「殿の陣構えは天下に比類なし。いかに筑前さまが戦に巧みだとはいえ、決して破ることはできぬ。今頃は小牧山を血眼になって攻めておられようが、城の守りと平八郎の槍先に翻弄されているであろうよ」
父は正信と目も合わさず、黙殺している。
「止めぬか」
家康が厳しい声で叱った。
陣内に緊迫した空気がみなぎり、太郎兵衛は失禁しそうになった。堅肥りの体が何倍にもなったように思え、戦の采配をふるう時の方がまだ優しげに見える。正信は身を縮めて俯いた。
「勝敗は共に我が傍らに常にある。百戦百勝の策を立てても、最後の勝利は神仏しかご存じない。己が全て差配できると思えば必ずや罰が当たる。だからこそ、心をこめて神仏に祈り、謙譲を忘れず必勝の策を講じるのだ」
声は静かだったが、誰もが逆らえない圧力がそこには秘められているように思えた。
「筑前どのは、いささか背伸びが過ぎるのではないかな。明智日向守の天下が良かった、と言われぬようにしてもらいたいものだ」
「背伸びとは、どういうことですかな」
太郎兵衛は、不気味な程の圧力を放つ家康に堂々と対している父の姿が頼もしかった。
「総見院さまのように、この国唯一人の神となり王となり、南蛮と張り合おうなど、できようはずもない」
吉成が言い返そうとした時、また一騎の伝令の兵が駆けこんでくると池田恒興を討ち取ったことを報告した。
家康は初めて大きく頷くと、吉成に対し、
「既にここ尾張での勝敗は決した。もう戻ってよいぞ。わしは清洲に戻る。あとは筑前どのによしなに計らって下さるよう、頼んでおいてくれ」
と告げた。吉成は一礼すると、太郎兵衛を伴って家康の陣を後にした。放した馬はいつの間にか本陣に繋がれており、飼葉もたっぷり与えられたのか上機嫌である。
「万事ぬかりのないことだ」
淡々と言う吉成の後鞍にまたがりながら、太郎兵衛は父の属する軍が大敗を喫してしまったことに落胆していた。
「負けたらどうなるの」
「負け? 誰が負けたのだ」
「だって、紀伊守さまや勝三さまは討ち死にしたって」
「そうだな……」
吉成は無念そうにため息をついた。
「だが、それが負け戦とは限らん。ここからが殿の戦だ」
父の言葉はやはり理解できなかった。
だが、半年ほどして家康が秀吉に屈服し、子の一人を人質に差し出したと聞いて、太郎兵衛はますますわからなくなった。秀吉が小牧長湫で戦っていたのはごく僅かな間だけである。家康が清洲に下がると見るや、秀吉も五月にはさっさと大坂へと引き返した。春から夏にかけて、尾張蟹江や北陸能登で戦闘は続いていたが、秀吉の興味は既に包囲網の解体に移っていたのである。
一戦で全ての形勢が決まる、と思っていた太郎兵衛からすると、秀吉の動きは驚くべきものだった。大坂にいて使者を送るだけで、戦場での劣勢をひっくり返してしまったからだ。
そもそも、家康が秀吉と戦った理由は織田信雄が頼ってきたことにある。同盟相手であった信長への義理だて、というのが建前としての開戦理由であった。秀吉も家康も、小牧長湫で矛を交えた結果、互いに死力を尽くしても何も得ることはないと考えるに至っている。
「紀伊守どのはそのようなことを仰っていたか」
家康のもとから帰ってきた吉成の言葉を聞いて、秀吉はしばし瞑目した。
「いや、確かに道理ではあるが、三河どのが寡兵を率いて山の上に陣取ったとして、何も備えがないとは思えぬ。紀伊守どのも勝三どのも、長湫に陣を敷いた時点で三河どのに全てを制せられていた。あちらの裾を捉えることは難しかったであろうよ」
吉成も、恒興の言葉を聞いた時は確かにそうだと思ったが、家康の布陣と采配を目の当たりにすると、ことはそう簡単でもないと考えるほかなかった。
「小牧で一度叩いておきたかったが、これも戦なれば致し方なし。他にやりようはいくらでもある」
戦いを避けたいのであれば、その理由をなくせばよい。秀吉は織田信雄の懐柔に乗り出した。激しい憎悪がある、と周囲が思ってもすっぱり捨てたように見せることが、秀吉の美点でもあった。
もちろん、ただ憎しみを捨てるということはしない。信雄が秀吉の申し入れを受け入れるよう、圧力をかけることも忘れなかった。信雄の領国である伊勢と伊賀に蒲生氏郷をはじめとする諸軍を入れ、そのほとんどを制圧してしまったのである。
家康は蟹江と竹ヶ鼻の攻防を通じて、尾張より西には兵を出さないと態度で示している。こうなると信雄も行き場がなくなる。そこを狙って秀吉は講和の誘いをかけたのであった。
信雄が屈服し、家康が兵を引いたとなれば秀吉に恐れるものはない。かえって紀州や四国を平定する口実を得て、大軍を差し向けて制圧してしまった。
「残るは九州だけですね」
気楽に言う太郎兵衛を、吉成はじろりと睨んだ。何か悪いことを言ったかと身を縮める。
「知らぬことは幸せだな」
父の口調に、ただならぬ気配を感じる太郎兵衛であった。

第三章 千雄丸、千熊丸
一
小牧長湫で秀吉と家康が対峙しているころ、九州にも戦乱の天地があった。
鎌倉時代から繰り返されてきた九州の覇権争いは、戦国の世に入ってから大きく動いた。中国地方から手を伸ばしてきた大内、毛利は既に衰退の激しかった少弐氏の勢力を手中に収めようとし、それが国人たちの動きを活発にしていた。
大友義鎮もその混乱に乗じて版図を広げようと豊後府内を拠点として三方に軍を送り込んだ。
豊前、筑前、筑後、肥後の多くを支配下に収めたものの、島津の反撃に遭って耳川の合戦で大敗を喫し、そこから攻守が逆転していた。大友の勢いが衰えたことを見てとった竜造寺家の主、隆信は猛然と軍を進め、大友氏が押さえていた九州北部の諸城を次々と陥落させたのである。
二方から島津と竜造寺という強敵を迎えて劣勢に立たされた大友義鎮は、秀吉を頼らざるを得なくなっていたのが、天正十二(一五八四)年の九州である。
もともと、九州平定は信長の予定の中に入っていた。
明智光秀や丹羽長秀に「惟任」や「惟住」といった九州人に馴染みの深い姓を名乗らせたのは、中国毛利の先を見ていた証である。
「大友の求めに応じて九州の無事を図る」
というのが秀吉の大方針であった。
だが、天正十三(一五八五)年の三月、沖田畷の戦いにおいて竜造寺隆信が討ち死にを遂げたことから、九州の情勢は一変した。
竜造寺隆信は肥後の虎と異名をとるだけのことはあり、勢力範囲と動員できる兵力だけでいえば、島津を圧倒していた。肥前一国を完全に支配下におき、筑州、豊州、肥後へと手を伸ばしていた。大友についていた国人、国衆の多くは竜造寺につき、その兵力は少なくとも二万は動かせる一大勢力となっている。
これに対し島津は薩摩一国に強固な地盤を持ち、大隅、肥後や豊後に勢力を広げているものの、その兵力は竜造寺の半数に満たない。だが、島津には他国にないものがあった。島津家久ら卓越した将領と、釣り野伏せ、捨て奸など家伝の戦法がそうである。
島津の将兵は戦場において恐怖を表に出さない。己に数倍する敵を前にしても平然としてたじろがないのである。
そんな彼らが得意としているのが、退却していると見せかけて敵を死地に誘導し、一気に反転して攻め滅ぼすという釣り野伏せの戦法である。このような戦い方は、将兵の間に強い絆があり、そして軍規が徹底しなければできない。
これが他の将だと中々うまくいかない。森長可は小牧山下の羽黒に陣を敷いた際に、家康方から攻撃された。一度軍を下げて敵を引き付け、包囲しようとした彼の思惑は、兵の思わぬ壊乱によって成らなかったものだ。
薩摩は隼人の昔から、中央のくびきから離れようとする傾向にあった。表向きは従うが、干渉は欲しないという姿勢である。だが秀吉は、九州で島津の勝手を許していては、天下に号令などかけられないと考えていた。
たとえ全体として見れば負けなかったとしても、秀吉は長湫で家康に痛い敗北を喫してしまった。四国や紀州攻めの勝利だけでは、まだ不足なのである。
「九州を平定してこそ、殿が目指した天下無事に一歩近づくことができる。小三次もそうは思わんか」
吉成も東の失策を西で取り返すのは賛成であった。
「しかし、島津もなかなかの狸ですぞ」
「東で大狸の相手をしてきたのだから、大したことはあるまい。いよいよ、海の向こうも見えてきたぞ」
「海の向こう、でございますか」
吉成はふと、家康が小牧の陣で言っていたことを思い出した。
「背伸びが過ぎるだと?」
目をむいた秀吉は哄笑し、すぐ真顔に戻った。
「小三次、人の身体は背伸びしてもそう変わらぬ。だがな、志と心は、いくらでも大きく育つのだ。そう殿に教えられたものだよ」
そう言って秀吉はにやりと笑って見せたものである。
秀吉は早いうちに、島津を屈服させたいと考えていた。もちろん、侮ってなどいない。竜造寺隆信を討ち取った手並みを見れば、好きにさせては何が起こるかわからない。そして腹背常ならないしたたかさも、秀吉の癇に障っていた。
豊前への攻撃を責めた使者に対しても、先に手を出してきたのは大友であって、自衛の戦いであると堂々と弁明して見せたものである。
そう弁明していながら、着々と戦線を広げている島津の魂胆は明らかであった。もし九州一円を領土とすれば、十万の兵を動員することができる。
だが、秀吉は島津の魂胆を封じ込める命令を下していた。「惣無事令」がそうである。天皇の名の下に大名間の私闘を禁じたものだ。これに反する者は、勅命に背く者として討伐される。
結局、島津は従わなかった。
秀吉が紀州、四国平定に動員した兵力がおよそ十万であることを考えれば、互角の戦力を手にすることになる。五分の兵力があれば、地の利のある島津が優位に立てる。もちろん、秀吉が全力を注げば十万を遥かに超える兵力を動かせるが、紀州も四国も定まったばかりで関東にはまだ手もついていない。西が揺らげば足もとが危うくなる、と秀吉は焦っていた。
「長宗我部に使いをしてこい」
と森吉成が秀吉から命じられたのは、天平十四(一五八六)年の夏四月のことであった。
「長宗我部と共に九州へ渡り、島津の北上を止めてくるのだ」
秀吉のもとに、九州の大友宗麟(義鎮)から島津の大軍が攻め寄せ、筑前へ侵攻する恐れがあるとの急報があった。秀吉の本隊は、いまだ紀州一揆勢の掃討に忙しく、西に振り向ける余裕はない。
そこで秀吉は、まだ味方になって間もない毛利と、帰順したばかりの長宗我部を主力として九州へ攻め込むよう命を下した。その交渉役、および軍監として吉成が土佐へと向かうことになったのである。
九歳になった太郎兵衛は、相変わらず犬飼九左衛門に鍛えられている。体も徐々に大きくなり、小刀と弓はもう一人前に扱えるようになった。馬は父に負けないほどであるし、印地打ちはますます威力を増している。
吉成は大坂に腰を落ち着けることもほとんどなく、長宗我部への使者の任には、太郎兵衛も連れて行くことになった。九歳とはいえ、太郎兵衛はおよその事情を理解してはいた。だがもちろん、扱いは馬子である。
吉成につき従う太郎兵衛の姿は黄母衣衆の名物となり、使いに出た先ではわざわざ太郎兵衛に会いに来る武将もいるほどだが、吉成は太郎兵衛に余計な口を挟むことを厳に禁じている。
「お前の一言で大事が失われたとしたら、お前や俺の首だけではすまぬ」
と言われれば、みだりに話をするわけにもいかなかった。
二人は大坂から便船を仕立てて九州へと向かった。船を用立ててくれたのは、瀬戸内の民、来島村上水軍である。早くから秀吉に従い、独立を認められた彼らの本拠地は、伊予と備後を隔てる小さな島、来島にあった。
だが、いち早く秀吉方についたせいで、毛利と伊予の大名、河野氏の攻撃を受けて来島を奪われ、一族郎党を率いて大坂へ逃れてきていた。
秀吉は、恐らく実益のことも考えてだと周囲は見ていたが、当主の村上通総を随分とかわいがった。出身地にちなんで、来島、来島、と呼ぶのが癖になっていたことを受けて、通総は自らの姓を来島と変えたほどである。
ともかく、来島通総は秀吉直属の水軍として、厚遇されていた。四国攻めでは海に精通した者として十二分に手腕を発揮し、今は伊予の風早郡に一万四千石の地を与えられ、大いに面目を施したばかりである。
通総は九州攻めに向けた準備のために大坂を訪れ、吉成たちの四国行きについても手はずを整えてくれたのである。
「おい何をのんびりしている。手伝わんか」
通総は港で大船を見上げている太郎兵衛の尻を蹴飛ばした。だが驚いて振り向いた少年の顔を見て、それが客の一人であることに気付いた。
「わはは!」
謝るどころか、水軍の将は笑いだした。
「お前の肌の色が我らと同じだから間違ってしもうたわ。尻を蹴られるのは鱶に噛まれるよりは痛くない。怒るなよ」
太郎兵衛の頭をくしゃくしゃと撫でまわし、あまりに明るい声で言うので怒りを忘れてしまった。
「土佐まで遠いんですか?」
「遠くはないが中々に厳しい海だ。お前、海は?」
「初めてです」
「じゃあ波に酔わないように神仏に願いを立てておけよ。ま、厳しい海を越えて行く値打ちがあるほどに土佐はいいところだぞ」
通総は自分と同じように真っ黒に日焼けした太郎兵衛に、親近感を抱いたようだった。船出の準備をしている水軍の者たちは、例外なく通総と同じ肌の色をしている。
「長宗我部の連中は気難しいのが多いが、人はいい。一度信じれば、それこそ一領具足の心意気で力になってくれるさ。俺にもう少し力があれば、あの土佐侍従のように四国切り取りに挑んでみたかったがな」
塩辛い声で豪快に笑う。土佐侍従とは、かつて秀吉包囲陣の一角を担い、今は九州攻めの先鋒を命じられようとしている長曽我部元親のことである。
二
来島通総の見送りを受けて堺を出港した船は、針路を西へととった。櫓の数五十丁の関船は、太郎兵衛の目には随分と大きなものに思われたが、まだ大きな船があるという。
夏の海は靄に覆われ、一里先も見えないほどとなった。その中を迷うことなく船を操る水軍衆の動きは太郎兵衛の目を奪った。だが、一刻もすると波は次第に荒くなり、彼は気分が悪くなって座り込んでしまった。
「大丈夫か」
と吉成に訊かれるなり口を押さえて船尾へ走り、腹の中のものを全て吐いた。
「大丈夫です」
吐いてもすっきりしないが、太郎兵衛はとりあえずそう答えた。吉成は平気な顔をして靄の向こうを眺めている。
「遠くを見るのだ。それか寝てしまえ」
そう言って行李の中から干した梅の実を取り出すと、太郎兵衛の口の中に放り込んだ。
「うまいぞ。船酔いに効くそうだ」
口の中に爽やかな酸味が広がり、確かにうまい。だがその旨味が腹の中で広がると、さらに気持ちが悪くなって、結局船べりから吐き出すこととなった。
梅の酸味が胃液の酸っぱさに替わってうんざりするが動けない。寝るなどもってのほかである。ひたすら空えずきを続けている彼の目の前に、大きな島影が現れた。
「淡路だ」
吉成は、太郎兵衛が身を乗り出して海に落ちないよう襟を掴んでいた。
「まだ道は半ばだぞ。伊予から筑州に船で渡るとなれば、さらに荒い海を行かねばならんと聞く。何せ、大海の中に激流が渦を巻いているのだからな」
「海の中に渦?」
「潮の流れとは不思議なものだぞ。北へ向かうかと思えば南へ流れ、西へ向かうと思えば渦を巻く。海を知らぬ者にはただ荒れ狂って入ることもかなわないが、腕の立つ船乗りはその流れに巧みに乗り、時にその中を突っ切って渡ってしまうのだから」
淡路の島影が遠ざかり、靄が晴れてきた。
「普段はこの辺りも荒いらしいのだが、今日は静かだな」
吉成がつぶやく。さきほどまでの波がおさまり、今度は気味が悪いほどに海は静かになった。風は時折西から強く吹いている。だが船は右に左に舵を切りつつ、前方に現れたさらに大きな島影へと近づきつつあった。
「あれが四国だ。目の前に見えているのは恐らく阿波だろう。ここから日和佐、甲浦を経て土佐に至るはずだ」
南へ舵を切ると、右手に緑の海岸線が延々と続く。数刻おきに浦が見えて、小さな人家が肩を寄せ合うようにして波風をしのいでいるのが見えた。海にも小船が浮かび、網を引いている漁民の姿が見える。
いくつかの港に立ち寄りながら、船はやがてひときわ長くなだらかな岸辺の沖合を進むようになった。風は相変わらず南西からの逆風で動きはもったりとしたものだったが、海に張り出すような険しい岸壁と、うらぶれた印象の漁村ばかり見ていた太郎兵衛は、遠くからでもわかる家並みの豊かさにほっとする。
「そろそろ土佐だぜ」
船頭が二人に声をかける。
「ここの殿さまが港を大きくして、街を広げてるんだ」
土佐侍従、長宗我部元親は四国を統一寸前まで切り取った戦国の申し子である。父の国親が土佐海岸に広がる平野の一角を治める国人領主から身を立てて周囲を平定すると、息子の元親の代になってその勢力は急拡大した。
元親が世に出た当時の四国には、阿波、讚岐に三好、伊予に西園寺、河野といった有力な大名が割拠していた。中でも三好氏は四国だけでなく畿内にも広く領土を持ち、将軍を手にかけるほどの勢威を示した。一時は九カ国を領し、天下人と目されたが、三好長慶の死後は三好三人衆、松永久秀などの有力な家臣たちが争っているうちに著しく衰えた。
西園寺には有力な武将がおらず、河野は中国毛利の支援を受けて激しい抵抗を見せつつも押されていた。四国は見る間に長宗我部の勢力へと変わっていった。
元親は父がのこした「一領具足」と共に四国を平定したが、海の外に出ることの不利を知っていた。彼が望んだのは、四国一円の力を背景にした半独立である。
信長が畿内で力を握ると見るや、四国の取次を任されていた明智光秀の仲介で誼を通じようとした。元親の母は美濃斎藤氏の出であり、妻は光秀の家臣として武名の高かった斎藤利三の妹で関係は深まっている。
だが、四国で急速に勢力を拡大した長宗我部を憎む伊予の西園寺と阿波の三好は、信長に直接、または秀吉に使いを送ってその討伐を求めていた。
信長は中国を押さえた後は、四国、九州へと進出する手はずを進めていたから、あまりに強い勢力が生まれることは望んでいなかった。結局、秀吉の意を受けた三好や西園寺の勧めを承諾する形で、四国へ軍を送る手はずを整えた。その総大将は織田信孝であり、補佐に丹羽長秀がつき、堺で出陣の準備を進めている所で本能寺の変が起こったのだ。
信長の死は元親にとっての僥倖となった。
彼は次の天下人が誰になるかを探り、秀吉がその筆頭であることを掴んだ。だが、秀吉は信長の時代から長宗我部には敵対的である。それに、秀吉が力を握れば畿内から近い四国に兵を進めてくるのは間違いないと考えた。
従って、元親が手を結んだのは全て秀吉に敵対した勢力である。柴田勝家とも連絡を取り合っていたし、徳川家康が目論んだ秀吉包囲網にも参加した。
だが、紀州の雑賀、根来が行ったような大坂突入など派手な軍事行動はとらなかった。
元親の関心は四国の平定であって、畿内ではない。家康の強さを聞き知った彼は、両者の戦いは長期にわたると予測していた。その間に宿願は成ると考えていたのである。
だが、この視野の狭さが、元親の首を絞めることになった。
秀吉は畿内の混乱を収めて家康と講和を結ぶと、伊予と讚岐をもとの領主へ返還するよう求めたのである。これは四国平定を目指す元親にとって受け入れられない条件である。
元親が抵抗する気配を見せるや、秀吉は羽柴秀次を淡路から、小早川隆景、吉川元春などを中心にした中国勢を備後から進めたのである。総勢十万を超える大軍を相手に、元親は抗戦の決意を固めて四万の軍勢を動員した。
だが、四国では無敵の一領具足も、本土で激戦を繰り広げてきた羽柴と毛利の精鋭には敵わなかった。やがて押し込まれ、元親が拠点として使っていた阿波の白地城への道は瞬く間に制圧された。
天正十三年の七月に、元親はついに降伏した。土佐一国を安堵された彼は、敵でありながら秀吉の度量に感心したという。
今の高知市にある大高坂山の廃城に手を入れて本拠地とし、城下と領国の整備に当たっていた。
大高坂山は土佐平野と土佐湾を見下ろし、南に鏡川、北に久万川を天然の掘割とする位置にある。室町時代にこの地の豪族が城としたが、しばらく使われていなかったものだ。
吉成たちが乗った船は、長大な砂浜が東西に広がる桂浜を大きく西に見ながら浦戸湾に入った。岬にはまだ新しい浦戸城が聳えて海を見下ろしている。桂浜が波を防ぎ、湾の波は実に穏やかだ。
「琵琶湖に似てる」
というのが太郎兵衛が抱いた印象だった。
土佐の入江は南が狭く、北に進むに従って広くなる。岸には水田が広がり、農村と漁村が交互に現れる。衣ヶ島、玉島という形のよい小島が二つ浮かび、その間をぬけてしばらく北に進むと、いよいよ大高坂山が見えてくる。
既に吉成たちの到着は知らされていたのか、港に着くと迎えが来ていた。
緊張した面持ちの少年が数人の近臣の先頭に立って船を見上げている。下船した吉成が挨拶をすると、
「谷忠兵衛忠澄にございます」
と近臣の中でもっとも恰幅のいい男が礼を返してきた。忠澄は長宗我部家の家老で、秀吉と戦う不利を元親に説いていた経緯もあり、両者の講和に尽力した人物である。
「こちらは千熊丸さまにございます」
と少年を紹介した。
「土佐侍従さまの若君にお出迎えいただけるとは、恐縮にございます」
吉成も丁寧な口調で述べた。
太郎兵衛は、千熊丸という少年をしげしげと眺めていた。自分よりも少し年長に見えて体も大きいが、優しげな顔だちをしている。千熊丸は太郎兵衛の視線に気付いたのか、彼を見て微かな笑みを浮かべた。
「使者の務め、大儀でございました」
吉成ではなく、太郎兵衛に目を向けたまま言った千熊丸は、二人を先導して大高坂城へと戻った。これが後の長宗我部盛親であった。
三
大高坂山城は、遠望すればごく小さな山城でしかない。だがその真下に立つと随分と大きく見えた。天守もなく、石積みと生垣の間にいくつかの曲輪と矢倉が設けられている。石段を登りきったところに、館が建っているだけの簡素なものであったが、頂に至るまでの道は急峻だ。
後ろを振り返ると、船が通ってきた浦戸湾が見える。南からの風が微かに潮の香りを運んできた。
谷忠澄に促され、吉成は広間へと通される。太郎兵衛は相変わらず馬丁という扱いではあったが、もはや吉成の息子であることは知れ渡っているので、客として遇されている。吉成は玄関口で待つよう命じるのが常であったが、迎える方はそうもいかず、結局客間に通されるのであった。
「噂は聞いていたが、子連れの使者とは珍しい。だから俺も熊を迎えにやったのだ。森どの、もはや我らの間には何も難しい話はないのだから、連れてくるがいい」
声が客間まで聞こえてきた。谷忠澄が迎えにきたので、太郎兵衛も吉成の隣に座ることになった。最近では珍しいことでもなくなり、吉成は息子を見ることなく、微かに目を伏せて黙っている。
子供の目で相手がどう見えるかを訊ねることもある。だが相変わらず、口を開くことは厳しく禁じられていた。
太郎兵衛は顔を上げる。広間の奥に胡坐をかいて座っている四国の元覇者は大きな男だった。座っていても見上げるほどだ。
「関白さまの大坂の城、普請の方はいかがか」
と元親の方から口を開いた。普通に話していても広間に響き渡る、堂々とした声である。
「稀に見る壮大なものとなりそうです」
「そうだろう。あれほどの軍勢を動かせる天下人であれば、比類なき城こそふさわしい」
元親は秀次が率いた羽柴軍の威容を、素直に誉め称えた。
「天下に敵なしとはこのことだ」
「いえ、いまだ天下は定まっておりませぬ。九州は島津の暴虐いまだ収まらず、豊後から助けを求める急使が至っております。援軍を送らねば、九州は島津のものとなってさらに戦乱の世が続くでしょう」
「それはいかんな! となれば、以前海を渡ってきたあの精鋭たちが、再び海を渡るというわけか」
元親の口調は明るいが、あくまで他人事であるという姿勢を崩していない。
「いえ、九州への先鋒は土佐侍従さまにとの殿のお言葉です」
吉成は秀吉からの書状を元親へと手渡した。そこには、陣立ての内容や九州上陸の期日、戦うべき相手と戦場となりうる場所まで詳細に記してある。
大友氏に味方する諸将から届く援軍の求めは急を要するだけに、具体的であった。秀吉は黒田孝高や小早川隆景ら備州に拠点をおく者たちに、九州の動静を探らせ、戦略を立てていた。
「豊前小倉の線で島津を食い止め、反撃に出るというのか」
元親は不愉快そうな表情を浮かべ、くちびるを曲げた。
「我ら土佐の一領具足は四国を出たことがないのでな」
「出たことがなければ戦えないと申されるか」
「先だって関白さまと戦った際、多くの兵が倒れてまだ国は回復しておらぬ。知行も土佐一国となって蓄えもない。聞けば島津は鉄砲を無数に持っているというではないか。一領具足は文字通り一領の甲冑しかないのでな」
心得と金があれば、二領の甲冑を用意するのが武家のたしなみであった。だが、半農の土佐軍は多くがひと揃いしか持っていない。海を渡るとなれば、必要となる糧秣も船も膨大な数となる。
「我らは九州に上陸する前に干上がってしまうな」
と元親は笑う。
「これは好機であることをご理解下さい」
吉成はその笑みを消すような厳しい声で言った。
「土佐侍従さまはこの度、殿に心を寄せられて三国を返された。ですが、まだ天下の多くはまだ野望を捨てていないと疑っている。小早川、吉川の両家が何故大兵を率いて四国へ渡られたかおわかりか」
毛利家中においてそれぞれ山陰道、山陽道を任されていた小早川、吉川は西に進出してきた織田方、とりわけ秀吉と長きにわたって激しく戦っていた。だが一方で、安国寺恵瓊といったすぐれた使僧を仲立ちにして度重なる交渉を行ってきた。
秀吉は毛利方の「両川」の力を認めていたし、毛利方も恵瓊から聞いた秀吉の人物と信長亡き後の水際立った振舞いに、家の命運を託すべき相手と見てもいた。四国攻めの時に、大挙して軍を送りこんできたのは、四国に領土を得ようとするためではない。秀吉のために働くという姿勢を明らかにするためであった。
「旗幟を明らかにするための好機だと申すか」
「殿は全ての武人は天下惣無事のために働くべしと申しております」
「天下惣無事、か……」
元親はしばし瞑目した。
「よくわからぬ。四国ですら俺には広かった。天下なべて事もなし、などできるのか」
「総見院さまの後を引き継いだ殿ならできますし、必ずやしてのけるでしょう。その先頭に立つことは、土佐侍従さまにとっても必ずや良き結果を招くはずです」
吉成の言葉に元親はしばし黙って聞いていたが、やがてゆっくりと頷いた。
「わかった。土佐の国中に陣触れを出そう」
吉成は表情を崩さず手をつき、丁重に礼を述べた。
「俺もこれまで散々たてついておいて、すぐに信を置いてもらえるとは思っておらぬよ。いずれ何らかの形でご奉公せねばならんが、いきなり島津の相手とは関白さまも中々に厳しい」
「お味方と心を許されているからこそのお願いです」
元親は頷き、太郎兵衛に視線を向けた。ちょうど張り詰めた空気が緩み、太郎兵衛は大きく口を開けて呼吸を繰り返している所だった。
「こうして政は決まっていくのだ」
慌てて口を閉じ、頭を下げる。
「お前も九州へ行くのか」
太郎兵衛が横目で父を見ると、微かに頷いた。お答えしろ、と促されて、
「左様でございます」
自分でも驚くほどの大声が出た。
「元気のいいことだ。うちの熊と年が近いようだから留守番でもしていてもらおうかと思っていたのだが、立派に働けるようだな。励めよ」
「はっ」
と手をついたところで、不意に背後が騒がしくなった。
「千熊丸さま、お待ちを!」
谷忠澄の声を振り切るように、一人が広間に走り込んできた。吉成たちに一礼した顔を見て、太郎兵衛は驚く。港まで迎えに来てくれた元親の子の千熊丸である。太郎兵衛は何事かと吉成と元親の顔を交互に見るが、吉成は表情を動かさず、元親は手で顔を覆っている。
「今は大坂からのご使者と大切な話をしているというのに、何だ騒がしい」
「お願いがございます」
どんと拳を広間の床板に叩きつけ、千熊丸は言葉激しく、九州攻めに帯同してくれるように頼んだ。港で見た柔和な印象が消え、名の通り熊のように猛っている。
「それはここで言わねばならぬことか」
「羽柴公の使者が来ている今こそ、願い出るべき時と心を決して参りました。島津は九州の覇者として土佐にまで名が轟いております」
「お前が島津と戦うとでもいうのか。まだ十二ではないか。焦ることはない。元服すればいくらでも戦に連れて行ってやる」
「戦はいつまでもあるとは限りませぬ。四国は関白さまの制するところとなり、島津がもし屈服すれば私はどこで名を揚げればよいのですか」
「名は戦場だけで揚がるものではない」
「ですが、戦で勇士と認められることこそが功名を挙げるただ一つの道です。それにこれあるご使者は私より年若い。務めを果たすのに元服しているかどうかは関わりのないことです」
吐き出すように一気に訴えるが、元親は首を振ってため息をつき、
「雄、雄はおるか」
と誰かを呼んだ。太郎兵衛がただならぬ気配に振り向くと、元親に背格好のよく似た、しかし顔立ちは際立って美しい若者が立っている。
長子の千雄丸信親である、と元親は紹介した。
「また熊が駄々をこねている。今は見ての通り、ご使者と談判中だ。連れて行ってくれ」
信親は静かな足取りで千熊丸に近づいていく。千熊丸も少年にしては大柄だが、信親に比べれば全くの子供だった。
「行こう」
兄が静かに言うと、千熊丸は怯えた表情を浮かべ、諦めたように立ち上がる。そして肩を抱かれるようにして広間から去った。気まずい沈黙が広間を覆ったが、
「さて、陣立てのことですが……」
吉成がごく自然に話を再開したので、元親もほっとした表情を浮かべたのであった。
四
吉成たちが元親と話を進めているころ、秀吉のもとには大友宗麟が訪れていた。島津の攻撃は激しく、もはや直接秀吉にすがるしかないところまで追い詰められていたのである。ここに至っても、秀吉は内心では交渉で島津が屈服すれば、それ以上ことを荒立てるつもりはなかった。
秀吉には見る者をひれ伏させる威厳こそなかったが、眼力は信長に劣らず、加えて「人たらし」と呼ばれるほどの術があった。
「相手に惚れさせよ」
と、秀吉はよく側近に言っていた。惚れた相手に、人は従うのだ。そうなれば争わずとも済む。吉成にはその実直な性格から、誠のみで押せと指示することが多かった。だが、版図が広がるに従って、できることなら相手を惚れさせてこいと命の最後に付け加えるのが常となった。
「何かをさせるにも、向こうからその気になってするのと、嫌々させるのでは大いに違うぞ。これほど愛しい女子はおらぬと思うて、対するのだ」
これには吉成も閉口した。彼はそれほど、女性に熱心なわけではない。当時はごく普通であった衆道もたしなんではいない。
「小三次は堅すぎる。女心の一つでも学んでこい」
秀吉はそう吉成をからかったが、その目は笑っていなかった。
「というてもお前が遊女屋通いするとも思えんから、一つわしが伝授してやろう。女は男の何に惚れるか。これだけわかっていればいいのだ」
人さし指を立てて、吉成の前に突き出す。
「もちろん、見目麗しければ放っておいても女は惚れる。だが、顔の美しさなどは三日もすれば飽きる。美しさを誇るなら、周りから飾っていくのだ。己が身の周りがきらびやかなら、自然と本人も美しく見える。わしがそうだろう?」
秀吉は大坂に巨大な城を築いていた。土台となった石山本願寺も、寺の範疇を超えた巨大なものであったが。東西七町、南北五町というから、その面積はおよそ三十五万平米にもなる。だが、新しい大坂城は桁が違った。
上町台地の北端に五層八階の大天守を置き、北を淀川本流、西は船場、南は谷町、東は森ノ宮と本願寺の四倍にも及ぶ。本丸は外堀と内堀、そして惣構えと呼ばれる外郭にも堀を巡らし、本丸に至るには急峻な石垣と複雑に入り組んだ曲輪の間を抜けなければならない。城攻めの名手であった秀吉ならではの、鉄壁の城であった。
「次に、高貴であるかどうかだ」
秀吉は二本目の指を立てた。彼は守護代の子であった信長や、三河の土豪であった家康に比べても、誇れる血筋などというものは全くなかった。だが、信長の死後は積極的に官位を取りにいった。
困窮していた朝廷は、手を差し伸べてくれる者に権威を与えるのが通例となっている。その様をつぶさに見ていた秀吉にとって、貴顕に列せられることは難しくなかった。先例、前例に縛られた世界であっても、それはあくまでもごく小さな盃の中の慣習であり、抜け道はいくらでもあった。
吉成が四国へ行く際には、秀吉は正二位内大臣となっており、さらにその上の位を得るべく手を回していた。
「高貴な位にしばらくいれば、わしが尾張で針を売っていたことなどやがて忘れる。土に汚れた猿に抱かれるのは嫌でも、大臣さまの手の中なら自ら帯を解こうよ」
そして最後は、と三本目の指を立てる。
「何だと思う?」
吉成は首を捻った。確かに、豪壮な城と高い位は女を口説く時に役に立ちそうだ。見目の良さは関係ないと言っているのだから、
「戦の強さですか」
と答えた。
「違う!」
手を叩いて秀吉は喜ぶ。まるでそう答えるのを予期していたような、してやったりの表情を浮かべている。吉成は、天下の半ばを取り、内大臣となってもこのような稚気を見せる秀吉が嫌いではなかった。
「そこだよ」
と秀吉は真顔になって言った。
「天下を睥睨する巨大な城を建て、十万の軍を動かして敵する者を打ち倒す。廟堂にあっては大臣の位にあり、いかなる将もその前には手をつかなければならない。だがその正体は、見ての通り猿顔の阿呆だ」
これで女はほっと安心する、と秀吉はにんまりと笑った。最近伸ばし始めた髭が、どうにも鼠を思い出させてぱっとしない。だがそのぱっとしなさが、天下人という言葉の恐ろしさを和らげているのも事実だった。
「畏れさせ、敬服させ、その後に安心させる。これに勝る手はない。ま、通じないお方もいるが」
秀吉は何かを思い出すようにうっとりと目を閉じた。吉成は、秀吉が秘かに想いを寄せていた女性を知っている。
信長の妹であるお市の方である。浅井長政に嫁ぎ、その滅亡後は柴田勝家に嫁いで、最後は夫と運命を共にした。
「あのお方だけは、今のわしにもなびかなかったろうな」
そう呟く。吉成はお市の方の姿を目にしたことは一度しかない。清洲会議の後、勝家に輿入れする交渉の際に見た。確かに、ぞくりとするほどの美しさと儚さと、そして強さを感じる女性だった。天下に聞こえた武将を二人続いて夫にするだけの「格」を感じさせたものである。
「何故あの時、お市さまを引き取らなかったのです?」
政としてだけ見れば、彼女を勝家に嫁がせたのは間違いではなかった。秀吉への反発が一時的にせよ弱まり、その間に周到な準備を整えることができた。
「欲しいものを我慢した方が、より大きな果実を得ることがあるのだ」
秀吉はお市の方に手を伸ばさなかった代わりに、信長家臣筆頭の地位を得たのだと言いたそうであった。だが吉成は、それが真実ではないと見抜いていた。
「怖かったのでしょう」
そう言うと、秀吉は照れ臭そうに頷いた。
「まあな」
秀吉はごく近い者には本音を漏らすことがある。誰に惚れた、振られた、勝った、負けたといっては抑えることなく笑い、泣く。だがお市の方の時だけは違った。じっと己の中に秘めて、このように控えめにしか表に出さない。それがかえって、秀吉の本気を思わせた。
「だが今のわしなら、そぐう相手になったのかもしれん」
「だから茶々さまを引き取ったのですね」
「よく似ている」
秀吉の頬は初恋のただなかにいる少年のように赤くなった。
「何とかあの娘に惚れてもらいたいものだ。あれほどの美しき者にわしの血だけでなく、心も受け継いだ子を産んでもらえたら、どれほど幸せなことか」
それだけの賢さと器量が、あの娘にあるのかと吉成は内心首を傾げた。だが、織田信長の姪であり、浅井長政の娘という茶々の血筋にはそれだけの夢を見させる高貴さがあることも、また事実だった。
秀吉には天下を覆う大胆と、娘の心に右往左往する小心が同居している、と吉成は感じていた。だがこれほどの幅がなければ、天下を左右できないのかもしれない、と長年秀吉と接してきた吉成も考えるようになった。
「それはそうと、お前もそろそろわしのような手管を使えるようにならねばならんぞ」
表情を改めて、秀吉は言った。
「何事です」
「そろそろ国持ちになってもよかろう」
さらりと秀吉が言ったものだから、吉成は驚いた。秀吉の側近、黄母衣衆として常に秀吉の身辺に侍り、四方へ奔走することが務めだと信じていた。吉成よりも遅くに仕えた者が大きな知行を得て大名となっていく。だが、彼は何とも思わなかった。秀吉の使い走りほど面白い仕事はないのである。
「お前にはそれだけの力がある。九州を平らげれば、一国を頼みたく思う。そのためにはまず土佐の長宗我部を動かしてくるのだ」
吉成もそう手をとられて気分が悪かろうはずがない。珍しく高揚した気分で大坂を後にした。だが、長宗我部元親が出兵を承知した後、宿に案内されたあたりで思い当たることがあった。
「うまく言うものだ」
と自然と苦笑が口元に浮かぶ。惚れさせる手管に見事に引っかかっているのは自分だ。そして、己が一番惚れていると思わせているあたりも大したものだ、と吉成は感心していた。
秀吉は天下に近づくにつれて、家臣団の陣容を厚くすると共に、入れ替えを試みていた。石田三成や大谷吉継、小西行長に前田玄以など、秀吉が万石の知行を持つようになってからの家臣は、吉成から見ても輝くような才能を持っていた。彼らは戦場にあって強いだけでなく、畿内の統治、兵站の管理や四方との交渉を任せられ、秀吉の期待にこたえる働きを見せていた。
賎ヶ岳で七本槍と称せられて活躍した若武者たちも、大変な抜擢を受けている。二十歳そこそこにして従五位を受けた加藤清正や福島正則などはその筆頭である。もはや子供のように見える者たちが、殿上人となっているのだ。
吉成とて、彼らと同じように働いて秀吉を支える気概は持ち続けているが、若さの放つ武と才の煌めきにはため息が出る。
「それで、よい」
一抹の寂しさはあるが、致し方のないことだ。天下は広い。吉成も使いをして交渉する相手が、野盗の類から国人、そして大名や大大名へと替わるにつれて、とてつもない重圧に苛まれるようになった。
秀吉が戦陣に出れば矢玉を恐れず駆け回ることができるが、帷幕の中で詰将棋をするような小牧長湫での戦の雰囲気は、正直あまり好きではない。そのような気配を、敏感な主君が見逃すはずはなかった。
気付くと、太郎兵衛がじっと見つめていた。
使者として出かける時に、馬丁として帯同するようになって二年ほどになる。大坂に帰れば犬飼九左衛門に鍛えられ、暇があれば相変わらず石合戦に明け暮れる日々だ。日に焼けて真っ黒な「焦げ坊主」が国持ち大名の子かと思うと、おかしくなる。
「何か用か」
「千熊丸さまが遊ぼうって」
四国に覇を唱えた男の子と、己の息子が遊ぶというなら、それなりの箔をつけてやらねばならんか、とも考える。
「行ってこい」
「しゃべってもいい?」
「当たり前だ」
太郎兵衛は嬉しそうに頷いて駆け出して行った。
五
秀吉は島津に「惚れさせる」ことはできなかった。
その力も位も、「成り上がり者」と罵られては用を為さない。鎌倉の世から守護大名として九州に勢威を誇る島津は、他家と比べても別して古く、そして強かった。かつて同じく伝統と強盛を誇った武田、今川、大内、大友などの諸家は既に没落しているのに、島津家だけは違う。勇ましくも秀吉との和解案を蹴り、本格的に北上を始めて筑前へと侵攻していた。
秀吉もついに大軍を催して九州へ攻め入ることになったが、あくまでも四国と九州の軍が中心である。だが、土佐では思ったように準備が進まず、吉成は焦っていた。
「今は畑仕事で忙しいからな」
元親は急かす吉成に対し、渋い顔で言い返した。四国では、軍の主力となる兵たちはまだ専業となっておらず、半農であることがほとんどだった。一領具足と呼ばれる者たちが、田畑の横に武具を立てかけていたという話はその象徴である。
九州へ入るのは夏ということになっているが、田畑の世話で忙しい時期でもあり、兵たちの士気は上がらなかった。
「天下の戦いといっても、彼らには通じぬよ」
「天下のために戦うことが、己の田畑を守ることだと教えて下さい」
と吉成は元親に懸命に説いた。そういうことなら、と元親も主だった者たちを集めては厳しく言い聞かせたものの、やはり軍の動きは緩慢だった。
四国から出征するのは、土佐の長宗我部と紀州攻めの功を認められて讚岐高松を領していた仙石秀久、かつて四国讚岐で長宗我部と争っていた十河存保、伊予の小早川秀包であった。
「もう讚岐や伊予は出撃の備えが整っているようです」
と吉成から聞いて、元親も焦りを覚えた。仙石秀久と元親の間には、因縁がある。四国攻めの際に、淡路から讚岐に上陸した秀久は、長宗我部軍の攻撃によって敗走し、幟を奪われるという恥をかかされた。
秀久は武勇をもって知られていただけに、この敗戦には含むところが大きかった。讚岐に十万石を与えられたのは、土佐の監視という意味合いもある。ここであまりに遅れると、秀久がどう秀吉に讒言するか知れたものではなかった。
六月に入り、筑前の情勢はいよいよ緊迫してきた。天正十四年七月、太宰府を眼下に望む岩屋城が島津軍およそ三万に包囲されたのである。
大城山の中腹に築かれた山城に篭るのは、高橋紹運をはじめとするわずか七百名あまり。ここと隣接する宝満城、立花城がある。立花城に篭るのは、高橋紹運の実子にして立花道雪の養子である宗茂だ。この線を破られると博多が丸裸となる。
博多は朝鮮や中国との貿易の大拠点であり、ここを押さえられては島津の力が倍加する。それに、博多を押さえられると残された大きな拠点は小倉だけとなり、九州全土を制圧される危険があった。
秀吉としても、それだけは絶対に避けなければならない。
大坂と土佐を忙しく往復している吉成の弟たちも、秀吉からの厳命を持ち帰っていた。ようやく準備が整った長宗我部軍と共に、伊予の松山で仙石秀久と合流したが、秀久の機嫌はすこぶる悪かった。
若い頃にその勇猛を信長に称賛されて秀吉の馬廻り衆となった彼は、四国の諸将を下に見る態度を隠そうともしなかった。しかも元親はかつて讚岐の引田で対戦し、旗印を奪われた相手でもある。秀久の肩には無用な力が入っていた。
「遅いではないか」
元親の顔を見るなり、秀久は噛みついた。
「これで九州を島津に切り取られるようなことになれば、土佐どのの責めになるぞ」
と決めつける。
元親はあまりの口のききように、手を刀の柄にかけかけたが、すぐに下ろした。土佐三千の兵を率いて本陣で喧嘩騒ぎなど起こせるわけがない。秀久もそれがわかっていて罵倒したのである。
「軍を出すには準備がいるのだ。文句を言うな」
元親が言い返すと、秀久は舌打ちをして顔を背ける。そして、険のある空気のまま、軍議となった。
四国から九州へ渡るには、伊予の西端、角のように突き出た三崎半島から、佐田岬を右に見つつ西へ進むのが常道だ。豊後の別府に近い、佐賀関の港までは二十里もない。
もし島津の本隊が筑前に集結しているのであれば、四国の軍勢が豊後に上陸してその背後をとることに大きな意味があった。
「即刻渡るべし」
と秀久は主張した。だが、四国の諸将はいい顔をしない。三崎から佐賀関まではごく近い。徒歩であっても二日もあればたどり着ける。だが、その間に横たわる海峡は「速吸瀬戸」と呼ばれている難所だ。
「越前守どのは海を知らぬ」
元親はなるべく穏やかに諭そうとした。四国軍の数はおよそ六千。それだけの軍勢を渡す水軍は、秀吉側も配下に収めてはいる。村上、九鬼、河野などの有力な海の民は秀吉に臣従していた。だが、彼らも秀久の性急な求めには渋い顔である。
「あの瀬戸はただ出て行っても流されるだけだ。南に流されたら最後、二度とは戻ってはこられぬ。戦わずして軍の半ばを失うこともありえるのですぞ」
秀吉から十分な援助を受けて自らの水軍を再建した来島通総は、秀久の無謀を止めた。それでも、
「では間に合わずして九州の岩屋城が落ち、筑前国が島津の手に落ちたらどうするのだ。この軍半数の犠牲ではすまぬぞ」
と秀久は譲らない。
「九州への討ち入りは関白さまの意である。これに逆らう者は、わしの槍にかけて許さぬ」
だが折りから、嵐の気配が伊予にはたちこめていた。水軍の頭として、来島通総が冷静に口を開いた。
「夏に南からの風が強き時は、決して海に出てはならん。うねりが行く手を阻み、瀬戸の流れが船を押し流す。確かに関白さまは大いなる力をお持ちだろう。俺も随分と世話になっている。人が相手なら、俺たちも白刃をふるっていくらでも突っ込んでやる。だが、相手が海となれば話が違う。どれほど偉い人間だろうと、命など聞かん。それでも行くというなら、勝手に行ってくれ」
歯切れのよい通総の反論に、秀久は顔色を変えた。
「貴殿の言い草、よくわかった」
そう言って本陣の後ろに立てかけてある槍を手に取る。
「ではこれより、わしが水軍の指揮をとる。来島通総は戦意なしとして謹慎。土佐侍従どのをはじめ、四国の諸軍は早速船に乗って瀬戸を渡れ。もし文句があるなら、わしが相手になるぞ」
戦場で数々の武勲を挙げた槍のきらめきが人々の目を射る。通総は怒りに黒き顔を紅に変えて本陣を出ていき、気まずい空気が満ちていく。
「さあ各々方、軍議はここまで。とく出立の備えをされよ。関白さまの尖兵となり、ご恩に報じるのだ!」
声高々に命じた秀久が槍を再び従者に渡したところで、元親が立ち上がった。勇猛な容貌の秀久を圧するような偉丈夫ぶりである。元親はこの時代の男にしては飛び抜けて長身であった。
「仙石越前守」
その声は、これまでと明らかに違っていた。
「な、何か存念があるなら申してみよ」
満足げだった秀久の表情が強張った。
「確かに、関白さまの九州討ち入り、天下惣無事のお志は天晴なものであろう。我らのような田舎武士には到底思いも及ばぬことではある。だが、四国の山と海になずんできた者も、それぞれ一領の具足をもってこの大事に馳せ参じているのだ」
「そんなことはわかっている」
秀久は元親に気押されないよう、ことさら厳めしい顔を作った。
「天下の無事は四国の武家や民百姓、すべての者のためでもある。関白さまの尖兵となることは、先々の幸せにつながると心得られよ」
「それは小三次どのからもうかがった。で、あるならば」
元親が一歩秀久に近づいた。
「四国の者の命を軽んじるようなことを口にするのは止めよ。彼らは戦に出ても、また帰ってきて土を耕す。海に出て漁もする」
秀久も左右に肩の広がった魁偉な体つきをしている。だが四国の覇王はさらに一回り大きかった。静かな怒りが、元親をさらに大きく見せて本陣内にいる者は言葉を失っていた。
「ふん、時代遅れなことだ」
秀久は一つ鼻を鳴らした。信長の試みを引き継いで、少しずつ専業の戦闘集団の育成を行っていた秀吉軍には、いつでも動員できる兵力が存在した。秀久が率いている讚岐の軍団にも地元の農民から徴した兵もいるが、その主力はあくまでも秀久が鍛えてきたものだ。だが、一領具足は秀久の攻勢は退けている。
「我らは関白さまのために命を懸ける兵だ。それほどの気概を持たぬと、これまでの反抗を帳消しにはできぬ、という意味で言ったのだ」
と秀久は弁明する。
「言っておくぞ」
居丈高な口調を取り戻した秀久は、
「誰がこの四国の指揮を執っているのか。それは長宗我部でも十河でも村上でもない。この仙石越前守である。我が命は関白さまのお言葉と肝に銘じよ」
と宣言した。元親に気押されたことを消し去ろうとするほどの大声だ。四国の諸将は鼻白んだ表情を浮かべ、本陣を後にしようと立ち上がろうとした。そこに、
「権兵衛!」
と末座から鋭い声がかかった。
六
軍議の間、口を一切開かなかった一人の男の方を、皆が見た。秀久もまた誰か文句をつけるのか、と心配と怒りで顔を真っ赤にしながら顔を向ける。そしてほっとしたように、
「小三次か……」
と呟いた。
「何だ。陣立てに何か異論があるのか」
秀久と吉成は古い付き合いである。信長が斎藤龍興を稲葉山に滅ぼした際に、美濃の土豪であった仙石氏は織田方に投じた。吉成はすでに馬廻り衆として秀吉に仕えていたが、秀久もその一員に加わったのである。
吉成がそのまま秀吉の馬廻りに残ったのに対し、秀久は軍を率いて先陣に立つ道に進んだ。十万石の大身とくらべものにならないほどに微禄な黄母衣衆ではあるが、吉成は全く遠慮なく秀久を呼び捨てにしてのけた。
「お前は殿からそのように四国の者たちを追い使えと命じられてきたのか」
そう問い詰めた。
「おうよ。これまで乱れていた四国の諸軍をまとめるために、大いに働けと命じられておる。これまで千々に乱れていた者たちを一つにして戦いに差し向けるのであるから、関白さまの威光に服させなければならんだろうが」
秀久も遠慮なく言い返す。
「この短慮者め」
吉成は叱りつけた。
「四国の諸将は我らのような成り上がり者にあらず。累代この山河と海を守ってきた者たちだ。戦乱の世に勝敗はつきものといえども、ただ力で押さえつけて死地に向けることを殿が命じるものか。既に土佐侍従さまをはじめ、皆が大坂に心を寄せている今となってはその戦いぶりを助けるのみで足る。お前の言い草は殿の姿を悪しきものとし、これから戦に臨もうとする士の心を意味なく挫くものだ」
これまで無言だった吉成の怒りに、元親らは驚いた表情を見せていた。秀久は顔を真っ赤にして吉成を睨みつけていたが何も言い返すことができず、大きな咳払いをしながら本陣を去った。
秀久が去った後、吉成は来島通総を呼び戻して再び元親の後ろに控え、軍議の続きを促す。それを受けて元親が口を開く。
「仙石どのはあくまでも軍監である。この戦、主軍となるは我ら四国勢だ。確かに関白さまと俺は長年戦ってきたが、矛を収める誓いをしたからにはその御為に働くのは当然のことである。さりながら、速吸瀬戸を越えるにはそれなりの備えが必要だ」
元親は、仙石勢が四国へ攻め入った際に使った船を伊予まで回航させ、それを渡海に使うという案を出した。淡路から讚岐までの海は速吸瀬戸よりはまだましだが、それでも播磨灘の荒波は激しい。それを越えるだけの頑丈な造りをしている船だ。
「来島どのには水先案内をお願いしたい」
来島通総は緊張した面持ちで頷いた。水軍を率いる彼らは、海を知る者でも気の抜けない瀬戸を、六千の軍を渡せるか潮目を見極めなければならない。
「では各々、四国に兵ありと天下に見せつけてやろうぞ」
という元親の言葉で軍議は決した。
軍議が紛糾していた頃、太郎兵衛は千熊丸と山の上から海を眺めていた。山までは後藤又兵衛が送ってくれた。又兵衛は、黒田官兵衛の息子、吉兵衛長政と仲違いして出奔し、仙石秀久の厄介になっている。
「今度は俺も派手に暴れてみせるぜ」
と力こぶを作る又兵衛を、太郎兵衛と千熊丸はまぶしそうに見上げた。
主家が滅んだ後の又兵衛は天下に見聞を広めて名を揚げようと播磨を後にしていたのである。そして四国を訪れるやその武勇を見込まれ、秀久の馬廻り衆に加えられていた。
「いいな、太郎兵衛たちは。これから海を渡るのだろう?」
心底羨ましそうな千熊丸の言葉にどう返していいかわからず、彼はただ黙って頷いた。
「俺も行きたかった」
千熊丸は結局、九州入りを許されなかった。吉成と父が話している所に踏み込んでまでの願いは、叱りつけられただけで終わった。散々に折檻されたものの、そのあまりの願いぶりに元親もやや折れて、四国を出るところまではついてきてよいと許したのである。
「熊の相手を頼む。あと、無茶をしようとしたら止めてくれ」
と元親は太郎兵衛に秘かに頼んでいた。
「無茶?」
「熊は向こう見ずなところがあってな。先だって広間に来た時の姿を見ただろう。こうと思うと周りが見えなくなるのだ。果敢なのはいい。だがあれで戦場に出ては真っ先に死ぬ」
それが戦に連れて行かない理由だ、と元親は述べた。
「せめて雄の重厚さがあればな」
ため息をつく。元親の長子である信親は、太郎兵衛から見ても圧倒される迫力があった。千熊丸がその顔を見ただけで動けなくなるのも理解できた。
「太郎兵衛よ、お前を小三次どのが連れ歩いている理由が、先日の一件でよくわかった。熊の奴が広間に走り込んで見苦しいさまを示したというのに、全く動じた様子も見せなかったな。それに聞けば、時に熊の遊び相手もしてくれているというではないか」
「ええ、まあ……」
太郎兵衛は微妙な顔をした。千熊丸は太郎兵衛より三つ年上であったが、尋常ではないほどに懐かれて、やや辟易していたのである。
やれ槍の修行をしよう、釣りをしよう、相撲をとろう、と毎日のように訪れては連れ回される。確かに、太郎兵衛も土佐に来てから暇ではある。鍛えてくれる九左衛門は大坂だし、石合戦をする知り合いもいない。又兵衛もさすがに毎日は遊んでくれない。最初は嬉しかったが、あまりの深情けに面倒くさくなってきた。
「ううむ、やはりそういう顔をされるのだな。熊は加減ができぬ故に友も少ない。俺が四国の覇者を目指して周囲を切り取ったために、同格の友というのもいなかったのだ」
頼む頼む、と大きな体を折り曲げるようにして元親は太郎兵衛に遊び相手を依頼した。結局、土佐から伊予まで来る道中でも、千熊丸はいつも太郎兵衛と轡を並べてきては側を離れようとしない。
吉成は、
「うまくお付き合いしていろ」
と言ったきり何を指示するわけでもない。この日も朝飯を食い終わったのを見計らうように、遊びに行こう、とお誘いが来たのである。
「どこへ行くんですか」
「山だ」
千熊丸は松山の街から西に見える小高い山を指した。
「あそこに登れば豊後が見えるかもしれない」
「そんなに近いのですか」
千熊丸は名前の通り、熊のように強く、大きかった。又兵衛には敵わぬまでも、流石は土佐侍従の子だなと太郎兵衛も感心するほどだ。脚も速く、馬丁として父の馬に徒歩で従っていた太郎兵衛もついていくのがやっとである。
松山の街を抜けて西にそびえる山並みを目指す。主峰の弁天山を中心に、垣生山、そして津田山と三つの小山が南北に連なっており、垣生山にはかつて土豪の埴生氏が城を築いていた。河野通直に従って秀吉に抵抗する姿勢を見せていたが、降伏して城を差し出している。今の城内にはわずかな警備兵以外は入っていない。
ところどころに兵は立っているが、黄母衣衆の吉成の子と、土佐侍従の子の顔を知らぬ者はおらず、頂への道を行くに何の支障もなかった。
瞬く間に山頂へたどりつくと、そこには出城の跡があった。埴生山城が羽柴方に引き渡された後、出城の類は全て破却された。弁天山は三山の中でももっとも高く、出城と物見櫓が設けられていたらしい。
その跡に立つと、西に広がる大海原が見えた。西から吹きつける海風は、温かな伊予でも秋が深まっていることを感じさせた。
「あれが豊後かな」
東北の方角に大きな島が見える。太郎兵衛もそうかな、と思ったが二十里先の九州があれほど大きく見えるのも妙な気がした。
「周防の島ではないでしょうか。豊後は真西の方角のはずだし、もっと遠いです」
「そうか」
千熊丸はさして気にする様子もなく、西の海を眺めている。
「この先で島津と大友が激しく戦っているのだな。一度でいいから、そのような戦場に身を置いてみたいものだ」
憧れを隠さず、千熊丸は呟いた。
「大変なところですよ」
太郎兵衛も父について、何度か戦場を通った。首を切り取られた死体、鉛玉で穴のあいた体、もげた腕などが転がる戦場は決して華々しいだけの場所ではない。だが太郎兵衛はそこに憧れ、千熊丸と同じように父について行きたいと願ったものだ。だから彼はどんなにうっとうしく思おうと、千熊丸を嫌いにはなれない。
「太郎兵衛は首を挙げたか」
「いえ……」
吉成は太郎兵衛に、戦場で槍をふるうことを許さなかった。矢玉が届く場所にいることも許さない。戦場ではあくまでも半人前の扱いしかされていないのである。父の危急を印地打ちで救ったことはあったが、あくまでも特別な例であった。
「俺も父上の四国切り取りに間に合っていれば。兄上のように武名を高められたものを」
口惜しそうにくちびるを噛む。千雄丸信親は、仙石秀久を敗退させた時に先鋒に立って敵方の侍大将の首をいくつか挙げた。それによって土佐の一領具足たちの尊敬を受けたのが羨ましくて仕方ない、と千熊丸は隠さず言った。
「だから俺も戦に出たい。なあ太郎兵衛、お前の従者でいいから連れて行ってくれよ」
伊予に入ってから、毎日のようにこうして懇願されていた。だが、そんなことはできるはずもない。
「土佐侍従さまに叱られるようなことはするな、と父に厳しく言われているので」
「そうか……」
寂しげに千熊丸は目を伏せた。讚岐から軍船が繋がれて回航してきているのが見えた。数も多く、讚岐高松から伊予松山までは結構な距離があり、その作業はなかなか進まない。
「七月のうちに豊後へ渡るのは難しいそうです」
千熊丸は太郎兵衛の言葉を聞くと、嬉しげにも悲しげにも見える、複雑な表情を浮かべた。
「なあ太郎兵衛。俺たちで船を一艘盗んでさ、先に豊後へ渡ってしまわないか? そうすれば一番槍は俺たちになるじゃないか」
とんでもないことを言いだす、と太郎兵衛は驚いた。
「俺は仙石どのよりは海を知っているぞ」
「確かにそうでしょうけれど」
土佐に生まれ育った千熊丸は確かに海に詳しかった。釣りに出ても、太郎兵衛が知らない潮の流れや魚の多く集まる場所を見極めて、大物を上げている。
「でも駄目ですよ」
「どうして!」
千熊丸はふと思いついた一番槍の空想に夢中になっているようであった。だが太郎兵衛は、千熊丸に無茶をさせぬよう元親にくれぐれも頼まれている。
「俺が何かをしようとすると皆が止める。名を揚げようと鍛え、それを戦場で発揮するのがそんなに悪いことなのか。俺はただ、一人前に戦えることを土佐に、天下に示したいだけなんだ」
太郎兵衛の肩を掴んで揺する。太郎兵衛は千熊丸の瞳が異様な光を放っていて少し怖くなった。だが一方で、このような男に見覚えがあるような気がした。
「又兵衛に似てる……」
と思わず口に出していた。
「又兵衛? ああ、仙石どのの馬廻り衆か。嫌いじゃない」
黒田の若君に従って長浜にやってきていた青年は、千熊丸よりも年長であったが、大柄なことと戦への想いが強いことでは同じだった。無茶に付き合わせるところも、よく似ていた。だがあれから四年経ち、太郎兵衛は少し成長している。
「千熊丸さまと一緒に海に出ることはできません」
きっぱり断れるようになっていた。
「じゃあ俺一人でも行く!」
肩をいからせて山を駆け下りていく千熊丸を、太郎兵衛は追わなかった。軍船は一人で操れるようなものではない。水軍の兵も長宗我部の若君が命じたところで、一隻を先に行かせるとは思えなかった。
七
放っておけばいいや、と山をゆっくりと下りた太郎兵衛は、吉成に呼ばれて碁の相手をさせられていた。吉成には趣味らしきものがなかったが、大坂に来てから覚えたらしく、太郎兵衛にも教え込んでいる。
敵を囲み、石を得ていくこの遊戯に吉成は熱中していた。だが、その腕は覚えたばかりの太郎兵衛にも負ける程度のものであった。
「ううむ……」
吉成は難しい顔で唸っている。
五局に一局は、熱戦の末に太郎兵衛が勝つ。彼からすると、父に勝てる唯一のことなので呼ばれても嫌な気はしない。時に顔を紅潮させたり、その手は待てなどと口にする父の姿は新鮮であった。
いつも有無を言わさぬ父が、碁を打っている時だけは、対等に扱ってくれるのが不思議ではある。今回も父の地は悪く、敗勢が濃い。このまま終わるかな、と思っていたところに、宿に使っていた寺の戸が激しく叩かれた。
吉成に促されて様子を見に行くと、谷忠澄が青い顔をして立っている。
「千熊丸さまがこちらに立ち寄られていないか」
「いえ、昼までは一緒にいましたが」
夜になっても陣屋に帰ってこないというのである。太郎兵衛は昼に弁天山で話したことを思い出して、言うべきかどうか迷った。
「昼に別れてどうしたのだ」
父が後ろに立っている。
「ありていに申せ」
碁石を打っている時の楽しげな気配とは違う、務めを果たしている時の厳しい声である。太郎兵衛は千熊丸が話していたことを忠澄に告げた。黄昏時であたりは暗くなりつつあったが、忠澄の表情が見る間に険しくなっていくのがわかった。
「先ほど、垣生の漁民から訴えがあったのです。小船が一艘、何者かに盗まれたとか」
「小船? その程度ならわざわざ本陣に訴え出てこなくとも」
吉成は首を傾げるが、小船を漕いで行ったのが誰か、明らかだった。
「侍装束を着た子供が一人、止めるのも聞かずに西へと漕ぎ出していったそうです。さすがにそのような愚かな真似はなさるまいと高をくくっていたのですが、太郎兵衛の話から考えると千熊丸さまに間違いなさそうですな」
うんざりした表情で肩を落とすと、忠澄は帰ろうとした。
「お待ちを」
吉成が呼び止める。
「こやつの責めでもあります」
と太郎兵衛を指して言ったものだから、彼は仰天した。
「土佐さまに千熊丸さまのことを頼まれておきながら、山を下りるのを追わなかった。これでは務めを果たしたとは言えません」
「いや、それは……」
忠澄は言いかけるが、吉成は太郎兵衛の襟がみを掴んで突き出す。
「千熊丸さまをお捜しの際は、こやつも存分にお使い下さい」
そう言って、寺の中へ引っ込んでしまった。太郎兵衛は呆然としたが、忠澄の困り果てた顔を見て、力になることに決めた。
「一緒に捜しに行きます」
「お前には悪いことをしたなぁ」
根が善人らしい家老は、太郎兵衛に詫びた。確かに迷惑なことではあったが、太郎兵衛にはおそらく大丈夫だろうという漠然とした自信があった。
「千熊丸さま、あまりよくお考えではなかったようですから。間もなく帰ってきますよ」
「わしもそう思う。ただ、来島どのも言っていたがこの辺りの海は流れが入り組んでいて、漕ぐのも難しい」
忠澄はそれでも心配なようであった。
「土佐の人間には、伊予の海はわからない。お国柄が違うように、海も所を変えれば顔が変わるのだ。その程度のことがわからぬ熊さまではないのだが、時折愚かなことをなさる」
ため息とともに忠澄は首を振る。
浜辺に着くと、既に数十人の兵が出て盛んに篝火が焚かれていた。沖で迷っていればわかるようにしてあるのだ。忠澄が兵たちに指示を出している間、太郎兵衛もじっと海を見つめていたが、既に日は暮れきってあたりは暗い。
「なんだ、太郎兵衛も来てくれたのか」
木陰に隠れるように、元親が立っていた。
「どうしようもないたわけ者だ。実に迷惑なことだろう」
怒っているが、兵たちの先頭に立つわけでもなく、どこかしょんぼりとしている。大きな体が幾分縮んで見えた。
「何を焦っているのか。時が来ればいくらでも名を揚げる機会などある。どこぞで土を耕している百姓や名もなき足軽でもない。敗れたりとはいえ、土佐一国を安堵された俺の子なのだぞ」
そう言いつつ、視線は忙しく黒い海を往復している。どれほど篝火を焚こうと、浜辺の一隅を照らすのみだ。
「間もなく九州へ出立するというのに、余計な手間をかけさせおって。他の者たちに知れたら何とする。いい恥さらしだぞ」
「恥?」
「いけすかん仙石のやつが威張り散らそうと、俺は土佐勢の総大将だ。その息子が勝手に国元をあけて陣に居座った挙句、一人海に出て行方も知れんとは情けなくて涙も出ない」
元親の嘆きを聞いていた太郎兵衛は、
「すごいなぁ」
思わず呟いた。
「すごい? 何が」
海を見るのを止めて、元親は訊ねた。
「それほど千熊丸さまは先陣を切りたかったのですね」
「まあ、俺とて気持ちがわからんでもないが」
元親は子供を見失った親熊のようにうろうろと歩き回りながら答えた。
「だがな、戦といっても変わったのだ。熊のやつは年寄りから昔の戦の話を聞いて、さぞかし華やかなものを思い浮かべているのだろうが、今や様変わりした」
今の戦は種子島を激しく打ち合い、怯んだ方が大抵負けである。
「昔のように名乗りを上げて相手に槍をつけ、衆人環視の中で功を立てるというのは難しいのだ。熊のやつも本当に武名を揚げたいのなら、徳川三河守の帷幕か関白さまの側にいて、彼らが何をしているか見てくればいいのだ」
元親の言葉には納得ができなかった。槍一筋で叩き上げた七本槍の面々はまだ年若いというのに、何千石もの知行を与えられ、戦場の先頭にいた仙石秀久は今や十万石の大名である。
「それは違うぞ」
きっぱりとした口調で元親は否定した。
「そんな時代はいつまでも続かん。関白さまは仙石や七本槍を大切にしているように見えるだろうが、本当に重用されているのは彼らではない。石田三成や前田玄以、小西行長といった連中だ。槍働きだけではない。関白さまの意を汲んで謀を立て、策を献じることにかけても他を圧している。我らも関白さまに何か申し上げる時は、頭を下げてその力を借りなければならない」
だがやはり、太郎兵衛には理解できなかった。武士の価値は石高と強さだと、彼も幼いながらに信じていたからである。
「大体、お前の父御も大した知行もないのに、大名どもに侮られていたか」
「あ……」
太郎兵衛の誇りは、どのような大身の者でも、父に対しては慇懃に挨拶をしていたことだった。父は厳し過ぎていけすかないところもあるが、それだけの力があるのだと漠然と誇らしく思っていたものだ。
「皆が頭を下げるのは武勇ではない。小三次どのと槍を合わせたことはないが、相当のつわものだ。だが、諸将が彼を敬するのは、背中にはためく黄母衣を見ているからだ。そして黄母衣は、関白さまが本当に心を許した者でなければ背負うことはできない」
「でも父上は九州を取ったら大坂に帰らないって」
吉成は勝てば大名、という話を太郎兵衛にはしていなかった。だから、ただ九州で暮らすことになると伝えていただけだ。
「ほう」
元親は複雑な表情を浮かべた。
「それは関白さまの心遣いだ」
「どういうことですか?」
「黄母衣衆は心を許せる側近で、もう共に働いて長い。関白さまのお考えがその心身にしみ込んだ者たちを九州に配するのはおかしなことではない」
「父上は殿のお傍で働くことが好きなのに」
父がお払い箱にされるみたいで、と太郎兵衛は寂しかったのだ。
「それは違うぞ。ま、槍一筋で黄母衣をはためかせているのがいいのか、国を任せられる方がいいのかはっきりわかる。どの道、この戦では懸命に戦って関白さまの覚えをめでたくせねば、我が家の先々も心配だ。小三次どのや太郎兵衛にもしっかり名を揚げてもらうぞ」
元親は気が紛れたのか、太郎兵衛を伴って海岸へと近づいた。暗い海の向こうに、何かが漂っていることに太郎兵衛は気付く。
「土佐侍従さま、あれ」
小船が一艘、波の間に漂っているのが微かに見えた。兵たちも気付き、騒いでいる。兵に交じって働いていた来島通総とその郎党が素早く一隻の軍船を出し、見る間にその小船を回収した。元親はその手際の良さに感嘆する。
「我らも海に縁がないわけではないが、あのようにはいかぬ。海の男は侮るべからず、というがその通りだな。ともかく、熊の奴にはきつく叱り置かねばならん」
浜に上げられた小船に肩をいからせつつ近づいた元親は、中を覗きこんでしばらく絶句していたが、太郎兵衛を手招いた。
何事かと太郎兵衛が近づくと、鼾が聞こえる。舷側から中を見ると、千熊丸は大の字になって眠っていた。
「こりゃ大した武辺者だ」
来島通総が哄笑すると、兵たちも笑った。
「海の妖もこんな剛胆は食えぬと返してくれたのだろう。おい」
気配に気付いた千熊丸は目をこすりながら起き上がる。まず父の姿に驚いた彼は、
「ああ、父上に追いつかれた。一番槍が!」
と頭を抱えて嘆き、元親は大笑いと共に息子を殴り飛ばしていた。

第四章 戸次川
一
四国勢が九州に上陸するのは、中国勢に比べて随分と遅れた。軍船が揃いきるまでに時間がかかったことと、筑前での戦況がめまぐるしく変わったためである。吉成の弟たちが率いる森の手勢は中国勢と共に先に豊前入りしたとの報せがもたらされていた。
「岩屋城での攻防戦は凄まじかったようだ」
浦戸城の一角で太郎兵衛と碁を打っている時、吉成はぽつりぽつりと九州の動きを話した。吉成も準備が整わなければどうしようもない。仙石秀久は四国勢の尻を叩き続けていたが、その溝は広がる一方である。
ただ、四国軍を束ねる長宗我部元親は吉成に対し、
「四国が関白さまのために働くことは間違いない」
と保証していた。
「土佐侍従さまほどの方が言うことを、周りがとやかくせっつくべきではない」
吉成は九州に弟の権兵衛吉雄や太郎兵衛の随身である杉助左衛門たちを派して、情勢を探りつつ、渡海の機会をうかがっていた。
「岩屋城に篭った高橋紹運どの以下七百名は、十四日持ちこたえた末に全員討ち死にした」
何より太郎兵衛を驚かせたのは、岩屋城が三万もの島津軍を引き受けていたことと、城兵が一歩も退かず、何度も敵を撥ね返し続けたことであった。
「城攻めはこれがあるから恐ろしい」
「島津は弱いの?」
「一戦の勝敗のみで軍の強弱をつけてはならん。確かに、岩屋城を落とすのに手間取ったかも知れないが、薩摩から筑前までを勝ち続けている軍が弱いわけがない」
島津家中興の祖と呼ばれる貴久の跡を継いで当時の島津家を率いていたのは、義久である。彼と三人の弟たち、義弘、歳久、家久はいずれも優れた武将であった。彼らをはじめとする一門衆をはじめ、伊集院一族を筆頭とする家臣団は精強であった。その強い島津に頑強に抵抗したのが、高橋紹運と立花宗茂の親子である。
「岩屋城を落とした後、島津方は立花城に降伏を促したが、それを逆手にとって降ると見せかけ、不意討ちを仕掛けたという」
義久の家老である島津忠長の本陣に突入して散々に蹴散らし、秋月種実、秋月種長など島津に味方する諸軍へと襲いかかり次々に破った。
「これには島津方も前進するのをためらった。岩屋城をようやく抜いたと思ったら、次にもっと厄介な将が控えていたのだからな」
この時立花宗茂は十九歳である。
「千雄丸さまと近いのですね」
「おそらく話を聞いて血が滾っておられることだろう」
宗茂の武勇は既に秀吉にまで届いていた。滅亡の危機を免れた大友宗鱗はその戦いぶりを詳細に伝えていたからである。
「いずれ天下に名の轟く武者になるだろう」
吉成はそう評した。岩屋城と立花城は奮戦していたが、岩屋城と立花城の間にある宝満城が陥落し、宗茂の命運もここまでかと思われた。
しかし、下関まで軍を進めていた中国勢がついに九州への上陸を開始したのである。天正十四年八月二十六日、毛利勢の先鋒が小倉に上陸した。
毛利輝元が安芸、引退していたがこの戦のために復帰した吉川元春が出雲、そして小早川隆景が四国勢と合流して伊予から九州へと向かうこととなっていたのである。これには島津も足を止めざるを得なくなった。
吉成は相変わらず、地を作るのが下手だった。
渡海を待っている間は暇な時間が多いので、吉成は太郎兵衛に碁の相手をさせる回数が増えていた。
千熊丸は結局、土佐へ帰されてしまった。一人で速吸瀬戸を越えようとした蛮勇は瞬く間に噂となって軍中に広まり、その稚気をあざ笑う者と称賛する者が相半ばした。
「人の口に戸は立てられません」
土佐へ送り返すことを決断するよう促したのは、吉成であった。
「土佐侍従さまは、どこかで千熊丸さまを豊後へ連れて行きたいというお気持ちもあったようだ。だがそれでは収まらぬ」
もともと勝手についてきている上に、噂の的になるような行いをしてしまったのでは示しがつかない。
「千熊丸さまはこれからのお人だ。ここは国に帰り、己をよく省みればよいのだ」
吉成は千熊丸が海に出たこと自体は責めなかった。仙石秀久は鬼の首でもとったように嘲笑したが、
「権兵衛が昔やらかした失態を一つ二つ披露してやったら黙ったよ」
「どんな?」
「女がらみだが。ともかく、他人を嘲る奴はいつか笑われるか、笑われていた奴だ。お前も人の行いを見てそれが奇妙なものでも、笑う前にまず考えろ」
「笑ったりはしません。俺だって千熊丸さまと同じようなことをしたし……」
戦場に憧れて、又兵衛と山崎の合戦を覗きに行ったものだ。
「あの時、お前は世間の者たちに笑われていた。俺も笑われた」
「え、そうなんですか……」
彼はむしろ、子供の世界では英雄であった。戦場を知らない者が多い中で、天下が転がる瞬間を見たと思っていた。山崎の合戦で勝った秀吉は、小牧長湫で敗れても天下を失わなかった。一度転がり出した天下の上で舞う秀吉を、父と共に仰ぎみている心地すらしていたのに、笑われていたとは意外だった。
「どのように考えていようが、無茶しているように見えればあざ笑うのが大人というものだ。だからあの後、俺はお前を勤めに連れて行き、馬丁として使ったのだ。笑わば笑え。こやつはもう働ける、と示さねばならんかったからな」
何度か黄母衣衆の従者として使っているうちに、嘲笑は止んだという。
「相手の立場が変われば態度も変わる。それも大人というものだ。あとは土佐侍従さまと千熊丸さまが、嘲りをどう跳ね返していくかお考えになればいい」
気付くと、地が逆転していた。
「他のことを考えていたから、隙を衝かれるのだ」
久々に息子に快勝した吉成は、満足げに立ち上がる。
「そろそろ出立の用意をしろ。九州では我らも奔走せねばならんぞ」
松山の街には陣触れの声が響き、甲冑の触れ合う音があちこちから聞こえる。吉成も黄母衣の正装で元親の本陣に加わる。その従者という扱いで太郎兵衛もつき従った。
鉄砲、槍、弓隊に続いて騎馬武者たちが整然と軍船へと乗り込み、西へと出陣していく。仙石、長宗我部、小早川の旗指物がはためく中を先導するのは来島村上水軍の面々だ。
関船と小早の大群を目にして、太郎兵衛は感嘆のため息を漏らした。
元親が座するのは軍の中で唯一である安宅船である。もともと信長が石山本願寺を攻める際に造らせたもので、そのうちの一隻が来島通総に与えられており、四国総大将の御座船として使われている。
「気を抜くな。渦が出たらすぐに知らせろ」
東西に細長い三崎半島を右に見ながら、船団は西へと進む。既にこのあたりの水軍衆は秀吉に帰順しており、襲われる心配はない。だが通総の表情は緊張していた。船乗りたちからもいつもの陽気さは消え、じっと海を見つめている。
「速吸の瀬戸はそれほど恐ろしいものなのか」
吉成も元親と信親親子も、四国の諸将とは微妙な距離をとっている軍監の仙石秀久も甲板に出て水軍衆の動きを見守っている。
「何故俺が気乗りしなかったのかわかるよ」
通総が険しい表情で言う。その言葉通り、三崎半島の先端、佐田岬を過ぎたあたりから、海の様相が一変した。
「父上、海の中に川が」
信親が指さす。それまで静かだった瀬戸内の海は白波の立つほどに荒れ始めている。陽光ふりそそぐ晩秋の好天は変わらないというのに、船底の下に嵐が襲いかかったように船が揺れ始めていた。
太郎兵衛は気持ち悪くなり、舷側から激しく戻してしまう。仙石秀久も隣でうずくまりながら青い顔をしていた。
「馬ならどれだけ乗っていても平気なのだがな」
太郎兵衛に言うともなく、言い訳を口にしている。
吐くだけ吐いて船端に寄りかかり、吉成が言っていたように遠くを見ようと試みる。海はめまぐるしく表情を変えている。凪いだと思えば波立ち、波立った一角に川のような流れが出来ている。
「渦です!」
帆柱の上から見張っていた水軍衆が叫ぶ。左前方に、海がわずかにくぼんでいるように見える場所があった。
「皆に伝えよ!」
通総が船を進ませるべき針路を各船に伝えさせる。波と潮流を見て即座に判断し、帆と舵を操って巨大な鉄甲船を進ませる連携は見事であった。
速吸瀬戸の難所を抜け、いよいよ船団の前には九州の海岸線がはっきりと見えるようになってきた。太郎兵衛は豊後の緑が、かつていた姫路や土佐よりも、随分と濃いような気がしていた。
「太郎兵衛、しっかり働けよ」
父がこのように言うのは初めてだった。驚きつつも、太郎兵衛は嬉しさを抑えきれなかった。
二
豊後に入った四国勢が命じられたのは、南と西から島津に圧力をかけられていた大友宗鱗の救援である。彼の居城は大分の府内館と、臼杵の丹生島城にあったが、臼杵の南にある、大友の有力家臣である佐伯惟定は島津の猛攻に頑強に抵抗していた。
佐伯の街を見下ろす栂牟礼山に築いた城を中心に多くの砦を築いて要塞とすると、島津軍の数度にわたる攻撃を弾き返したのである。
島津方の豊後方面攻略の総大将は、戦上手で知られる島津家久である。彼は佐伯を攻略するのが困難だと見るや、すぐさま道を変えた。
当初、島津軍は海岸線に沿って北上し、佐伯、津久見、臼杵と経由して大分府内を攻略する予定であった。だが、臼杵と津久見を結ぶ線を捨てて山中を抜け、戸次庄の鶴賀城へと迫ったのである。
戸次庄は、大分府内への南からの入り口となる要衝であり、臼杵など豊後各地へ至る要にあたる土地でもある。島津軍がここに迫った時、戸次庄にある鶴賀城をわずか七百の手勢で守っていたのは、利光宗魚であった。
「援軍はしばしお待ちください」
四国の諸将が驚いたことに、宗魚は府内にそう使いを送ってきていた。この時、大友宗鱗は臼杵を守り、子の義統が四国勢と共に府内にいた。
「三万もの大軍を退けることなど無理だ」
仙石秀久は、あくまでも援軍を差し向けるべきだと主張する。
「宗魚がいらないと申しているのですから」
大友の若君は、戦装束が似合わない男だった。軍議の席でもぼんやりとしていて、口を開けば茶の湯や歌のことなど戦にはまるで関係のないことばかり言う。それでいて、秀久が救援をというとこのように拒む。元親が、
「では宗魚どのを府内へ退かせましょう。勇者をこのまま犬死させるわけにはいかぬ」
と勧めてみると、
「助けなければ」
などと口にする。これには元親も秀久も閉口した。
「戦のことは我らで進めよう」
という点では元親と秀久は一致した。臼杵との連絡は戸次庄が戦場になっているためうまくいかない。府内は府内で守らねばならなかった。
この時、豊後以外の情勢は秀吉方の有利に働いていた。筑前では立花宗茂らの奮戦によって島津の進撃は止まり、毛利軍の主力と共に黒田孝高が小倉に上陸し、反撃と調略を盛んに行っていた。だが、まだ豊後まで軍を送る余裕はない。秀吉の意向を受けた黒田孝高は府内に使いを送ってきて、四国勢は府内で篭城戦を行うよう勧めていた。
これに焦っていたのが仙石秀久である。
「ぼやぼやしていると何もしないまま九州の戦が終わってしまうぞ。すぐさま兵を出して島津を押し返すべきだ」
秀久の意見に、讚岐の十河存保が同調した。
「我らはただでさえ、中国勢に遅れている。このままでは関白さまのお叱りを蒙ることは間違いない。すぐさま鶴賀城へ全軍を送るべきである」
と続けた。
「まずは豊後の地を知ってからだ」
元親は土地勘がないことを心配していた。もちろん、大友方の協力を得て地勢を理解しつつある。だが、知らない土地で伏兵に遭えば逃げ場もわからず壊滅する恐れがあった。
「島津とて知らないはずだ。いつまでも待つわけにはいかない」
「それに兵数に差がありすぎる」
島津は五万と称して軍を動かしていた。四国勢のうち、府内館を守っているのは六千あまりである。一万近くの軍勢で九州に上陸してはいたが、伊予の三千は海伝いに臼杵へと向かっていた。
「寡兵で戦う時は慎重でなければならん」
「そういう土佐侍従どのはたった四万で関白さま十万の兵に戦いを挑んでいたではないか」
秀久が皮肉を込めて言うと、
「それは戦場が四国だったからだ。よく知る土地で、他所から兵を迎え撃つのは寡兵もってしても足る。島津は豊後を知らないといっても、降った国人諸将を先導に使っているはずだ。我らと同じかそれ以上は知っているだろう」
秀久と元親は歩み寄る気配を見せない。
「では鶴賀城の勇者たちを見殺しにするのか」
「彼らは岩屋城と立花城の戦いを聞いているはずだ」
「だからといって全滅戦をさせるわけにはいかん」
秀久は鶴賀城を守る利光宗魚の意向を無視してでも、兵を出すべきであると譲らない。
「義のないところに勝ちはない」
「義も勝ちも、生き残ってこそである」
秀久は正論で押したが、元親は冷静に返す。
「土佐侍従ともあろうお人が臆したか」
睨み合いとなったものの、結局は鶴賀城の情勢を見ながら軍を動かすこととなった。城を守る宗魚に策があった場合、下手に足を引っ張ってはならない。ひとまず、そういう結論に落ち着いた。
利光宗魚は、助けは要らないと豪語しただけの戦いぶりを見せた。鶴賀城は大野川(戸次川)の東岸にあり、豊後府内へと至る街道を見下ろせる位置にある。川の西岸は急な山で、軍を動かすには向いていない。
この時、島津軍は佐伯での激戦などを経て兵数を減じてはいた。だがそれでも、一万余りの軍勢が城を囲んでいる。
宗魚は急を聞いて出兵していた肥前から戻ると、三段構えの山城に立てこもって島津方を迎え撃った。激しく銃を撃ちかけてくる間は息をひそめ、攻め手が構えを破ろうと踏み込んでくるところを、数少ない銃で反撃していたのである。
木の虚がどこにあるかすら知っている守備兵たちは、神出鬼没に現れては島津陣をかき乱した。十一月二十六日の夜半になって宗魚はそれまで温めていた秘策を実行に移すことにした。
家久本陣への斬り込みである。この策を実現させるためには、相手よりも圧倒的に寡兵で侮らせなければならず、思わぬ抵抗を見せて焦らせなければならない。
そこに隙が現れるのを待つわけだから、四国勢などに出てこられては邪魔なのだ。宗魚はきれいに禿げ上がった頭をゆっくりと叩きながらその時を待った。
鶴賀城の三段構えは既に二段までが破られて本丸が残るのみだ。わずか七百の兵で三万の島津軍を退けた岩屋城と立花城の評判は、豊後まで聞こえていた。
「同じ大友家中の我らに出来ぬことはない。その上をいくぞ」
宗魚は兵たちを励ましていた。甲冑が緩く見えるほどに小柄で痩せた男だった。だが、大声でよく笑い、その声が山のどこにいても聞こえるほどの明るさを放っていた。彼の姿を見れば、兵たちはしばし恐怖を忘れた。
岩屋城は全滅し、宝満城は落城し、立花城は耐えきった。三城あって一つしか残らなかった、ともいえる。宗魚は鶴賀の一城で三城の働きをすると豪語したのである。
「やってやろうや」
島津の大軍を前にした時から、宗魚は一度たりとも怖れを見せたことはなかった。城の兵は最初頭がおかしくなったのかと訝しんだが、その指揮ぶりを見て考えを改めた。この男についていけば、たとえどれほどの大軍を前にしても勝てる。そう信じるに至った。
城には宗魚の弟の豪永と息子の統久が共に篭っていた。彼ら二人だけは、城主の様子が尋常でないことに気付いていた。いつも穏やかな笑みを浮かべ、銃弾ですら恐れず指揮を下す姿が、常とはあまりに違っていた。
「大丈夫ですか」
二人だけになった時に、豪永は兄に訊ねた。
「何がだ」
微笑を含んだまま、宗魚は訊ねる。
「最近の兄上は鬼に見えますよ」
「坊主らしいことを言うではないか」
豪永は若くに出家して府内館近くの寺で修行していた。島津軍に襲われている故郷を救うと共に、兄の危急を助けるべく城へと入っていた。
「そういえば、義姉上はどうされたのです。甥の太兵衛の姿も見ない。府内へ逃れたと仰っていましたが、見なかった。城には統久しかいないではありませんか」
豪永は、兄の顔に影が差したことに気付いた。
「何があったのです?」
宗魚は立ち上がり、豪永を本丸の背後にあるごく小さな庭へと誘った。庭といっても、松が数本植えられているだけの狭く小さなものだ。
「ここにいる」
宗魚が指した先には、小さな土饅頭が二つ並んでいた。
「島津の先手が襲った際に、妻は他の者を守って先に行かせた。そして自分たちだけが逃げ遅れたのだ」
「俺が仇を……」
怒りを露わにして言いかける豪永の肩に、宗魚は優しく手を置いた。
「妻が何をしようとしたか、俺はずっと考えていた。己の命を賭してまで、城兵たちの家族を守ろうとした。では俺が何をすべきか。それは城を守りきることだ。違うか」
豪永は無念の涙を流す。だが、宗魚の穏やかな表情は変わらなかった。
「この城を守るためには、家久の首を挙げて島津の気勢を挫いてしまわねばならぬ。俺はこの未明に城を出て家久に槍をつけてくる。その間、城を守っていてくれ」
兄は死ぬつもりなのか、と豪永は宗魚を見つめる。
「生きるさ。でないと誰が供養してやるんだ」
そう言って、宗魚は本丸の方へと戻っていった。
三
「鶴賀城へ行ってこい」
太郎兵衛が吉成に命じられたのは、宗魚が夜討ちを敢行する二日前のことであった。
「大友御曹司と四国勢は、存分に宗魚どのの働きを見届けさせていただく。そう伝えてくるのだ」
命じられて、太郎兵衛は武者ぶるいをした。前線への使者を命じられるのはこれが初めてのことである。
「そしてこう付け加えよ。鶴賀城が危うくなれば、即刻府内に落ちてこられるように。城にこもる全ての者を受け入れる用意がある、とな」
承りました、と一礼して太郎兵衛は府内館を出る。府内では島津の襲来に備えて、民たちが避難を始めている。府内の城は、守護である大友氏が暮らす大友氏館と、南部にある防衛拠点の上原館がある。
豊後の国衙は北に海を望む地形からして、南に守りの重点が置かれていた。大友義統をはじめ、豊後勢と四国勢は上原館に詰めており、太郎兵衛もそこから出立している。
大友義統は町から避難する民たちを、高崎山城に収めるよう布告を出していた。高崎山は府内の西北に聳える独立峰で、山城が築かれている。府内が守りがたしと見ればそこで戦うよう、義統は宗鱗から命じられていた。
太郎兵衛は徒歩である。
鶴賀城は島津に包囲されていると考えられ、そこに騎馬で行くことはできない。その服装も、地元の百姓の子から借りたものになっていた。
「島津に捕えられたら?」
「何をされても口を開くな。もしそれができないなら、自ら命を絶て」
吉成は厳かに命じていた。捕まったら死ね、という父の言葉に、島津の軍はすぐ近くにいることを実感する。だが、不思議と恐怖はなかった。戦の真っただ中にようやく足を踏み入れられる喜びの方が大きかった。
府内から南へと進むと、大野川を挟みこむように山並みが聳えている。その間の谷間が戸次庄となる。
そこから先には十字の旗印が見える。島津の本陣が今にも府内に向けて押し寄せてきそうな勢いである。だが、思ったよりも少ないと太郎兵衛は感じた。海を渡った四国勢とさして変わらない。
「三万はいると聞いていたのに……」
一万程のように見える。残りの二万が山を迂回して府内へ突入してくるのでは、と怖くなったが、それよりもまずは使者の任を果たさねばならない。彼は府内で聞いていた通り、島津軍で充満する日向街道から外れて石鎚神社のある側道の方へと進んでいった。
道は神社で行き止まりになっている。だが拝殿の奥に、神主が山に参拝するさいの細い道があることを聞いていた。この道をたどると、鶴賀城の真下に出るという。
太郎兵衛は周囲を警戒しながら急な山道を進み、二度ほど道を見失った末にようやく尾根筋へと向かう道を見つけた。だがそこで、何者かの気配を感じて太郎兵衛は動きを止めた。
木立の中を縫うように、一つの影が山を登っている。太郎兵衛は悟られぬよう距離をとり、その後をつけた。粗末な杣人姿で敵か味方かは判然としない。だが人目を気にするように、何度か足を止めて周囲の気配を探っているようでもあった。
山肌は急峻さを増し、そして木立の向こうに微かに曲輪が見えてきた。土づくりではあるが、堅牢そうな造りなのが遠目でもわかる。
男は何やら指を前に出し、寸法を測っていた。どうやら島津の忍びの類らしい、と太郎兵衛は緊張した。城まではまだ一町ほどはありそうだ。このままやり過ごすかどうか迷っていたその時、耳をつんざく音がして太郎兵衛は慌てて身を伏せた。
忍びらしき男は顔の半ばを吹き飛ばされてしばらくふらついていたが、やがて仰向けに倒れた。狙って当てたのであれば、大した腕だと太郎兵衛は感心した。
この鉄砲に狙われるとまずい。太郎兵衛は身を伏せ、土塀が見えるところまで何とか近づくと、銃口がじっとこちらを見ていることに気付いた。
太郎兵衛は敢えて身をさらし、
「府内より使者として参りました、関白羽柴筑前守が黄母衣衆、森小三次吉成が子、森太郎兵衛にございます」
と名乗った。
銃手はわずかに顔をのぞかせ、使者という者が幼い子供であることに戸惑った表情を浮かべたが、太郎兵衛も先ほどの鉄砲名人が同じ年頃の子どもだと知って驚いていた。
やがて僧形に甲冑を身に付けたいかつい男が出てきて太郎兵衛を曲輪の中に招き入れた。
「利光豪永だ。使者の任、大儀である」
そう挨拶した後、
「すぐに兄上に会わせよう」
と豪永は本丸へ至るほとんど崖といってもよい山肌をよじ登っていった。
「石垣を積むような銭もないのでな」
豪永は腕一本で岩からぶら下がりながら微かに笑みを浮かべる。
「この城を落とすのは島津三万といえども、そう簡単にはいかない」
「三万もの全軍はいないように見えました」
二人にも、他の地域での戦闘の詳細まではわからない。
「戦場はここだけではない。臼杵の宗麟さまのところも攻められているだろうし、西の肥前でも戦があるだろう。兄上は肥前に出征しているところ、留守を襲われたのだからな。島津は諸方に軍を分けているのかもしれん。ま、どちらにしても島津の大軍がいることには変わりない」
本丸は頑丈そうな柵と矢倉で守られてはいるが、ごく粗末な山城だ。安土や大坂の城を知る太郎兵衛からすると、出城の一つ程度にしか見えない。途中までは深い木立と急峻な山肌で周囲が見えなかったが、城まで登ると山の全容と島津の大軍が明らかになった。
本丸から東に延びる尾根筋に沿って二の丸、三の丸が設けられ、北と南、西の三方には小さいながらも曲輪が城を守っている。
「粗末だが、使いでのいい城なんだぞ」
と豪永は得意げに言う。やがて本丸の門が開き、館の奥に通された太郎兵衛は城主の利光宗魚に目通りした。
「おお、随分と若い使者が来たものだ」
城主の宗魚も、僧形であった。だが、まるで親しい友が遊びに来たかのような穏やかな笑みを浮かべ、甲冑を身につけているわけでもない。
「して、義統さまからは何と?」
太郎兵衛が使者としての言葉を伝えると、こくりと宗魚は頷いた。
「こちらの想いを聞き届けて下さり、心より感謝申し上げる」
鶴賀城が主筋の大友義統、そして四国勢の後詰めを断わったことは、太郎兵衛も吉成から聞かされて知っている。だがその理由を訊ねるのは、仕事のうちに入っていない。
「ではこれにて失礼いたします」
初めての使者の務めが無事に済んだことに安堵し、太郎兵衛は手をつく。だが宗魚は一晩ここで泊っていけ、と勧めた。
「もう日が暮れる。お主はこのあたりの山に詳しいわけではなかろう。本丸にいて明朝府内へ帰るといい。統久もいることだしな」
「は……」
島津の大軍に囲まれているとは思えぬ、悠然とした態度である。太郎兵衛はどうにも我慢できなくなり、怖くないのですか、と訊ねてしまっていた。
「何が?」
と逆に問われる。ここで島津が、と答えると宗魚を辱めているような気がして、太郎兵衛は口ごもった。
「島津が怖いか、と申すか。そりゃ怖い」
宗魚はあっさりとそう言った。
「敵の大軍何するものぞ、といえば勇ましくていいのだろうが、生憎俺の性分には合わないのでな。川に釣りに行くような気持ちでいようと思いながら、眠れぬ夜を過ごしておるよ」
太郎兵衛は逆に拍子抜けしたような気がして、言葉が出ない。
「統久が来たようだから、奥で茶でも飲んでいくがいい。篭城中ゆえ、ろくなもてなしもできぬが、許せよ」
呼ばれて出てきた少年が先ほどの銃兵だったので、二人はあっと声を上げ、そして照れ臭そうに笑った。宗魚はそんな二人の様子を微笑んで見ていた。
四
宗魚への挨拶がすむと、太郎兵衛は統久の部屋で休むよう告げられた。大坂や姫路、土佐の話をしているうちに夜が更けて、二人は床についた。
城の周囲はしんと静まり返り、やかましいほどの虫の声だけが聞こえる。太郎兵衛は緊張が解けて、すぐさま眠りに落ちそうになったが、統久がしきりに寝返りを打つので目が醒めてしまった。
「どうしたの?」
「……何でもない」
「怖い?」
「全然」
統久は声を押し殺すようにして答えた。涙混じりの声だった。
「島津の奴ら、絶対に許さない」
統久の母と兄が城下の人々を守って討ち死にしたことを知り、太郎兵衛は言葉を失う。
「この城、必ず守ってみせる。来るやつは皆殺しだ」
泣いているのだ、ということに太郎兵衛が気付いた時には、統久は立ち上がって部屋から出て行っていた。使者として利光宗魚のもとまでたどり着くことだけを思って山道を歩いてきたが、よくよく考えると今は島津軍一万の刃の上にいるのと変わりはない。
そうと思うと自分まで震えてきた。冬深更で、しかも山の上だ。寒さもより厳しく感じられて心細い。
なかなか統久は帰ってこない。厠にでも落ちたかと心配になって部屋から出ると、太郎兵衛は異変に気付いた。
城のあちこちから甲冑の触れ合う音が聞こえる。だが、喊声が聞こえるわけでもなく、銃声もしていない。
こっそりと本丸の方へ向かうと、篝火も焚かれていないのにやはり多くの人の気配がする。柱の陰から覗くと、統久をはじめ数十人の武者が白い鉢巻をしめて居並んでいる。数人は銃を持ち、多くは弓を持ち、柄を短く切った槍を手にしている者もいた。
宗魚が手を上げると、数人の兵が静かに門を開く。闇の中へと消える兵たちの最後に、宗魚と統久が続いた。統久の横顔は、先ほどまで泣いていたとは思えないほどに、静かなものとなっている。
太郎兵衛はその後に続こうとした。統久たちがこの夜更けに武具を身につけてどこに行くのか、明らかだ。島津への夜襲をかけようとしている。だが、
「これはお前の戦ではない」
と肩を掴まれる。振り向くと、豪永が立っていた。
「使者の任を果たすのが務めであって、我らの戦に助太刀することは命じられていないはずだ。一緒に槍をとって戦うのではなく、見届けていくのが本分だろう」
そう諭され、太郎兵衛は力を抜いた。
「物見櫓があるから、そこから見ているがいい」
豪永は兄と甥が死地に赴いているというのに、随分と落ち着いて見えた。
「今の兄上には島津の兵が一万いようと、恐れるに足らぬ」
「どうしてです?」
「負けられぬ理由のある者は強い、ということだ」
「統久に聞きました」
「そうか……」
太郎兵衛を伴って豪永は物見櫓に登る。櫓は木立の上からは周囲を見渡せるが、下からは見えないように巧妙に枝葉を使って隠されていた。そこから顔を出すと、既に破られた三の構えと二の構えが無残な姿をさらしていた。
島津軍は一度退いて戸次庄の集落に陣を置き、さかんに篝火を焚いている。
「勝ちに驕っておるわ」
夜明けに近い真夜中は、奇襲にもっとも向いている刻限とはいえ、警戒も厳しいはずだ。だが、島津家久の陣には見張りの兵もそれほど立っているようには見えない。
「島津も疲れているのだ」
豪永は敵の警戒が薄い理由を、そう読み解いた。
「薩摩から激しい戦を繰り返して北上し、筑前では上方からの軍が押し返してきている。このまま府内を抜いて北上して、関白さまの精鋭を中国へ押し戻すのは至難の業だろう。勝っていても、その先に終わりが見えなければ辛いものだ」
だが俺たちは違う、と豪永は胸を張る。
「我らは大友家に恩を受け、故郷を安堵されている。この戦に勝てば、またこれまでのように暮らせる。島津のように限りなく戦っているわけではないからな。だから、この一戦に全てを賭することができるのだ」
城には数百しかいないが、この先にもつわものがいくらでも待ち構えている。筑前まで達したところで、上方の大軍に迎え撃たれる。
「それがわかっていながら、あくまでも北上を続けるあいつらも天晴な敵だ」
豪永は島津軍を称えてすら見せた。
「そろそろか。あの辺りを見ているといい」
指された辺りは、何ということもない木々に覆われた山肌だ。篝火のおかげで仄かに明るくはなっているが、重い闇が周囲を包んでいて様子がわからない。
だが、山肌がわずかにざわついたように見えた。風のせいかと思えばそうではない。波立つようにざわめいた茂みの間から、ゆっくりと姿を現したのは、白い鉢巻姿の武者たちである。
島津家久の本陣はまだ静まり返っている。城を出る時には最後に出て行った宗魚が、先頭に立っているのが見えた。大胆にも篝火のすぐ近くまで行った姿が、物見櫓からも見えたのである。
宗魚の右手がさっと上がった。喊声をあげることもなく、槍をふるって本陣へと突入する。銃声が一斉に轟いて、島津の陣は騒然となった。慌てて飛び出してくる者は銃弾と鏃の餌食となり、次々に倒されていく。
だが島津の混乱は間もなく収まった。
宗魚たちの夜襲は激しいとはいえ、島津の本隊からすればはるかに小勢である。敵軍全体を混乱させるには至らない。本陣の幔幕は燃え上がったとはいえ、家久の首を挙げたわけではない。
陣太鼓の音が響き、それを合図にしたように、島津方は整然と反撃を開始する。
「まずいな……」
豪永はくちびるを噛んだ。そして物見櫓の下に向かい、宗魚たちが山を登ってくればすぐさま収容するように命じる。
「さすがは島津家にその人ありと知られた家久だ。沖田畷で竜造寺の精鋭を破っただけのことはあるな。太郎兵衛は本丸に隠れていろ」
「ここで見ています」
「そうか。では俺たち利光一族の戦いぶりを四国の面々にお伝えできるよう、手痛く働いて来るとしようか」
豪永は不敵に笑うと、物見櫓を下りていった。
島津軍に押し詰められた宗魚であったが、慌てる様子も見せず兵たちをまとめると、銃と弓で追手を怯ませつつ後退を始めた。太郎兵衛はその悠然とした退き口から目を離せず、櫓の木組みから身を乗り出すように見つめている。
多勢で追いすがる島津兵を狭い沢に引き込んでは射すくめる。山ひだの一枚にまで精通している彼らに追いつけず、島津方は苛立っているのが手に取るようにわかり、太郎兵衛は喜んで櫓の手すりを叩いた。
だが、彼は恐ろしいことに気付いた。島津方の一隊が、既に落ちた二の構えへと回り込んでいる。焼け焦げてはいるがまだ建っている矢倉の上へと、数人の銃卒が入った。
太郎兵衛は急いで物見櫓を下り、豪永の姿を捜す。
迎撃の備えを整えていた彼は、崩壊した二の構えに回り込んだ一隊を認めると、すぐさま一隊を向かわせようとした。だが、太郎兵衛が山を登ってきた裏門の方から突如喊声が上がる。
「豪永さま、搦め手の道から島津兵が攻めのぼってきています」
「くそ、ばれたか」
しばし迷った末、豪永は兄の救援に向かわせるはずの一隊を、搦め手へと送った。
「なあに、兄上はそう簡単には死なんよ」
自分に言い聞かせるように呟いた豪永は太郎兵衛の肩に手を置く。
「しばらくは戦が激しくなるから隠れていろ。もし城門が破られるようなことがあれば、すぐさま逃げるんだ。府内から来た使者を死なせたとあっては、大友の殿に失礼だからな」
そう言うと、搦め手の方へと駆けて行った。残された太郎兵衛は懐に手を入れる。小刀一振りと丸い石が三つ、入っていた。もう一度物見櫓に登って宗魚たちを捜すと、三の構えを越えたところで猛反撃に出ていた。
敵兵の怯んだところでさっと退く采配ぶりは相変わらず見事だが、二の構えに先回りした銃卒たちには気付いていないように見えた。
太郎兵衛は島津方に備えている兵たちの間をすり抜けて柵から飛び降りると、止める声も聞かずに二の構えの背後へと走り込んだ。島津の銃卒が宗魚の背後をとり、その背後に太郎兵衛が回った形となる。
矢倉の上に顔を出している銃卒は五人。石は三つだが、三人の頭を砕けば残りの二人は逃げると考えていた。しばらく石合戦もしていないから、印地打ちがうまく決まるか自信はない。だが、やらねばならない。
銃卒の一人が銃口をわずかに下に向けて狙いを定めた。太郎兵衛も足場を確かめ、手の中に石を握る。
太郎兵衛は腕をしならせ、石を投げる。当たるかどうかを確かめもせず、次の石を手の中に握る。頭を出しているもう一人の銃卒を狙って、二つ目を投げた。
狙いをつけていた銃卒の頭が跳ねあがるが島津兵は怯まない。二発目の石が当たって兵が矢倉から落ちたところで、太郎兵衛は愕然とした。
普通であれば、二人も倒されれば他の兵は周囲を探すか、慌てて逃げてもおかしくない。だが島津の銃卒は、二人が倒されたのにもかかわらず、石が飛んできた先を探そうともせず銃を構える。
焦ったのは太郎兵衛の方であった。予想外の動きをされたことで心を乱され、三つ目の石は銃に当たっただけで兵を倒すまでには至らない。三人の銃卒がほぼ一斉に、山を上がってくる宗魚たちに向けて発砲した。
太郎兵衛の方から、宗魚たちは見えない。だが、反撃によって三人の銃卒は瞬く間に倒された。ほっと胸をなでおろして宗魚たちの方に向かおうとすると、地響きのような鬨の声が響き渡る。
島津軍が十文字の旗を押し立てて、続々と鶴賀城山を登りつつあった。太郎兵衛は急いで本丸に戻り、宗魚たちの奇襲隊と共に城内へ駆け戻る。
数人の死者は出たが、ほとんどが無事に帰ってきた。統久も膝に手をついて荒い息をついている。だが、宗魚の姿が見えない。
「統久、兄上は……」
豪永が声をかけると、統久はそのまま顔を覆い、崩れ落ちた。生還した兵たちも俯いてくちびるを噛んでいる。
「殿は、二の構えまで上がった時に敵兵に撃たれて倒れられました。俺たちは担いで行こうとしたのですが、置いて先に行けと叱りつけられ……」
一人の兵がそう報告し、太郎兵衛は目の前がぐるりと回ったような気がしてよろめいた。
やはり、印地打ちを外したせいで、宗魚は命を落とすことになってしまったのだ。人の父を殺してしまったような気がして、太郎兵衛は思わず統久と豪永の前に手をついた。
「俺がしくじったばかりに!」
と詫びる。初めての使者として鶴賀城に来て、城主を死なせてしまうとは何事か、と太郎兵衛は自分を殴りつけたかった。その願いを見抜いたかのように、大きな拳が彼の頬を打ち抜く。
目を回しながら立ち上がった太郎兵衛の前に、拳を握りしめたままの豪永が仁王立ちになっていた。
「府内からの使者にご無礼、平にご容赦願いたい。だが、言っておく。兄上は存分に戦って討たれた。誰かのせいではなく、己の心のままに戦い、志を遂げられるべく武者の道を歩いていたのだ。その道に余人が入ることは許されぬ」
太刀で斬り捨てるような厳しい声である。
太郎兵衛は己の浅はかさを悟り、俯く。宗魚は島津の大軍の本陣へと斬り込み、総大将を慌てさせた。そして鮮やかに退いて見せる途中で敵弾に当たって傷つき、味方を庇って討ち死にしたのである。その名誉に、誰も踏み込んではならないのだ。
言葉を失っている太郎兵衛を、統久が見つめていた。
「太郎兵衛の石、見たよ。見事だった」
どう応じるべきか迷う太郎兵衛の手をとった統久は、
「俺はこれから豪永叔父と共に、この城を守る」
と静かに告げた。
物見櫓からは、島津の先鋒が二の構えを越えて山肌を登ってきていると声が聞こえていた。全ての城兵が柵の銃眼から敵に狙いをつけ、弓を持った兵は次々と弦を引き絞っている。
「それが俺の務めだ。太郎兵衛の務めは、府内に帰ることにある。ここで俺たちと共に闘うことではない」
その声は太郎兵衛の耳には冷たく響いた。でも、と統久は続ける。
「太郎兵衛の助太刀、嬉しかった。単身、俺たちを助けに城を出てくれたことは忘れない。共に戦ってくれて、ありがとう。いつかこの恩を返そう」
力を篭めて太郎兵衛の手を握り締めて、離した。太郎兵衛が顔を上げると、統久は微笑んでいた。顔見知りになった城兵たちや、先ほど太郎兵衛を殴り飛ばした豪永ですら、穏やかな笑みを含んでいる。初めてまみえた時の宗魚と同じ表情であった。
「太郎兵衛、お前の道は俺たちで作ってやる。兄は存分に思いを遂げた。島津はいま、利光宗魚のいないこの城を落とそうと総がかりになっている。その背後を衝くなら今だ。府内へ帰り、我らの言葉を伝えてくれ」
豪永は鶴賀城の将兵は退かず、ここで島津軍を引き付けるから、全軍を以ってその後詰めとなることを要請する、ときっぱりとした口調で言った。
「道は石鎚神社から続く搦め手の他に、我らしか知らぬ隠された道がもう一本ある」
豪永に促されて、太郎兵衛は返書を胸に城を出る。登ってきた道にある搦め手の曲輪からは、銃声と断末魔の叫びが聞こえてくる。城方のものなのか、敵のものなのかが気になるが、振り返るな、と豪永は言う。
「さあ行け!」
背中を強く叩かれて、太郎兵衛は走り出した。初めて通る茂みに覆われた道であったが、迷うことなく駆け下りる。
道をたどると、再び社の裏手に出た。石碑を見ると丹生天満神社とある。鳥居から大野川が見えて、その先には府内の街が広がっていた。まだ島津軍の気配はなく、ほっとしつつ川を渡る。
振り返ると、戸次と府内を隔てる山並みが見える。山稜の向こうから煙が数本立ち上り、一見のどかにすら思える。だがその下では、統久や豪永が死力を尽くして城を守っているのだ。
太郎兵衛は府内館へ走った。
五
「利光宗魚さまは討ち死に。しかし弟の豪永どの、子息の統久どのが懸命に城を守って支えています。島津は足止めされ、側面から衝く好機です。今すぐ軍を動かして下さい!」
泥だらけになって帰ってきた太郎兵衛は必死に援軍を出すよう求めた。だがその報告を受けて、軍議はさらに紛糾するばかりである。
「すぐさま討って出て、島津家久の首を取るべきだ」
仙石秀久は広間の床を叩いて喚いた。
「ここで宗魚どのの死を無駄にしては、我らが海を渡ってきた意味がない。それに、戸次を破られれば府内は丸裸になる」
背後に海があり、三方が開けている府内の大友館は、守るに適さない。四国勢が詰めている上原館も城としては弱かった。
「それに使者からの報告によれば、城兵は島津の主力を引き付けてくれている。その背後を衝くのは上策である」
だが、長宗我部元親と信親親子は反対した。
「我らは寡兵であり、島津家久ともあろう者が、背後の備えを怠っているとは思えない。ここは高崎山城へと退いて堅く守り、鶴賀城で疲弊した島津方の気力を殺ぎながら臼杵の宗麟どのと兵を合わせる機をうかがうべきだ」
太郎兵衛は使者として城をつぶさに見てきた手前、軍議の末席にいた。だが、元親たちの言葉には苛立ちを覚えた。助けなければならないのは明白である。なのにどうしてこのような評定を繰り返すのか。
だから父が立ち上がった時は、ほっとした。これで統久たちは助かると思ったからである。だが、
「軍を戸次に出すべきではない」
と言った時には愕然とした。
「鶴賀城はすでに三段構えの二段までを破られ、本丸には残存の五百ほどが守るのみ。彼らはよく戦っているが、戦は広い目をもって見るべきだ。ここは土佐侍従さまの言う通り、高崎山城に退いて、敵の戦力を削るべきである。薩摩から長駆して戦い続けている島津は疲れている。戦う気力を殺ぐことこそ肝要だ。だが、利光一族の奮闘を見殺しにしてはならぬ。秘かに一隊を送り、呼吸を合わせて血路を開いて後に退く」
「それでは手ぬるい」
秀久は吉成をぐっと睨みつけ、
「土佐侍従どのと小三次の案は受け入れられぬ」
と拒んだ。
「これまでは海のこともあって遠慮していたが、戦の大事を決するとなれば、わが命に従ってもらう。関白さまに四国勢の戦いぶりやいかにと訊ねられて、ひたすら山に篭っておりましたと答えるわけにはいかん。ただでさえ、我らは中国勢に後れをとっているのだぞ。しかも、あちらは筑前一国を奪い返し、さらに南へ島津を押し返そうという勢いなのに、このまま横目で眺めているだけでよいのか」
土佐にやる気がないのなら、他の三国だけで出る、とまで秀久は言った。
「戦が終わった後、土佐侍従は怯懦にして戦意なしとご報告申し上げるが、異議を申されないようにな」
そこまで言われては、元親も返す言葉がない。軍議は戸次への出陣に決まった。諸将がそれぞれの陣へと帰っていく中、太郎兵衛は安堵と共に物足りなさも感じていた。自分の報告によって、四国勢は炎のように島津方の背後を襲い、鶴賀城を助けてくれるはずであった。
なのに、元親親子は兵を出すことに反対し、父は統久たちを助ける案は出してくれたが、城は捨てると言った。
「不服か」
むっとした顔をしている息子に、吉成は声をかけた。だが、軍議で決まったことに不服を言うことは憚られた。黙っていると、
「お前は何のために兵を出すべきだと考えた」
「統久たち、城を守る者を救うためです」
間髪容れず、太郎兵衛は答える。だが吉成はそれは間違いだ、と言う。
「我らが考えなければならないことは、小さな城を一つ守ることではなく、島津を薩摩に追い返すことだ」
「確かにそうですが……。でも、味方の奮戦を見殺しにするようでは、誰もついてきません」
「鶴賀城はもともと、我らの援軍を断った。その間に島津は戸次へと兵を入れ、こちらから攻め入るのは難しいほどの陣を築いたのだ。そこへ島津よりも兵力の少ない我らが攻めかかることは、四国勢にも大きな犠牲が出ることを意味する」
「だからといって、あれほどに奮戦している鶴賀城を見捨てていいという理由にはならないではありませんか」
と太郎兵衛は父に詰め寄る。
「お前は随分と、城内の者たちに肩入れするのだな」
「そ、それはあの戦い方を見れば誰でもそうなります」
「見るべきは城がどうなるかだけではないのだ」
吉成は甲冑を身につけ、黄母衣を羽織る。
「だが、鶴賀城は要地だし、味方の士気も大事だ。高崎山城に篭るとなれば、俺が自ら走って利光豪永以下、城を守っている者たちを脱出させる」
「見捨てないのですね」
太郎兵衛は胸を撫で下ろした。
「四国勢が後詰めに入れば、家久は備えをとらなければならない。鶴賀城は小さいとはいえ、これまで島津の我攻めにすら持ちこたえてきたのだぞ」
「城は落ちない、と?」
「おそらくな。それよりも、俺たちは己の心配をした方がいい。権兵衛の奴、功を焦り過ぎている」
吉成は鶴賀城より、功に逸っている秀久のことを気にしていた。
「あまり無茶をしなければいいのだが」
「無茶?」
「島津は剽悍だが頭のいい連中だ。俺も軍議であの程度のことは言えるが、やはり軍を実際に率いている連中の意を曲げるのは難しい」
への字にくちびるを歪ませた吉成は嘆息する。
「四国勢が健在であることが城を助けることになると気付けばいいものを。これで我らもろともに島津にやられたら、鶴賀城どころか豊後全体が危うくなるぞ。こうなっては四国勢の奮闘を祈るのみだ」
黄母衣衆の吉成には、数十人の郎党しかいない。これでは戦に出ることはかなわないので、元親の本陣近くに侍ることになる。土佐衆の気勢は今一つ上がらなかったが、それでも戦を前にして兵たちの気分は高揚しつつあった。
仔細はともかく、九州に入ってようやく戦えるのである。滞陣中やることもなく、博打に明け暮れていた兵たちは勇躍して進撃を開始した。
六
細作が見聞してきたところによると、島津は戸次から大野川を渡り、判太郷のはずれに陣を敷いていた。軍を三つにわけ、中軍を中心に両翼に陣を展開している。
それ以上の前進を許しては、府内の城下へと攻め込まれてしまう。
「ほら見たことか」
仙石秀久は得意げな表情を隠そうともしない。
「わしがこうして軍を出そうと言わなければ、我らは何もせぬまま府内の館を囲まれていたのだぞ」
長曽我部元親と森吉成は憮然として答えなかったが、十河存保も同じように誇らしげな顔であった。
「これでようやく、関白さまに功をお知らせできますな」
布陣は、秀久の軍が中央で先陣を切る。長宗我部と十河が両翼、そして小早川はその後詰めとして敵を川の向こうへと押し返すことになった。
土佐から来た一領具足たちも、戦を前に張り詰めた空気の中で押し黙っている。太郎兵衛は元親が諸将にてきぱきと指揮を下す様をじっと見つめていた。将兵と軍馬の吐く息が、一帯に白く漂っている。太郎兵衛は、ともすれば震えそうになる体に力を入れて我慢していた。
「いよいよですね」
千雄丸信親が、吉成に話しかけている。信親も一軍を率いて元親と共に戦うことになっている。全ての配置が終われば、元親に挨拶をして自軍に戻ろうという頃合いだった。
「存分に戦ってきます。ご検分ください」
信親の顔を高揚が覆っている。
「あまり気負われませんように」
じっと若武者の顔を見返していた吉成は、ただそれだけ言った。
「九州で覇を目指す島津に、かつて四国に覇を唱えた長宗我部がぶつかるのです。気負わずにおられましょうか」
「関白さまの主力はまだ畿内にとどまっています。利がなければすぐさま退かれますように」
吉成の言葉に、信親は不愉快そうな表情となった。
「戦の前に随分なことを仰る」
「これは関白さまの戦いでもなければ、土佐侍従さまの戦いでもない。権兵衛の我がままから出た戦でしかありません」
「島津は大野川を越えて陣を敷き、府内へ攻めかかる姿勢を見せています。仙石どのの発意から始まったことだとしても、今や戦うに十分な理由があり、功を立てる時だと思っております」
その横顔を、太郎兵衛は眩しげに見上げていた。その視線に気付いた信親は、
「太郎兵衛、我ら共に名を揚げる好機ぞ」
と張りのある声をかけた。太郎兵衛もその意気に当てられて大きな声で返事をすると、満足げに頷く。信親は吉成に一礼すると自陣へと戻っていった。その背中を見送っていた吉成は、
「太郎兵衛、我らは千雄丸さまにつくぞ」
そう告げた。
吉成は戦においては元親の側にいることになっている。それは、秀吉からの使者で軍監であるという立場からである。だが、それは誰に命じられたわけでもない。
「千雄丸さまは何度も戦場に出られ、存分に戦える力もある。だが、権兵衛が強引に始めた戦で万が一のことがあれば、俺は殿にも土佐侍従さまにも顔向けできぬ」
吉成は初めて、太郎兵衛に馬に跨ることと、甲冑で身を固めることを許した。これまでは馬丁扱いだから何もなく、せいぜい胴丸と鉢金だけの足軽のような格好だった。
「これが俺の初陣ですか」
「気負うことはない」
励まされているのかと思ったが、そうではない。
「ことさら初陣だからと気負うような家でもなし」
とつれない父の言葉だ。だがそれでも、太郎兵衛は嬉しかった。初めて騎馬を許され、侍として戦うことができる。そのための鍛錬はもう十分にした。
「ともかく我らは千雄丸さまの側にいて、その無事を守るのだ」
太郎兵衛は力強く頷く。土佐侍従の息子を守って戦うなど、これ以上ない名誉の務めである。鶴賀城では宗魚を目の前で死なせてしまった。次はそうはさせない、と槍を握りしめる。
「あまり己の腕を過信するなよ」
吉成の忠告に頷くが、太郎兵衛も気負っていた。
長宗我部の三千のうち、信親が率いるのは千人である。信親の軍を前衛とし、右翼の島津軍を攻める。激しい銃撃戦が始まると、あたりは濛々とした煙と火薬の匂いで覆われた。
「戦況を」
信親はひっきりなしに物見の兵を出し、状況を知りたがった。島津には膨大な数の銃があり、四国勢も秀吉から与えられた大量の銃を備えている。互いが撃ち合う銃撃の優劣は、結局はその数と用い方が左右する。
「我が軍が押しています」
銃の性能や運用については、双方ともに熟練しているといってよかった。この時期になると戦は銃卒の撃ち合いが多くなり、先に崩れた方が負ける。
「島津方が潰走を始めているようです!」
数人の物見が立て続けて報告した。
「追撃を……」
と命じかけたところを、信親の後見に付けられていた谷忠澄が止めた。
「まだ早い。策略かもしれません」
「谷どのの言う通りです。島津がこれほどあっさりと退くとは考え難い」
吉成も横から言い添える。
「それは故があるのか」
信親は普段の静かな表情を捨て、闘神のように猛って二人に詰め寄る。容貌魁偉な信親が見せる激しい戦意に谷忠澄は押されたように口ごもった。
「故はありませんが、戦には機微があります」
吉成は駆けだそうとする信親の手綱を掴んで止めようとした。
「機微とは何か! 敵の敗勢を見て攻めてこそ、機を失わないのではないか」
そう反論されて、吉成は言葉に詰まった。太郎兵衛は、敵が逃げ出しているのに追ってはならぬという父たちの言葉が理解できない。
「島津方は川を渡って敗走しています!」
続けざまに報告が来る。そして信親の表情が変わったのは、
「仙石越前守さま、敵の左翼を破って川を渡り始めております」
との報がもたらされた時である。仙石秀久ら淡路勢が敵の左側に攻めかけ、第二陣に十河存保と信親の軍勢が続いている。元親はその後詰めに入っていた。
「怖じているのなら無理にとは言わぬ。我らは敵を追い、家久の首を取る。越前守どのに後れをとるわけにはいかない」
そう言って吉成の手を振り払うと、大声で追撃を命じる。喊声を上げた長宗我部軍は戸次川に足を踏み入れ、次々に渡り始めた。
「千雄丸さまから離れるな」
吉成は太郎兵衛にそう命じると、馬を走らせようとする。
「どこへ行くんですか」
「様子を見に行くのだ。島津一の戦上手が、こうもあっさり退くのがどうしても信じがたい。何があったのか確かめねばならん」
そう言って煙と喧騒の中へと消えていった。
信親の軍の後を追って、元親の本隊も続いている。仙石秀久の軍も競うように川を渡り、戸次の集落へと入り込んでいた。島津方の逃げ足は速く、煙が晴れてきたというのにその姿がわずかにしか見えない。
「急げ!」
信親は馬の腹を蹴り、軍の先頭に立って走る。だが、目前から駆け戻ってきた吉成がその前に立ちふさがった。
「すぐに退くのです!」
「なぜ!」
「釣り野伏せ……」
と吉成が言いかけたところに、その声をかき消すほどの銃声が轟いた。太郎兵衛の視界の中で、数人の兵が次々に倒れる。銃弾が胴丸を貫く乾いた音がして、続いてあちこちで血しぶきが舞うのが見えた。
土と血の湿った香りを塗りつぶすように、糞尿の臭いが立ち込める。命を失う寸前に、人は体内にたまった排泄物を出す。戦場はいつも、その臭いが充満していた。しかしこれほど近くで、その瞬間を見たのは太郎兵衛も初めてだった。
一人の武者が槍を構え、太郎兵衛の前に突進してきた。
組み止めきれず転ばされた太郎兵衛に槍を突き出そうという武者の首筋に、矢が突き立った。
「太郎兵衛、止めを!」
矢を放った次郎九郎吉隆が叫ぶ。無我夢中でその武者の首を掻き切った。
「押せ!」
信親は敵の勢いに怯まず、銃卒を前に出して反撃を試みた。だが、集落の陰から狙撃してくる敵の姿は硝煙に隠れて定かでない。密集して川を渡ってきた長曽我部軍は格好の標的となって、次々に倒れていく。
「千雄丸さま、機は失われました」
馬を撃たれて失い、徒歩になった谷忠澄が信親を引きとめる。
「越前守どのの軍はどうなっている」
戦場は混乱し、中央から川を渡った秀久の動きは判然としない。
「島津の策が我らにだけかけられたとは思えません。島津は最初から一度退いて我らを引きこんでいるのです。即刻退かねば全滅します!」
吉成の言葉に、太郎兵衛は愕然とした。集落の向こうから、肝が凍るような鬨の声が巻き起こった。島津の本隊が整然と押し出してくる。銃火は炎の束となって襲いかかり、信親の軍は見る間に百を超える兵を失った。
「退こう……」
信親は肩を落とした。だが、忠澄に軍の指揮を命じ、自らは殿となって敵を防ぐと命じた。吉成と太郎兵衛にも先に退くよう告げるが、吉成は拒んだ。
「見届けるべき軍がそこにある以上、離れるわけにはいきません。それに千雄丸さま、あなたは存分にご検分せよと仰ったではないか。軍監が真っ先に逃げ帰って、何の面目があって殿に報告できましょうか」
驚いたように目を大きく見開くと、若武者の顔は驚くほどあどけなくなった。頷いた信親は槍を構え直す。猛烈な射撃の中、土佐の兵たちは次々に倒れていく。だが信親の本陣はじっと動きを止め、静まり返っていた。
七
十字の旗を押し立てた大軍が信親たちへと迫っている。太郎兵衛は既に、数人と槍を合わせて討ち取っていた。
首を挙げて功名としたかったが、討ち捨てにせよと命じられている。言われてみれば確かに、いちいち首を掻き切っていたのでは間に合わない。それほどの乱戦であった。
体は疲れている。いくら鍛錬を積んでいるとはいえ、一間半の馬上槍を持つ手は痺れていた。太郎兵衛は吉成や信親の強さに驚くばかりである。
二人とも面頬から脛当てに至るまで、乾いた返り血で色が変わっている。それでも押し詰めてくる敵を前に気を静め、微動だにしない。
土佐勢の鉄砲はまばらで、島津の銃声は激しい。銃の力は、太郎兵衛を心底震えあがらせた。顔面に直撃を受けると、顔の半ばは吹き飛ばされる。胴に当たれば拳より大きな穴が開いた。これまでも戦場でそのような死体を見てはきたが、目の前でそうなる姿は、やはり彼に衝撃を与えていた。
夢中で戦っているうちは平気だったが、ふと我に返るとやはり怖い。
「太郎兵衛」
気付くと、信親が轡を並べていた。
「一つ頼みたい」
土佐の軍を率いて、府内まで退く指揮をしてもらいたいと信親は言った。
「そんな……無理ですよ」
これまでは使者の、しかも馬丁や従者でしかない元服前の子供である。数百人とはいえ、土佐の戦士たちを指揮するなど、考えたこともない。
「男たるもの、いつ将となり王となるかわからない。その心構えをしておくのが戦国の武者というものだ」
信親は面頬を外した。色白の横顔は戦場にあるとは思えぬほどに柔らかな笑みを湛えている。そしてぞっとするほどに美しかった。
「これまでの戦いぶり、見事だ」
「ご覧になっていたのですね」
「目に入る限りはな。誰がどのように戦い、傷つき、倒れていったかを胸に刻み込んでいくのも、将の務めだ。ともかく、この場を預かる将としての命だ。残りの兵をまとめ、大野川を渡って府内へ戻れ」
「千雄丸さまは?」
「小三次どのと共に殿を務め、後に続くよ」
そこには土佐や府内で見せた気負いは全くなかった。太郎兵衛は引き込まれたように、承りました、と頷くほかない。満足げな表情を浮かべた信親は、腰から太刀を外し、太郎兵衛に手渡す。
「これは?」
「かつて信長さまより拝領した左文字だ」
「そんな物をいただくわけには……」
「お前は関白さまからの使者であり、俺に代わって軍を率いるのに不足はない。この左文字の太刀は長宗我部信親の魂だ。しばし預かっておいてくれ」
あれだけの乱戦を切りぬけたというのに、鞘にすら汚れ一つついていない。信親の戦いぶりがうかがえる太刀の清らかさであった。父を見ると、言う通りにせよと頷いていた。
「戦が一段落したらお返しします」
「……そうだな。では府内で」
信親の背中は大きい。土佐だけでなく、四国を背負えるだろうと見惚れてしまうような武者振りであった。太郎兵衛は左文字の太刀を握り、本陣の後ろに控える一領具足たちのもとへと向かう。
彼らの多くは傷ついていたが、爛々と目を光らせ反撃の下知を待っている。だから太郎兵衛がこれから川を渡り府内へ戻る、その指揮を執ると言い渡した時もすぐには従わなかった。
「千雄丸さまは俺にこの太刀を託された」
太郎兵衛が頭上に掲げた太刀を見て、一領具足たちはざわめいた。
「それを何故お前が持っている」
一人が訊いた。
「皆が府内へ戻るまで、俺が指揮を執るよう千雄丸さまは命じられた」
しばらく顔を見合わせていた一領具足たちは頷く。
「若君がその太刀を託すということは、お前にそれだけの値打ちがあるのだろう」
太郎兵衛は内心胸を撫で下ろす。
「で、千雄丸さまは」
「我が父と近習の方々で殿を務められる。一領具足の面々は先に退き、反撃の機を待つようにとの仰せだ」
じっと見つめてくる男たちの視線を太郎兵衛は受けきった。自分の後ろには信親が立っている。そう懸命に考え、将であろうと己に言い聞かせた。
「退くぞ!」
太郎兵衛は旗印のように太刀を掲げ、そして采配のように振る。一領具足たちは整然と大野川の流れへと身を浸し、北へと走る。既に岸まで押し出してきた島津方の銃卒が、次々と味方を射殺していく。
だが太郎兵衛も一領具足たちも振り返らず、ただ前へと進んだ。狙撃は確実であったがまばらで、信親たちが食い止めてくれていることがうかがえた。
数十人の犠牲を出しながら川を渡り終え、彼らはようやく対岸を見た。
帆掛舟の旗印が力強く揺れているところに、島津方の新納忠元軍が襲いかかっている。数で圧倒する島津方を、信親たちの殿軍は何度もはじき返していた。
「止まるな! 千雄丸さまの殿を無にしてはならない」
太郎兵衛は声を励まして命じる。あの中に父がいる、ということはなるべく考えないようにした。父がいるから、信親も無事に戻ってくるはずだと己に言い聞かせる。
府内へ戻り、上原館に入ると間もなく元親も戻ってきた。疲れてはいるが意気軒高で、太郎兵衛の顔を見て無事を喜ぶ。だが、戦況の話になるとその表情は急速に曇っていった。
八
「千雄丸が殿に、か……」
「おかげで我らは無事に府内へ帰りつくことができました」
一領具足のまとめ役となっている竹村惣衛門が元親の前に手をつく。元親はそれに頷き返しながらも、視線はじっと大野川の方へと向けられていた。だが、
「十河存保さま、討ち死に!」
「淡路勢、潰走しました!」
との報が立て続けに入るに至って、元親の顔色は青ざめていった。
「雄はどうしている」
周囲に何度も訊ねるが、物見の兵も信親の隊の様子を探ることはできない。彼のいたあたりには、既に島津の軍兵が満ちていた。
「島津の主力も川を渡り始めているようです」
「大友の若殿は!」
後詰めをしているはずの大友義統の姿はどこにもなかった。兵たちのほとんども知らなかったが、彼はわずかな供回りだけを連れてさっさと高崎山城へと逃げ込んでいた。
「大友館は守るには不利だ。高崎山城へと篭るべきか。仙石どのがいれば軍を合わせて動けるのだが」
元親が諸将と諮っているところに、
「仙石越前守さまは小倉に向けて走っているとのこと!」
との報がもたらされた。
「我らを見捨てて行くつもりか……」
元親はくちびるを噛むが如何ともしがたい。彼は信親を収容し次第、府内の港に泊めてある軍船に分乗して四国へ撤退すると将兵に命じた。
「まずは港で出港の備えを整え、殿の者たちを待とう」
不安を押し隠した表情で言い渡すと、元親たち四国勢は港へと向かう。船のもやいを解き、帆を上げるが潮が大きく引いてしまい船を出すのは適さない。
元親は浜の前に陣を敷き、余った船を柵として銃兵と弓兵を配した。太郎兵衛も弓を手に取り、横倒しにされた船から顔を出して南を見つめる。
濛々と煙が上がり、街から火が出ているのがわかる。それが島津方によるものなのか、狼藉者の仕業かはわからない。だが、大友氏の拠点として栄えた府内は灰燼に帰そうとしていた。
「何か見えるか」
元親が身軽に舷側に手をかけ、身を乗り出す。千雄丸が心配なのは、口に出さなくてもわかった。太郎兵衛も父の無事を確かめたいが、焦りだけが募る。
府内の街からは煙が上がっているものの、島津の十字も長宗我部の帆掛舟も見えない。奇妙な静けさがしばし続いた後に、武者を乗せた一騎が駆けてきた。
「雄の近習だ」
元親は慌てて船から下りると自ら出迎える。矢傷と鉄砲傷でぼろぼろになった騎馬武者は、元親を見ると滑り落ちるように馬から下り、そしてその足もとでうずくまった。
「よく無事で帰ってきた」
と肩を抱く元親にすがり、慟哭する。そしてひとしきり泣いた後、
「千雄丸さま……、討ち死にされました!」
と言って意識を失った。元親はしばらく、身じろぎ一つしなかった。太郎兵衛も一領具足たちも、ただ言葉もなくその背中を見つめている。
「手当てをしてやれ」
静かな口調で命じた元親は、続けて、
「馬を曳け。槍を持て。これより千雄丸の弔い合戦を行う」
と命じた。元親は甲冑を締め直し、今にも討って出ようとする勢いである。それを見て兵たちは色めき立ち、続こうと騒ぎたてる。だが、
「これから我らは海に出るのです。千雄丸さまが何故殿に残ったかおわかりなさいませ」
谷忠澄が立ち塞がって諌めた。
「うるさい」
元親は激することなく、忠澄を蹴散らそうとする。さすがの忠澄も馬蹄を慌てて避けた先に、太郎兵衛が立った。
「そこをどくのだ。お前の父も雄についていた。助けに行かねばならん」
だが太郎兵衛はそれに答えず、信親から託された左文字の太刀をぐっと元親の目の前に突き出した。
「千雄丸さまはこれを俺に託し、土佐侍従さまをお守りしろと命じられました。その心を無にするわけにはまいりません」
「これは我が子のための戦いである」
元親はあくまでも討って出ようとした。
「お心をわからず無駄に死んで、それで千雄丸さまと冥土でお会いできるとお思いですか!」
自分でも驚くほどに激しい叱責が、口をついて出た。元親は槍先を太郎兵衛の喉元に突き付け、
「道をあけよ」
と厳しい声で命じる。だが太郎兵衛は左文字を掲げたまま退かない。しばらく睨み合いになった末に、折れたのは元親の方であった。
「総見院さまは、かつて雄を見て養子に欲しいと仰ったことがあった。もちろん、質としてとるという心はあっただろう」
馬を下り、槍を収めた元親は天を仰いだ。
「天下に覇を唱えようとする男に息子をとられてなるものかと焦った俺に、あの方は仰った。この子は天馬である。それにふさわしい場は四国にはない。近くで育て、ゆくゆくは織田の翼となって欲しいと願われたものだ。慌てて断わると、信の一字とその左文字を下さった」
元親は息子が討ち死にを遂げた戸次の方角を見つめていた。
「あの頃の俺には大望があった。西に覇を唱え、雄と共に天下を向こうに回して勝負をかける。だが、総見院さまの顔を見た時、これは敵わぬな、と実感したものだ。あの目、気迫の凄まじさを持つ者は四国にはいない。雄をあのようなお人の側においては、父である俺のことも忘れてしまうに違いない。そうとまで思いつめたものだ」
だから元親は四国の覇者を目指した。
「天下と五分に渡り合うためには、総見院さまを超えなければならぬ。だから本能寺で倒れられた時には安堵したものよ。これで宿願に一歩近づいたと手を打ったものだ」
信親も、信長に名を一文字与えられるに十分値する力を示した。
「まさに天馬だったよ。そのまま俺を置いて、天下に名を轟かせて欲しかった……」
府内からは島津の軍勢が姿を見せている。
「時が来たようだ」
元親はむしろ嬉しそうであった。
「飯を食え。腹いっぱい食え」
元親は干し飯を頬張り、太郎兵衛にも分け与えた。太郎兵衛の兵糧は乱戦の中でなくなっていた。
「食べる気がしません」
よくこんな時に飯など食えるな、と太郎兵衛は感心していた。信親は討たれ、父の安否も絶望的だ。太郎兵衛はもはや疲れも忘れ、ただ敵の中に突撃する自分だけを頭の中に思い浮かべていた。だが元親は清々しい顔で飯を食い続け、水を飲んで大きく息をついている。
「空きっ腹で存分に戦えるか?」
確かにそうか、と太郎兵衛ももそもそと干し飯を口に入れる。ただでさえ味のない乾いた米粒は口の中に貼りつくが、我慢して飲み込んだ。
「これも食え」
元親が差し出してくれたのは、梅漬けであった。酸味や塩気を予測していた太郎兵衛の舌は裏切られる。それは体が震えるほどに甘かったからである。
「土佐は砂糖も名産でな」
元親は信長に三千斤もの砂糖を献上したことで知られていた。甘味の後で酸味が立ち現れ、しばらくすると疲れがすっと引いた。
「飯のあてにはならんだろうが、力は出る」
確かに甘酸っぱい梅漬けと干し飯の相性は良いとは言えなかったが、交互に口に運んでいるうちに力が湧いてくる。
「不思議なものだ」
元親は全て食べ終わり、余った梅を旺盛な食欲を見せている近習たちに分け与えると、立ち上がった。
「どれだけ悲しかろうと、食えば気力が湧いてくる。雄も腹が減って足もとのふらついたわしの姿など見たくはなかろう」
手を払った元親は再び槍を握った。
「太郎兵衛、すまぬな。せっかくわしに生きよと言ってくれたのに、潮が満ちねば船も出ぬ」
太郎兵衛は土佐の男たちの闘気が徐々に上がっているのを感じていた。敗北を前にした消沈したものではなく、その横顔の一つ一つが輝きを帯び始めている。傷を負っていようといまいと、その目はひたと敵に向けられ、元親の下知を待っている。
鶴賀城の面々と同じだ、と太郎兵衛は感じた。城はどうなったのか、明らかではない。だが落城したという報せもなかった。彼は豪永や統久たちがあの城を守りきっているのではないか、という予感がしていた。
信親の遺志を継がなければならない。そのためには、元親を死なせるわけにはいかない。太郎兵衛は左文字をそっと撫でる。
「敵軍、前進を始めました」
物見が告げるまでもなく、太郎兵衛たちからも島津方の動きは見えていた。一際大きな十字の旗がはためいている。
「家久め、来るなら来い。土佐侍従の意地を見せてくれる」
元親は泰然と立って敵の動きを見つめている。互いの鉄砲が届くか届かないかぎりぎりまでの位置まで進んだところで、島津軍は動きを止めた。
「まだ撃つな」
元親は厳しく言い渡す。火縄は点火され、弦は引き絞られている。数少ない騎馬武者たちもいつでも飛び出せる態勢にあった。
対峙は永遠に続くように思われた。張り詰めた空気は一瞬たりとも緩まず、それでいて暴発する者もいない。達人同士の立ち合いのように、静かだった。
島津の本陣から、一丁の輿が兵たちに担がれて進み出てきた。兵たちが狙いを定めるところを、元親は下げさせる。先頭に白い幟を二本立てたそれは、葬列のようであった。
「何かの策でしょうか」
谷忠澄は元親に訊ねるが、答えずにじっと黙ったままである。
「輿を担いでいる連中、島津では名の通った者ばかりだ」
行列の先頭を歩いているのは、川上久智という、豊薩合戦では諸方で功を立て、敵方にまで名の知れた男であった。信親を討った部隊を率いる新納忠元と共に、戸次川での釣り野伏せで大いに働いた男である。
「何かの策略です。撃ちましょう!」
銃卒たちが迫ったが、元親は頷かなかった。
「敵の動きから目を離すな。不意を衝いてくるとしたら今だ」
冷静さを失わないまま、元親は輿を通させる。輿は人が一人乗れる程度の大きさで、人数が潜んでいるとも見えない。太郎兵衛は懐の中の石を握りながら、輿がゆっくりと下ろされるのを見つめていた。
川上久智は元親の前で名乗り、島津家久からの軍使である旨を丁重な口調で告げる。薩摩の訛りが、太郎兵衛の耳には新鮮だった。元親も慇懃に礼を返し、用向きを訊ねる。
「我が軍の新納忠元が手の者が土佐侍従どののご子息と槍を合わせ、首を申し受けましてございます」
太郎兵衛には、元親の大きな体が一瞬揺れたように見えたが、
「左様承っている」
と静かな声で応じた。
「戦のこと故、是非もなしと又七郎さまは仰り、ここに千雄丸信親さまのご遺体をお返しするものであります」
元親は微かに頷き、
「心配り、痛み入ると家久どのにお伝えあれ。これより後は存分に戦おう」
そう言って久智たちを送り帰そうとしたが、久智はもう一つ用件があると続ける。
「これより夕刻まで、我らは構えを解きます。激しい戦いに我が軍も疲れが濃く、兵糧をとらせねばなりません。全ての槍を伏せ、火縄を消し、ゆったりと休まねば兵も働けませぬゆえ」
冗談のようなことをごく真剣な口調で告げた後、薩摩の使者たちは帰って行った。しばし呆然としていた長宗我部の将領たちは、元親の命を待つ。
だが、元親は輿から下ろされた棺の前に崩れ落ちていた。
「潮が満ちたらすぐに船を出す用意を」
谷忠澄が諸隊に命を送る。
「島津の策では」
そう心配する者もいた。
「もはや島津が我らと戦うことはあるまい。疲れているのは間違いないだろうが、ここで我らが下手に足掻いても千雄丸さまの想いを踏みにじるだけだ。大友の主力は山にこもり、阿波、讚岐の兵たちは壊滅だ」
仙石軍は小倉に落ち、十河の残兵は長宗我部勢に収容されている。小早川秀包は臼杵の救援に向かっているとなれば、もはや戦える状態にない。
「我らは千雄丸さまを失った。身を挺して我らをお守り下さったことを忘れてはならん。この恨みを忘れず、土佐に帰ろう」
忠澄の言葉に、将兵たちは肩を落とし、それぞれの船へと乗った。元親は肩を震わせて涙を流していたが、やがて立ち上がると棺を船に乗せるよう命じた。
一瞬にして十は年をとったようにやつれてしまっていたが、
「太郎兵衛、小三次どのの消息は知れぬが、我らと共に来るか」
と気遣ってくれた。
「このまま豊後に残るのは危うい。高崎山城は島津に囲まれているだろうし、臼杵や他の城もどうなっているかわからん。俺たちと共に四国へ退き、後のことを考えよう」
「ありがとうございます」
息子を失った悲しさを隠して、四方に指示を出す元親の姿を見て、太郎兵衛もようやく心が落ち着いてきた。一領具足や兵たちも、家臣たちもそうであった。息子の変わり果てた姿に慟哭していた元親が常の姿に戻ったことが、皆の混乱を抑えていた。
「でも俺、父上を捜します。関白さまの使者として父が生きているのなら、復命させねばなりません。もし討ち死にしたのであれば、確かめて俺が代わりにそう報告します」
自分でも思った以上に、冷静な言葉が出た。
「そうか……。見上げた心がけだ」
元親は頷き、船に乗り込んだ。太郎兵衛は呼び止め、信親の形見である左文字を手渡そうとした。だが元親は受け取らず、逆に自ら佩いていた短刀を太郎兵衛の腰に挿してやる。
「雄のやつが刀を託したのは、俺に渡して欲しいからじゃない。戦場でお前を見込んだからだ。その心を無にするでない。そしてこの短刀は、息子の刀を引き継いでくれたお前へのせめてもの感謝の気持ちだ」
刃を見ると、吉光、と銘が切られている。太郎兵衛もさすがにこの刀の価値は知っている。京の粟田口に住み、鎌倉時代に多くの名品を残した伝説の刀鍛冶、粟田口吉光である。信長や秀吉も熱心に集め、また褒美や外交の際に大いに活用したものだ。
「関白さまにいただいた物だが、これを佩いて復命すれば、誰もお前のことは侮らぬ。土佐侍従の父子の刀を授けられる者として、堂々と働くがいい」
また会おう、と元親は朗らかに手を振って海へと出ていった。潮は満ち、多くの傷ついた兵を乗せた軍船が東へと向かう。速吸瀬戸は勝とうが負けようが、人の都合など関係のない難所だ。来島の旗印を上げた数隻が先陣を切り、波の向こうへと船団は消えていった。

第五章 徹斎
一
穏やかな潮の香りが漂っている。昨日までの雪混じりの寒さが嘘のように、南国の温暖さが戻っていた。
先ほどまで周囲を埋め尽くしていた男たちが発する、汗と脂と血の臭いはすでに沖合へと去った。戦は終わり、四国勢は大敗を喫してしまった。
四国に帰る船団を見送った後、太郎兵衛はしばらく砂浜に座り込んでいた。千雄丸、長宗我部信親の遺体が置かれていた場所にそっと手を伸ばした。あれほど強く、颯爽とした若武者が首のない死体となって敵陣から送られてくる。それが戦なのだ、と太郎兵衛は己に言い聞かせた。
だが、父が死んだかもしれないことを自分に納得させるのは難しかった。どうにも立っていられない。信親の遺体を見て嘆いた後、すぐさま軍の指揮をとり始めた元親の姿が瞼の裏に焼きついて離れない。
動揺していた四国の残兵がきびきびした動きを取り戻したのは、元親の常と変わらぬ下知を受け始めてからであった。すごいな、と感嘆したが自分にはできないことだ、とも思った。
敗走した際の焦りと恐怖が収まって冷静になった途端に、体じゅうの力が抜けてしまったのだ。父の安否が知れないことと、信親の死が肩に重くのしかかっている。
「四国へ行けばよかったかな……」
吉成が無事なのかを確かめねばならない、とも思ったが一人ではどうにもならない。まさか島津の陣に訊きに行くわけにもいかない。
腰の両刀が重い。体の大きな信親が佩いていた太刀は、やはり大きかった。二尺はありそうな刃は、まだ体の小さな太郎兵衛が背伸びしても地面に摺るほどである。太刀を布に包んで背負い、脇差だけを腰に挿す。
「筑前へ行こう」
自分に言い聞かせて、立ち上がる。筑前は毛利の本隊と軍監の黒田孝高や安国寺恵瓊が押さえ、島津も押し返されている。秀吉が九州に向かっているかどうか太郎兵衛は知らなかったが、父の行方を捜すにも復命するにも、孝高に合流するのが都合がいい。
仙石勢と共に後退したはずの又兵衛の消息がわかるかもしれない、ということもある。彼になら一緒に父を捜してもらえるかもしれない。
そう考えた太郎兵衛は、立ち上がって歩き出した。このまま豊後街道を西にたどれば、大友義統が篭る高崎山城に至るが、そちらは島津の大軍で満ちているに違いなかった。
もうひと押しで全滅させられた四国勢を見逃した島津の意図は、太郎兵衛にはよくわからない。だが、このまま豊後から引き下がる気配はなかった。四国勢が海に出たのを見届けた島津軍の主力が、そのまま土煙を上げつつ軍を西に向けて動いたのを太郎兵衛も目にしている。
主要な街道筋を進めないとあれば、海沿いを行くしかない。高崎山城がまだ落ちていなければ、そこから北にはまだ島津軍は進んでいないはずだ。
府内の大友館はほぼ無人となり、陥落しているのは間違いない。太郎兵衛は物陰に隠れるようにして、海沿いの木立を進んでいく。村々から出てきた民たちが一揆を組み、戦の後に金目の物が落ちていないか探している。
落ち武者狩りも始まっているのか、身ぐるみ剥がされた死体があちこちに転がっている。府内から高崎山の北を回り込んで北上すれば別府の町がある。だがそこまで行っても安全かどうかは自信がなかった。
震えそうになる体に力を入れ、太郎兵衛は先を急ぐ。
小倉街道、と道標にはあった。
島津は城を攻める陣を南に敷いているのか、幸いなことに兵の姿はほとんど見えなかった。戦の真っただ中にある府内へと向かう人影もなく、太郎兵衛はほっと胸を撫で下ろしつつ、海辺の道を歩く。
二本の岬が海を抱いているような田浦を右手に見て進むうちに、ようやく街道をゆく人の姿も多くなってきた。街道といっても、荷車が一台通れるほどの幅しかない粗末なものだ。それでも道に人がいるというのは随分と心強いものである。
太郎兵衛の格好は血と汗に汚れたものであったが、道行く人もさして気にする様子もない。九州一円が戦場となっている時に、けが人など珍しくもなかったからである。
もう目の前に別府の港が見えている。山が急速に開けてくると、太郎兵衛の足も自然と軽くなった。だが轟音が響き、太郎兵衛は地面に倒れ伏していた。
頭が石で殴られたように痛い。
一瞬気が遠くなりかけたが何とか踏みとどまり、衝撃を受けた辺りを手で触る。指に血はついていない。銃で撃たれたことはわかったが、弾は頭のすぐ近くを通っただけですんだらしい。
すぐに起き上がって木立に飛びこみ、振り返る。
鉄砲を持った男が、数人の杣人姿の男たちに合図をし、太郎兵衛が潜んだ木立を取り囲むよう指示している。
落ち武者狩りに見つかったのか、と太郎兵衛は暗澹たる気分になった。足取りは軽くなったものの、合戦の後で体は疲れている。腰には元親の吉光、背中には信親の左文字という業物がある。
「若いお武家さまよ」
鉄砲を担いだ頭目がのんびりした口調で声をかけてくる。
「随分と立派なものを腰に挿していらっしゃる。どうです、お服も汚れているようだ。私が良い値で買い取ってあげますよ」
そう言いながら、男たちは包囲の輪を狭めてくる。又兵衛がいてくれれば、と太郎兵衛はくちびるを噛んだ。こんな野盗どもは一網打尽にしてくれたはずだ。
こんなところで元親からもらった名刀を抜きたくはなかったが、野盗の類に大人しく渡すわけにもいかない。太郎兵衛は気配を殺し、男たちが間合いに入るのを待った。
だが、次々に一揆勢の姿は増えて、ついには二十人を超えた。鉄砲を持つ者こそ、頭目の一人だけだが、多くが太刀や手槍を持ち、弓矢を構えている者もいる。海と山に挟まれたこの辺りに住んでいるせいか、漁師のような風体をしている男たちも交じっていた。
「出さぬのなら致し方なし。おい、取ってこい」
頭目らしき男は周囲に命じる。太郎兵衛はゆっくりと短刀を抜く。手にずっしりと重いのに、握っているうちに手になじみ、体と重なっていくような錯覚を起こさせた。
白刃のひらめきが恐怖を拭い去ってくれる。
太郎兵衛は身を沈めて駆けだすと、頭目へと一気に間合いを詰める。多勢に油断していた男の腹に体ごと突き込むと、うめき声と共に腹を押さえて倒れた。
「何しやがる!」
賊たちが激昂して襲いかかるが、吉光の短刀は確実にその急所を抉っていった。刃こぼれは感じず、血脂で切れ味が落ちることもない。だが五人倒したところで、太郎兵衛は膝をついた。
体が動かない。刀に力を吸い取られたような激しい疲労である。賊たちから繰り出される槍を避けきれず、いくつかの傷を負ったところで意識も薄れ始めた。
「こんなところで!」
ともう一人の首すじを刎ね斬ったところで、全ての力を使い果たした。賊たちは勝利を確信したのか、太郎兵衛に罵声と嘲りを投げかけながらとどめを刺そうと刃を振り上げた。
「諦めるもんか!」
そう叫んだところに白刃が振り下ろされる。瞼を閉じず、ゆっくりと脳天に食い込もうとする刃を見つめていたが、いつまでも刃は体に届かない。それどころか、太郎兵衛を取り囲んでいた賊たちは一斉に地面に倒れ伏してしまった。
痩せた長身の侍が、倒れている男たちの中央に立っていた。懐手に薄汚れた小袖姿で腰に大刀を一本だけ挿している。どこかの家中というわけでもなく、足軽風情という風でもない。場にそぐわない気楽な雰囲気を漂わせている。
「確かに、童には似つかわしくない刀を持っているな。しかも二振りか」
若いようにも見えたが、髪は半ば白かった。目は細く、瞳に浮かぶ表情はうかがえない。
「おい、なんだお前は」
賊たちが後ろから怒鳴りつけるが、男は倒れた頭目を見下ろして顎を撫でている。
「童、いい突きだな。刀を見せてみろ」
太郎兵衛は言われるままに、吉光の短刀を手渡した。穏やかな声は、どこか逆らい難い威厳を漂わせていた。
「おい、これ粟田口じゃないか」
男は細い目を大きく見開き、短刀を太郎兵衛に返した。
「お前どこかの公達か?」
太郎兵衛は名乗らなかった。相手が何者かわからぬのに、正体を明かすのは危険だった。
「私は丸目徹斎長恵という浪人よ」
その名に、微かな聞き覚えがあった。
「丸目、徹斎……」
剣聖である上泉信綱に柳生宗厳らと共に教えを受け、免許皆伝を許された数少ない剣士である。京での評判は抜群で、太郎兵衛もその名を知っている。剣術を学ぶために弟子入りしないかと吉成に勧められたこともあった。
驚きつつ、太郎兵衛も名乗った。
「黄母衣衆の子か。なるほど、お前のような子でもそれほどの名刀を挿せるほどに関白の羽柴筑前の威勢は大きくなっているのだな。そちらの太刀も見せてもらっていいか」
「違います。さるお方から預かっているものです」
「どちらでもいいさ」
手を差し出す男に、太郎兵衛は背負っていた左文字も渡す。男の刀を扱う手つきは丁寧で、優美にさえ見えた。
すると業を煮やした賊の一人が、槍で突きかかる。
「邪魔をするな」
男は言うなり後ろに足を突きだす。軽く出したように見えた足裏に触れた賊の一人は宙を飛び、立ち木の幹に激突して動かなくなった。
「これは左文字か」
太郎兵衛が頷くと、
「土佐侍従さまのご子息に与えられた筈だが」
「……千雄丸信親さまは、島津との戦いで討ち死にされました」
「そうか」
話している間にも、賊たちは背を向けたままの丸目長恵に斬りかかっている。だが、わずかに長恵が身を揺らして手を振るだけで、賊たちは顎を砕かれ、鼻を潰されてうずくまる。拳や肘を使っているらしい、としか太郎兵衛にはわからないほどの速さである。
「大切に持っておきなさい」
長恵が左文字の太刀を返してくれた時には、賊のほとんどが地に倒れ、残りは逃げ去っていた。
二
「鶴賀城は落ちたのですね」
噂は街道を走る。戦に関わった者、目にした者が四方に伝え、それが広がっていく。統久たちの安否を気にしていた太郎兵衛の耳にも、その報は入ってきた。
「お前が落ち込んでも仕方ない」
丸目長恵は太郎兵衛を慰めた。
「ですが……」
四国勢が惨敗し、救援は望めない。総大将の利光宗魚が討ち死にする瞬間もこの目で見た。すぐに降伏したとて恥ずべきことではない。それよりも、太郎兵衛は統久や豪永を思って、くちびるを噛んだ。
「ある種の武人は表すべき心を大切にする。本意といってもよい。そういった連中にとって生死はその後のことなのだ」
馬が二頭ようやく並べる程度の道を、丸目長恵は速足で歩いている。腰の位置がほとんど上下せず、手もほとんど振らない。そして何刻歩いても息ひとつ乱さなかった。起きている時に止まるのは用を足す時か食事を摂る時だけで、どちらも一日に一度、朝の起きぬけにする。飯は乾飯を一握りに味噌玉を少しなめる程度だ。
「飯も糞も心のままだ」
と長恵は涼しい顔をしている。
小倉へ通じる街道沿いは、人気が少なかった。
「島津が来ると皆が怖がっていたからな。あいつらは蝗のようなものだ。それぞれは別々の事を考えているのに、襲いかかる時は一団となって派手に略奪していくからな。百姓たちからしたらたまったもんじゃない」
日が暮れれば街道脇の木陰に寝そべって火を熾すと、あっという間に寝息を立てる。空腹と寒さで寝付けない太郎兵衛は歯を鳴らしながら身を縮めているばかりだった。
明け方になると長恵は火を再び熾し、湯を沸かして椀に一杯飲み干す。この瞬間が、一日のうちでもっとも心が休まった。
「寒いからこそ温かいもののありがたみがわかる。負けているからこそ、勝ちのありがたみがわかる」
ひとり言のように、長恵は言うのであった。
ともかく、この剣客が筑前まで送り届けてくれたおかげで、太郎兵衛は無事に豊前小倉までたどり着くことができた。
長恵は九州ではとにかく名の通った剣士らしく、どの村を通ろうと弟子が出迎えた。驚いたことに、筑前の諸将も大抵顔見知りらしく、訪れては剣技と理を教えては一泊する。一刻でも早く毛利の本陣にたどり着きたい太郎兵衛であったが、長恵の話がわからないなりに楽しく、複雑な思いだった。
長恵は豊後から海岸線をたどって豊前に入ることはせず、日田の盆地を経由して筑前へと入っていた。
「この道を島津が通ったのさ」
長恵はさして先を急ぐでもなく、歩を進めている。戦場だった形跡はほとんどなくなり、注意して見ると道のあちこちに欠けた鏃や鉛玉が落ちている程度だ。
「これから先も、この道を大軍が通ることになるだろうよ」
「関白さまが来るのでしょうか」
「島津が惣無事に従うかどうかにかかっている」
確かに、島津の強さは恐ろしいほどであった。長宗我部元親をはじめとする四国の諸将は、仙石秀久の暴走はあったにせよ、まるで歯が立たずに敗退した。
「大友からの求めに応じて九州を先に片付けようとしたのは賢いことだ。天下から私の戦を取り除く、という大義を明らかにできるのだから」
丸目長恵は、剣を教える時も自ら立つことはなかった。言葉で一つ二つ、助言を与えるだけである。驚いたことに、太郎兵衛に弟子の相手をさせることすらあった。
「俺は丸目さまの弟子ではありません」
「そんなことはどうでもいいのだ」
長恵は戸惑う太郎兵衛にかまわず、道場に立たせる。太郎兵衛の剣は犬飼九左衛門に教えてもらったもので、戦場往来の実用的なものだ。長恵の弟子たちも大きな所では変わらないが、太郎兵衛も気付かないところで様々な工夫がなされていた。
気付くと刀を落とされていたり、小手を押さえられたりしている。組み打ちも上手で、取っ組み合いには自信のある太郎兵衛もあっさりと組み伏せられることが多かった。その強さの秘密を訊ねると、
「知らぬ者には勝てるような方策を考えているだけだよ」
と言うばかりだ。
「兵法というやつですか?」
「戦場というのは、でたらめに見えて決まった流れがある。戦における人の動きも同じだ。相手の剣が迫っていれば逃れようとするし、弱気を見れば嵩にかかる。そのあたりの機微については、我が師は抜群によくご存じでな。おかげで私が負けることはまずなくなったのだよ」
長恵が話すきら星のごとき弟子たちの中で、特に太郎兵衛の興味を惹いたのが立花弥七郎統虎、後の宗茂である。もちろん、太郎兵衛もその武勇を聞き知っている。
筑前に攻め寄せてきた島津軍を父の高橋紹運と共に迎え撃ち、父以下岩屋城に篭った者たちが全滅するという大きな犠牲を払いながら、ついには撃退した勇者である。
「ちょっと立花城に寄って行こう」
と長恵が言った時には、胸がときめいた。
篭城戦の凄まじさは、太郎兵衛も鶴賀城でつぶさに見てきたばかりだ。その苦しさと、守る者たちの強さは尋常ではない。利光宗魚の戦いぶりは太郎兵衛の心に深く刻み込まれている。
それほど勇敢に戦っても、宗魚は敵弾に倒れた。残された宗魚の弟である豪永と息子の統久はさらに数日、島津の攻勢を支え続けたが、四国勢の敗退と大友義統が高崎山城にこもって救援を出さない態度をとったことから降伏したらしい。命は無事だと知って、太郎兵衛もほっと胸を撫で下ろした。
ともあれ、立花宗茂は大友宗鱗に救援を求め、宗鱗は自ら大坂に秀吉を訪れて助けを願っていた。毛利や長宗我部が出撃するとなっても、いつとも知れない助けを待ちながら島津軍と戦い続け、ついに撤退させたことには驚くほかない。
「まだ弥七郎は十九だ」
と長恵が言ったので、太郎兵衛はつい信親を思い出してしまった。戸次川で散った長宗我部の御曹司と二つ違いである。
「岩屋、立花の戦で何を得たのか、ぜひ知りたいものだ」
長恵は話好きな男で、歩いている間はもちろん、弟子の家に寄せてもらえば夜半遅くまで喋っている。
「私は将としてはまったく駄目な男だった」
見栄を張ることもなく、さらりと言った。
「そんなにお強いのに、ですか」
太郎兵衛の言葉に、長恵は照れ臭そうな表情を浮かべた。
「確かに一剣を以って相対すれば、私は大抵の者には負けぬだろうよ。それだけの剣を授けられ、自らも鍛えてきた。だがそれは、ただ一人、兵の強さに過ぎない。だが、将とは剣技が優れていればよい、というものではない。太郎兵衛にはちょっと難しいかな」
だが、太郎兵衛はその先をせがんだ。
「ふむ……。お前は私の剣を見た時よりも、興趣を惹かれた顔をしているな。なるほど。では将才がないなりに考えを述べてみようか」
兵が技であるとすれば、将は術である、と長恵は言った。
「技と、術……」
「一人一人は技を持っている。だがその技を束ねる戦の術に優れていなければ、軍を率いることはできない」
「そうすればいい将になれるのですか?」
「一軍を率いるのであれば、それで十分だ。だがその上がある。それは、略だ」
「略……」
「術を持つ将たちを束ねるには略がいる。戦の略、術の略だ。営み、謀り、大局を捉え、簡略を旨として鋭く打つことを略という」
太郎兵衛は頭がくらくらしてきたが、惹きこまれるものはあった。
「今、日本に略の心で天下を動かせるのは一人、いや二人かもしれん」
「関白さまだ!」
「そうだな。後は、三河の殿くらいか。あの方はやや術に偏る気配があるが」
長恵は楽しそうに腕組みをして話していたが、はっと表情を改めた。
「偉そうなことを言っているが、相良の殿に仕えている頃には、任されている城を落とされたりしたものだよ。よき将になりたくて色々と思い悩んだものだ」
だから城を守る苦しさと難しさはよく知っているという。
「城を守る時は将一人が強くても駄目だ。それは技でしかない。将の心が強くあるのはもちろんのことだが、兵が一人門を開いてしまえば、そこで終わりなのだからな。共に篭る者たちの気持ちを掴んでいなければならない。そこに術がいる。私にはそれができなかったんだよ。その点剣一筋に生きれば、将として人を死なせなくてすむ」
長恵は初めて苦い表情を浮かべた。
「戦いは突きつめれば全て一人と一人に行きつくのだが、将となればそうはいかない。我が師もそうで、将としては今一つでな。結局万人を統べる男にはなれんかった。そこで、己一人くらいは御せるようになろうというのが、我らが兵法の始まりなのだ」
と随分と情けないことを言う。だが太郎兵衛は、長恵の恐ろしい強さを目の当たりにしているから、何とも答えようがない。
「だが、この己一人を鍛えることによって、強き男をさらに強くすることができる。そうなれば、一人を平穏の境地へと導き、それが結局天下を平らかにする人材を作ると考えているのだ」
その理想の形の一つが、立花弥七郎という若者の形をとって筑前に現れているという。
「どんなお人なのですか」
太郎兵衛はどうにも気になって訊ねてみると、
「一見に勝るものはない」
といたずらっぽい笑みを浮かべて答えてくれない。
「私も、今の弥七郎がどうなっているのか、見当がつかないのだ」
日田の盆地を抜けて筑前に入り、北へと進むと再び左右から山肌が迫ってくる。その左右の山こそ、島津に相対した岩屋城と宝満城があった場所である。
「紹運どのには会っていこう」
急峻な山道を身軽に上がっていく長恵に太郎兵衛もついていく。
太宰府を見下ろす小さな山だが、登ってみると存外に険しい。登る者から見て覆いかぶさるように木立が茂り、岩峰をよじろうとしてもその先にはまた別の岩壁がある。狭い道は九十九折りとなり、頂まで着くのに随分と時間がかかった。
山の中腹に、ごく狭い平地があってそこだけはよく踏み固められている。
「ここが岩屋城だ」
と長恵に言われて、太郎兵衛は驚いた。言われてみると、確かに石組の跡は残っているようであったが、その他には何もない。ほんの数カ月前に激戦が行われたとは信じられないほどの、静けさであった。
「紹運どの以下、七百人余りが立て篭って、十数日の間島津三万の軍を食い止めた。見事な死にざまだ」
長恵が腰を屈め、何かを拾う。よく見ると、甲冑の錣だ。
「私にはできなかった」
そうぽつりと呟く。
「だが、他にできることは何かあるのだと思って、この世を歩いているよ」
錣を石積みの上に置き、手を合わせた。太郎兵衛は再び鶴賀城のことを思い出す。利光統久と豪永は篭城を止めて降伏した。長恵の言葉では、そうやって降ったことが何か悪いことのように言われている気がして、不愉快だった。
「何故怒っている」
手を合わせたまま、長恵は言った。
「どうしてわかるのですか」
「剣を長く握っているとな、不思議なことに周囲の人間がまとう心がわかるのだ。どれほど強いか、だけではない。心の中で何を思っているのかすら、伝わってくることがある」
合掌を終え、振り向いた長恵は、優しく太郎兵衛に怒りの理由を訊ねた。
「城に篭って戦い、仕方なく降った友がいます」
そう言うと、長恵は嬉しそうに頷いた。
「素晴らしい者たちだ」
「死ぬまで戦った方が立派なんじゃないんですか」
「人は生を享けて、いつどこで死ぬかわからん。そうならば、生を選ぶ方が貴いに決まっている」
太郎兵衛は長恵の言葉の意味がわからず、黙りこむ。
「答えなどないのだ」
岩屋城からの道を、長恵は下り始める。木立の先に太宰府の広大な敷地が見える。島津家久が陣を敷いたあたりは、草が少なくまだその痕跡をとどめていた。
「どれほど美しい死も、醜い生に及ばないことがある。どれほど醜い死でも、美しい生に勝ることがある。難しいよ」
長恵は登りよりもゆったりとした足取りで、山を下りる。
「さあ、弔いは終わった。生者の巷に戻ろう」
太宰府から北へ三里ほど歩くと、香椎宮が見えてくる。香椎宮の西はもう海である。潮風を遮るように聳えているのが、立花城である。南北に三つの峰が連なり、それぞれが城塞となって敵を防ぐ造りとなっている。
岩屋城よりも険しいとは見えなかったが、山襞の入り込みが深く、攻め落とすには相当に苦労しそうではあった。城の周囲には既に軍勢がいるわけでもなく、山裾の畑には農作業をしている百姓たちの姿が見える。
城の大手への道はきれいに掃き清められ、何年も戦と無縁であるかのような静けさをたたえている。
門には二人の兵が立っているのみで、長恵の顔を見るなり嬉しげに駆け寄ってきた。
「先生、いつ筑前にお帰りになったのですか。殿も落ち着いたからには剣の修業を再び始めたいから京に使いを送ろうかと仰っていました」
と古くからの顔見知りのように親しげに挨拶した。
「お前たちも息災で何より。弥七郎も元気そうだな」
「それはもう」
楽しげに言葉を交わす門番と長恵の後ろで太郎兵衛が待っていると、
「この子は新しいお弟子さんですか」
番兵が訊ねた。
「まあそんなもんだ」
違います、と言うのももはや面倒になって黙っている。
「弥七郎にこの子を引き合わせてやろうと思ってな」
門番たちは顔を見合わせたが、腰に挿している刀を見て慌てて奥へと駆けて行った。
「その刀、よからぬ者も引き寄せるが、挨拶代わりにもなって便利だな。大きな城に入る時は背中の太刀も見えるようにしておけばいい」
長恵は門番が帰ってくるのも待たず、先へと進む。立花山の頂に近いところに、館が設けられている。矢倉や柵は、鶴賀城で見たものよりもやや大掛かりではあったが、登ってみればそれほど、堅い城とも見えなかった。
三
館から一人の若者が出てきた。一瞬、太郎兵衛は信親の幻を見たのかと目を疑っていた。それほどに、背格好が似ていたのである。
「こちらは四国勢軍監を務められた森吉成どのの子息、太郎兵衛だ」
いきなり、長恵は太郎兵衛を紹介した。
「立花弥七郎にございます」
はるかに年下で、服も汚れてぼろぼろの太郎兵衛に対し、弥七郎は丁寧に挨拶をした。だが太郎兵衛は返礼もせずに突っ立ったままでいる。
「どうした?」
長恵に声を掛けられて我に返り、ようやくのことで名乗る。
「四国勢の方々は、気の毒なことでした。存分に戦えず、さぞや無念であったことでしょう」
心よりの言葉に、太郎兵衛は胸が詰まった。初めて会ったばかりだというのに、その一言が胸に広がっていく。顔を上げると、太い眉の下から黒目の大きな瞳がじっと太郎兵衛を見つめていた。
「あの……、言葉をお平らにしていただけると助かります」
弥七郎のような名将に辞を低くされていると居心地が悪くて仕方ない。そう言うと、弥七郎は少年のような笑みを浮かべた。
「紹運さまはよく仰っていた」
弥七郎は実の父のことを、そう呼んだ。今の彼の父はあくまでも立花道雪である。
「城の主と胸を反らせたところで、その命を支えているのは兵であり、その兵を支えているのは民である。そのことを考えると、誰に対しても偉そうなことを言えるわけがない。とはいえ、政となれば厳しく接しなければならないのが難しいところだ」
「すっかり大名らしくなったな」
長恵が言うと、弥七郎ははにかんだように顔を伏せた。
「何もかも手探りです」
「いや、将としても男としても、いい顔になってきた」
この立花弥七郎という若者は随分と大人びて見えた。最初に感じた重圧のようなものも今は消え、長恵の下座に静かに座っている様は、信親より若いとは到底見えない。
「師よ、天下が平らかになりましたら、またお教えを願いたく存じます」
弥七郎は手をつき、長恵に頼んだ。
「平らかになるのは、まだ相当先だな」
「ではそうならなくともお教え下さい」
「そう思ってふらふら歩きまわっている」
太郎兵衛は二人の遣り取りを聞きながら、どちらも岩屋城の話をしないのが不思議だった。弥七郎に対して悔やみを言うこともなければ、その戦いを振り返るようなことも言わない。長恵は岩屋城に行ったことすら口にしなかった。
「太郎兵衛、弥七郎の相手をしてあげなさい」
と命じられて庭に下り、木刀を握ったところではっとなった。
「俺、どうして弥七郎さまと立ち合うことになっているんでしょう」
弥七郎は木刀を下ろして笑いだした。
「何故ここに来て言うんだ」
「気付けばこうしていたのです」
弥七郎は冗談めかしていながら、責めるような視線を長恵に向ける。
「また先生はそういう悪戯を」
「悪戯ではないよ。弥七郎の腕と眼を試すには丁度いい機会だと思ってね」
訳の分からないまま突っ立っている太郎兵衛に、弥七郎が師の術の種明かしをした。
「我が師は剣で相手を制する術を使って、太郎兵衛を乗せたのだ。人の気が逸れた瞬間、呼吸が乱れた刹那に踏み込んで勝つのと同じように、意図したことをさせる。恐ろしい技ですよ。しかし先生、太郎兵衛と俺を立ち合わせたいですか」
長恵は悪戯が見つかった少年のように、こくりと頷いた。
「この子は弥七郎の気配に押されて、尋常なことでは立ち合ってくれないと思ったのでね」
そう言われると、太郎兵衛は俄然やる気が湧いてきた。
「お、その気になったようだな」
長恵は面白そうに足を組み直す。何故わかるのか謎だったが、太郎兵衛も弥七郎という若者から感じた圧力の正体を確かめたくなったのだ。
「弥七郎、制してみよ」
木刀を腰に挿したまま佇立していた弥七郎は微かに頷く。太郎兵衛は八双に剣を構えた。押されるような感覚はない。太郎兵衛は身を沈めるようにして踏み込み、伸びあがって木刀を袈裟がけに振り下ろした、はずであった。
だが、伸びあがったところで体は止まり、木刀もそこから先に進まない。弥七郎の瞳の黒が視界一杯に広がり、それが壁となって動きを止められているような感覚であった。ついで、その瞳から発せられた黒きうねりが白刃のひらめきへと変わる。
弥七郎が持っている木刀が真剣の鋭さを伴って襲いくる恐怖に、太郎兵衛は思わず叫び声を上げた。
「そこまで!」
長恵の声がかかり、太郎兵衛は自分が木刀を取り落として尻もちをついていることに気付いた。弥七郎の方を見ると、先ほどと変わらず木刀を腰に挿したままで、抜いてもいない。
「見事だ、弥七郎」
師に誉められても、弥七郎は太郎兵衛を見つめたままでいた。
「剣気で完全に制することができたな。まだ太郎兵衛が幼いとはいえ、素晴らしかった。ここ最近の戦がお前をさらに強くしている。惜しむらくは、もう少し太郎兵衛の剣を見たかったが」
弥七郎は倒れている太郎兵衛を助け起こして師を見た。
「この子には俺の心が全て読まれていたような気がするのです」
そうなのか、と長恵は太郎兵衛に訊ねるが、そんなことはないと首を振る。恐ろしげな幻覚に襲われて気付けば腰を抜かしていただけだ。
「そこまで見ていたのは、お前が初めてだよ」
弥七郎は満足げに微笑んで太郎兵衛から手を離した。
「この子にはぜひ先生の剣を授けて下さい。きっといい遣い手になります」
「将としてはどうかな」
「楽しみにしてよいのではないでしょうか」
その言葉に、長恵は満足げに頷いた。
四
豊前小倉に集結した豊臣方の軍勢は、町を覆い尽くさんばかりの人数だった。
「こんなもの、ただの先ぶれに過ぎないぞ」
長恵は大軍勢の中を悠々と懐手で歩いていた。誰何するものもいたが、名乗れば大抵それ以上何も言われなかった。それどころか、各陣屋から招きがくるほどであった。小倉ではどこにも寄らず、まっすぐに向かったのは城下にある小さな寺であった。
数百人ほどの小勢を率いてそこにいたのは、黒田孝高である。
「丸目先生が小三次どのの子を連れてくるとは、奇縁としか言いようがないな」
こちらを見ることもなく、忙しげに書状をしたため続けている。長恵はそれを無礼と咎めることもなく、勝手に寺の台所に行って人数分の茶を淹れて持ってきた。
「この子の父御の消息を知りたくてね」
筆を走らせる手を止めて、孝高は顔を上げた。
「太郎兵衛よ、四国勢を前にして島津は止めを刺さなかったのだな」
信親の遺体を返し、夕方まで猶予を与えて敢えて退却させた。そのおかげで、長宗我部と十河の残存兵力は無事に海を渡ることができたのだ。
「小三次どのは無事かも知れんぞ」
「どういうことですかな」
長恵は興味深そうに身を乗り出した。
「あそこで四国勢に情けをかけたのは、辱めを与えたようにも見える。だが、島津はあくまでも礼を尽くして信親どのの遺体を返してきた。敗走させたのではなく、兵糧をとらせるという名目で軍を止めて、その間に四国勢が軍を返すのは逃げたのではないと周囲に示すことができる。顔を立ててくれたと考えるべきであろうな」
「島津がそのような挙に出た意図は何です?」
「薩摩の連中、一筋縄ではいかん奴らだよ」
孝高は筆尻で広い額を叩きながら答えた。
「畿内から兵を率いてきた連中の足元を見るのに長けている。総力を挙げて戦うと見せつつ、指一本は繋げておこうとする。そこを見抜いて、四国勢を助けるよう仕向ける者がいたとしたら、それは関白さまの薫陶を受けた者だろうよ」
捕えられた吉成がそうさせたかも知れぬ、と孝高は言った。
「わかるのですか」
太郎兵衛は喜びを隠しきれない。
「中国を走り回って話をまとめていた一人だからな。わしも関白さまにつく前は、小三次どのと随分と膝を突き合わせて話したものだ」
ただ、と孝高は鋭い視線を太郎兵衛に送る。
「今の九州は何が起こるかわからん。小三次どのの案というわしの考えは誤りで、既に首になっているかも知れん。黄母衣衆といえば関白さま直属の精鋭だ。その首となれば価値もあろう」
「はい……。わかっています」
悄然とした太郎兵衛を見て、孝高はやや表情を和らげた。
「わしの知っている小三次どのは、それはしぶとい男だ。死地にあってもそう簡単に首を渡すような男とは思えん。生死は天のみが知っているが、子であるお前が不安を抱いていてはどうにもならんぞ」
「東はもういいのですか」
「徳川三河守さまとの和平は固い。そうでなければ、三十万の軍は動かせまい。出来ることならいらっしゃる前に島津を片付けておきたかったのだが、筑前と豊前どまりであったな」
秀吉は天正十五(一五八七)年の春を機に、直接九州征討の軍を起こすと公言していた。
「三十万もの軍が来るのか」
丸目長恵は天を仰ぐ。
「それほどの大軍が、一人の男の意思で動く時代になったのか」
「九州を手に入れればそれが四十万、関東を手に入れれば五十万になりますな。それが天下の力というものです」
にやりと孝高は笑い、再び猛烈な勢いで書状をしたため始めた。
五
太郎兵衛が大坂に帰ることはなかった。吉成と叔父たちがひょっこり小倉に姿を現したからである。
「太郎兵衛さま、ご無事で!」
杉助左衛門と宮田甚之丞に突き飛ばされそうな勢いで抱きつかれて、太郎兵衛は驚いた。
多くの郎党が傷つき、死者もいたが、一族の主だった者は無事であった。
「なんだその顔は。これから忙しくなるぞ」
「よくぞご無事で……」
「見ての通りだ」
息子の感傷などまるで無視して、吉成は黒田孝高へ報告に向かおうとした。
「太郎兵衛」
「は、はい」
「土佐侍従さまから委細は聞いている」
よくやった、と一言誉めるなり孝高のもとを訪れると、半日ほど何か語らっていた。これまでの話を聞いて欲しい太郎兵衛であったが、吉成は全く興味を示さない。
「お前が四国勢とどう動いていたかは土佐侍従さまからの書状で、その後どうしていたかは、丸目長恵どのから聞いている」
だから話す必要はないと言うのである。
「じゃあ父上は戸次川の後、どうしていたんですか。島津に囚われていたのですか」
「そうだ。殺すよりもいい使い方があったら使う。それだけの賢さがあるのが、島津という連中だ」
で話は終わりである。島津の陣中で何があったのかは一切口にしなかった。太郎兵衛が気になっているのは、吉成の献策で家久は四国勢への手心を加えたか否かであったが、
「それを知ってどうする」
と問われて言葉に詰まる。
「もし、俺が島津に四国勢に情けをかけろと言ったとしても、どうして彼らが俺の言葉を聞き入れる必要がある」
「……後々有利だから」
「それは官兵衛どのの受け売りだろう」
あっさりばれてしまう。
「太郎兵衛。土佐侍従さまをはじめ、四国勢は決して弱いわけではない。島津の知勇がそれをわずかに上回っていただけだ。戦の機微は俺ごときで左右できるものではない」
父が元親たちを救ったと思いたかった太郎兵衛の願いはあっさり否定された。吉成はそれ以上、島津に囚われている間の話をすることはなく、翌年に控えた秀吉出陣に向けた準備を進め始めた。
天正十五年の年も明けて、吉成は四方に奔走しているが太郎兵衛を連れて行くわけではない。かといって大坂に帰すわけでもなく、要するに太郎兵衛は暇を持て余していた。
「関白さまご出陣となるまで、我が陣でゆるりと過ごしているがいい」
黒田孝高はそう言ったきり、一室にこもって書状作りと謀議の日々だ。遊び相手になってくれるはずの又兵衛も、孝高の命を受けてあちこちに出かけている。
連れて行ってくれと父にせがんでみるが、
「今は待て」
と言われるばかりだ。暇つぶしの相手は、同じく陣内でぶらぶらしている丸目長恵となった。剣を教えてくれと頼めば相手をしてくれるし、釣りに誘えば隣で糸を垂れてくれる。忙しい陣中で、長恵の周囲だけが時の流れが別であった。
「丸目先生は軍を率いて島津と戦うのですか」
「向いてないから、やめておくよ」
「戦場に立って一番槍ですか?」
「私は己一人の強さを追い求める気持ちが強くてな。いまは誰にも仕えていないし、仕えるつもりもないよ」
そんな男が陣中にいるのが不思議であったが、孝高や吉成だけでなく、九州のあちこちから弟子が来ては話をしていくのでそれなりにありがたみがあるのだろう、と太郎兵衛は思っている。
「あ、私の剣を疑っているな?」
「滅相もない。丸目先生が強いのはこの目で見ています」
「口惜しいことに、太郎兵衛はあまり私の剣に心惹かれていないんだよな。筋もいいし、このまま剣に専心すればそこそこの腕になるのだが」
と実に惜しそうな顔をする。
「太郎兵衛の剣は、技の剣ではないんだよな」
とぶつぶつと何やら呟き続けていた。
春三月になって、のんびりとさえ感じられた太郎兵衛の周囲は一気に慌ただしくなってきた。前年から準備を進めていた秀吉は三十万の大軍を動員し、中国道を西に下り始めたのである。
宇喜多秀家を先陣、豊臣秀長を第二陣、そして秀吉自身は第三陣の主力を率いて九州へと上陸した。この万端の準備で、秀吉の中での勝算はほぼ固まっていた。
「島津のやせ城など、木の葉のように吹き飛ばしてくれる、と関白さまは意気軒高だ」
吉成は孝高に送られた朱印状を見せてもらい、安堵していた。彼がこのところ没頭していたのは、豊後の後始末である。
鶴賀城を抜かれ、府内を落とされた大友氏側であったが、すんでのところで踏みとどまっていた。大友宗鱗は臼杵に追い詰められていたものの、臼杵の支城である鶴崎城の妙林尼、豊後玖珠の日出生城に篭っていた鬼御前など女性たちの活躍など、必死の反撃で島津の猛攻を退けていた。この時秀吉は、毛利輝元と黒田官兵衛の中国軍を豊前まで進めており、島津への圧力を強めてその進撃を止め、ついに豊後平定を諦めさせたのである。
宇喜多の軍勢だけでも小倉の町は膨れ上がったように見えていたのが、秀吉本隊がやってきたことで町の様相は一変した。
「お祭りだ……」
そう太郎兵衛が呟くほどである。
「祭りか。なるほどな」
ここしばらく、息子と口をきく暇も見せなかった吉成が久々にくつろいだ姿を見せている。秀吉の本隊が来た時には、ほぼ全ての務めは終わっている、という算段であった。秀吉が中国道を西に進んでいる時から、吉成は何度も呼び出されていた。
「四国のことは、えらく殿に叱られたな」
そう言いつつ、父は怯えている風でもない。
「叱られるって、どうして?」
「仙石権兵衛を止められなかったうえに、千雄丸さまを死なせてしまった。大友の御曹司を動かすこともできなかったうえに、俺は島津に捕まってしまった。いいとこなしだ」
秀吉の怒りは、小倉にも伝わり聞こえていた。仙石秀久は改易に処せられ、十万石を失った。四国勢をまとめる地位にいながら、真っ先に逃げ出したのだから無理もないと太郎兵衛も納得していたが、父がしくじったとは思えなかった。
「豊後は負け戦だったからな。一国全てが島津になびいてもおかしくなかった。大友氏に義理だてする諸将がいてくれなければ、どうなっていたか」
島津の諸将は勇敢で智謀にも長けていたが、薩摩の人々は恐れられてもいた。兵が剽悍なだけでなく、その略奪も徹底していたからである。当時の戦場は、略奪と人攫いが横行しており、敗北によって蒙る損害は莫大なものとなっていた。
島津は人買い商人を陣に帯同しており、攫った人々を島原の市に持ち込んでは奴隷として売り飛ばしていた。身代金と引き換えに返すという取引も行っている。これに豊後や豊前の人々が激しく抵抗したのは言うまでもない。
「島津の自業自得でもあった。もし四国勢を率いていたのが殿なら、もっとうまくやったことだろう」
秀吉は行く先々で、ことさら仁政を印象付けようとしていた。兵糧は徴発するのではなく購入し、人を使えば賃金を払った。人買いなどもちろん厳禁である。
これが進軍先の人々の心を随分と和らげたことは間違いない。
「攻め入る先も同じ天下だと思っているから、無茶をしない」
三十万の軍を迎え入れた小倉では、嫌な顔をする者は少なかった。むしろ商売のタネがやって来たと大いに盛り上がったのである。商いをする者だけでなく、遊郭や芝居小屋まで立ち並んでいる。
吉成は久しぶりに自分から太郎兵衛を誘い、町に出ていた。しばらくあった話しかけづらいほどの張り詰めた気配は、なくなっている。
「皆もう飽き飽きしているからな」
「飽きているって、戦に?」
そうだ、と吉成は頷く。
「百年以上、どこかで戦いが起きている。ここ二、三十年は大きな戦いも多かった。総見院さまの代で考えても、どれだけの人死にが出たかわからない。疲れてきているのだよ。やる気に満ちた島津でさえそうだ」
九州を制覇するために兵を動かしたのも、結局は秀吉というより大きな相手との戦いを避けるためだと吉成は言う。
「殿は兵や民たちの心を汲み取るのが実に上手い。しかも九州ははるか遠いところにあるからな。兵たちを退屈させない工夫も必要だ。それが、祭りのように賑やかな小倉の町なのだろう」
だがもちろん、秀吉は将兵を遊ばせに九州に来ているわけではなかった。小倉に上陸した秀吉は何度か吉成からも九州の情勢を聞いていたが、三月二十四日の軍議には太郎兵衛も伴って参加するようにとの命が送られてきた。
六
大坂でも見たことのないほど多くの武将たちが、一堂に会していた。小倉城の大広間が一杯になるほどの人数である。太郎兵衛もさすがに気押されて、父の陰に隠れるように座っていた。
「陣立てを告げる」
秀吉は一段高いところに座り、諸将は広間に座っている。かつて同輩や上役であった者たちも、ごく自然に秀吉を見上げていた。陣立てを述べているのは石田三成である。戦をさせても強く、九州の諸将の取り次ぎも務めるなど秀吉に重用されている。
彼をはじめ、小西行長や前野長康などの兵站を担当した諸将は、秀吉の新たな側近団であった。
太郎兵衛は父が広間に座っているのが不思議ではあった。秀吉の傍らに侍って、こうして諸将に命を伝えるのが務めだと思っていたからである。
広間に集められた諸将は、三成の口元に注目していた。
「第一陣、森吉成どの、高橋元種どの、城井朝房どの、竜造寺政家どの」
そう名が読み上げられて広間はざわめきに包まれる。太郎兵衛も驚いて父を見上げるが、微動だにせず座っている。前に座る父の表情はうかがえないが、肩に力みがあるわけでもなかった。
吉成と共に第一陣を命じられた高橋元種と城井朝房は、共に九州の国人武将である。高橋元種は、島津について豊前、筑前を攻略しようとした秋月種実の次男にあたる。大友氏に従っていたが、毛利の調略によって寝返り、その家督を立花弥七郎宗茂の実父で岩屋城に散った高橋紹運に奪われている。
今や大友も毛利も秀吉に従っている。宙に浮いた形となった彼からすると、高橋家本筋の名誉を回復するために、どうしても避けられない戦いであった。もう一人の城井朝房は大友氏に従っていたが、島津の攻勢を見て寝返り、秀吉の出馬を見て再び寝返った。ここで戦功を挙げなければ信を勝ち得ることはできない。
そんな二人に交じって先鋒を務めるのが黄母衣衆の森吉成であったから、一同のざわめきはなかなか収まらなかった。
「森どのには十分な兵がおらぬゆえ、関白さま直属の近江衆と美濃衆をつける」
そう三成は告げて二番隊以降の陣立てを発表していった。太郎兵衛は、父がついに一軍の将になるという驚きと嬉しさで、体が震える思いだった。
秀吉は三十万の大軍を西の肥後、東の日向というふうに二手に分けた。吉成が先鋒を務める肥後表の総大将を秀吉自身が、日向から南へ攻め入る軍の総大将には豊臣秀長が就くこととなっている。
肥後方面軍には福島正則、木村重茲、堀秀政など秀吉子飼いの諸将が従い、日向方面軍にはもはや秀吉の腹心といってよい黒田孝高を一番隊に据え、小早川隆景や毛利、宇喜多、因幡の諸将など中国地方で新たに従った者たちが名を連ねている。一度四国へ撤退していた長宗我部元親の名も、日向方面の番外にあった。
やがて出陣の手はずが言い渡され、質疑があって軍議は終わる。三成の戦準備は周到で、質問が挙がることもほとんどなかった。
「小三次どのは官兵衛どのと同じほど信任を受けているのか」
という囁きが聞こえる中を、吉成は立ち上がり、広間を退出した。
「父上、やりましたね!」
黒田孝高が借りている寺の一室を、吉成たちは間借りしていた。帰り着くなり、太郎兵衛は叫ばずにはいられなかった。
「ついに一軍の将だ!」
いくら黄母衣衆といっても、知行は多くとも数千石、配下の兵は五百を超えないのが普通だ。千人、万人を率いて戦場を往来するのとはわけが違う。父の仕事は凄いと思うようになった太郎兵衛も、血の滾りを抑えられなかった。
「つまらんことだ」
吉成は特に慌てて準備することもなく、湯を沸かし始めた。庭に生えている茶の木の枝を何本か折ると、そのまま沸いている湯の中に突っ込む。
「茶の湯もできるかもしれないね」
出世すると、茶の湯ができるという。大坂城を訪れた際に見た茶室は、目も眩むような豪華さだった。あれこそ、世に出た者の証だ。名物と言われる茶器は千金の値であり、そのやり取りで国の命運が左右されることすらあった。
「俺がいつ茶の湯などやりたいと言った」
父が淹れているのは、出来合いの粗末な焼き物に庭でへし折った茶の枝である。優雅な茶の湯とはかけ離れている。
「お前、まさかそのような贅沢をしたいなどと望んでいるのか」
怖い声で問われて慌てて首を振る。
「茶の湯のために戦うなど、俺には阿呆らしくてできないな。そのあたりの茶の木でも十分に味が出る」
一杯先に自分で飲み、次の一杯は太郎兵衛に渡した。
「うまいだろう」
と吉成は言うが、それほどのものではない。微かに茶の香りはするが、そのすぐ後に泥水のような匂いがして太郎兵衛は顔をしかめた。
「白湯の方がいい」
「戦を経験して少しは大人になったと思ったが、まだまだだな」
吉成は苦笑すると、大の字になって寝てしまった。
秀吉軍がまずやるべきことは、筑前に残った島津方の拠点を一掃することである。島津方について岩屋城など諸方を荒らしまわった秋月種実に対してどう勝利を収めるかによって、戦況は大きく変わる。
「秋月種実が篭る古処山城を落とせば、決着はすぐにつく」
秀吉は当初、そう考えていた。秋月氏が本拠とする古処山と岩石の両城は、豊前小倉へと続く山塊の出口に位置する。遠賀川沿いに広がる平野を制せられては軍を自由に動かすことはできない。この城をそのままにしておけば、小倉に多くの守備兵を残しておかねばならず、徹底して叩かねばならなかった。
「岩石城を先に落とすべきです」
蒲生氏郷や前田利長は軍議でそう主張した。古処山を落とそうとすれば、東に位置する岩石城から側面を衝かれる恐れがある。それに、古処山城を陥落させたとしても、岩石城が堅く守って落ちなければ結局かかる手間は同じである。
「小三次」
呼ばれた吉成は黄母衣衆の一人として主君のすぐ傍らに控えていた。
「豊前をつぶさに見て、種実の取次をしていたお前はどう思う」
「岩石城を先にすべきです。種実は当初、私を通じて降伏の道を探っていました。心に迷いがあるうちに一気に片をつけるべきです」
とすぐさま答えた。
「では岩石城に寄せる」
秀吉は先鋒の諸将に攻略を命じたが一つだけ条件をつけた。
「一日だ。一日で落としてこい。派手に攻め、派手に討ち取り、派手に燃やしてくるのだ。しかし、降るなら許せ」
秀吉との付き合いの長い氏郷や利長は表情も変えず命を受けたが、九州で新たに従った高橋元種、城井朝房の顔は青ざめた。意気揚々と出陣の準備を始める蒲生勢や前田勢を横目に、城井朝房は吉成に歩み寄った。
「関白さまは我らに死ねと仰るのか」
城井氏は豊前宇都宮氏とも呼ばれ、祖は鎌倉時代に下野からやってきた。国人として長きにわたって豊前に勢力を張り、朝房の父、鎮房は城井谷城を本拠として周辺の大勢力の間で何とか勢威を保っていた。
鎮房は大友宗麟の妹を娶ったものの、耳川で大友軍が大敗すると一転して島津方についている。秀吉の大軍勢を見て敵対は避けたものの、鎮房自身は出陣せず、微妙な立ち位置を崩さなかった。
「そうですな。それくらいのお覚悟があってしかるべきでしょうな」
自陣に戻りながら、吉成はこともなげに答えた。
「城井どのは表裏のないところをこの一戦で諸将にご覧に入れれば、この先に行われるであろう九州国分けにおいてもめでたきことになりましょう。その際には私もきっと、口添えいたします」
と約束した。
「この戦、お父上が出て来られるべきでした」
鎮房は剛力無双にして弓の名手として知られる豪傑だ。
「父にも立場があるのです。ご理解を」
「わかっています。ですからこそ、あなたは殿に見せるべき姿がある。私はしっかりと見ておりますよ」
朝房は青ざめたまま頷き、自陣へと戻る。吉成は秀吉から与えられた一軍を前に、出陣の命を下している。森隊は前田、蒲生の両軍と共に岩石城に攻め込み、一気呵成に落とすこととなった。
太郎兵衛は吉成を支える将領たちを見て目を輝かせた。
「知っている人ばかりだ」
長浜で隣近所だった黄母衣衆の面々がいる。後に勝永と共に大坂で戦うことになる、速水守久、真野助宗、伊東長実は太郎兵衛を見て、若との、若君、とからかった。他にも、木村重成の父である隼人正重茲も陣に加わっていた。
「九州での働きは聞いているぞ。お前の名は俺たちで揚げてやるよ」
木村重玆が言うと一同が気勢を上げた。
石合戦仲間の連中で、近年元服を迎えた者もいる。それぞれが槍や鉄砲をかつぎ、一丁前の武者姿で馳せ参じていた。
「若!」
宮田甚之丞や杉助左衛門も新しい馬と甲冑を与えられ、輝くような笑顔を見せている。彼らは一隊を率い、吉成と共に進軍することとなっていた。
だが、血の気の多い者が増えれば揉め事も起きる。
「喧嘩だ」
と騒ぎが起きて太郎兵衛がすっ飛んで行くこともままあった。出陣を前にして、若武者たちが村の娘をかどわかしたという訴えがもたらされた。軍令で、地下のものへの濫妨狼藉は厳しく禁じられている。
「ことによっては成敗してもよい」
という吉成の命を受けて、太郎兵衛は走った。父の軍を辱める輩を許す気はない。彼が駆けつけた時には、悪さをした者たちは酒に酔い、娘の衣に手をかけて諌める者にも矢を放つ始末であった。
「戦に勢いをつけるんじゃ。邪魔をするな!」
猛り狂った男たちは五人ほどいて、いずれも腕に覚えがあるらしく、始末に負えない。太郎兵衛は怒りのままに突き進もうとした。だが、
「関白さまの軍は島津と変わらんな」
と凛とした声が飛んだ。武者たちを恐れる気配もなく、六尺槍に似た、長大な鉄砲を担いだ男が一人、立っている。
「何を抜かす。殿を愚弄するのか!」
「お前たちのような奴の姿が主君を愚弄しているんだ」
「やかましい!」
男たちは矢を番え、娘をなぶろうとしていた男も槍を構え、一気に銃手へと突っ込んだ。太郎兵衛が足元の石を拾い、印地打ちで救おうとした次の瞬間、山が震えるような轟音が響いた。
白煙が銃口から立ち上ったその時には、荒くれ者たちは一列になって倒れていた。娘は悲鳴を上げて村へと帰り、銃手はゆっくりと銃を担ぎ直して太郎兵衛の方を向いた。
「こんな連中がいるようじゃ、島津には勝てないよ」
太郎兵衛は駆け寄った。
「豊前でこんな無礼を働く奴は、俺と父上が決して許さない」
「五人使い物にならなくなった」
統久は鼻を鳴らし、倒れた足軽たちを見下ろす。
「でも統久が加わってくれたら、それでいい」
「嬉しいこと言うね」
統久の手を、太郎兵衛は握りしめた。統久も力強く握り返す。豊後戸次の鶴賀城を守っていた利光一族の跡取りで銃の名手がそこにいた。
「どうしてここに?」
「村は豪永おじに任せて、天下を見て回ることにしたんだ。それに、太郎兵衛には世話になったしな。つくとしたらお前のところだと決めていたんだ」
喜びに言葉が出ず、太郎兵衛はただ統久の手を握って何度も振った。
吉成が一軍を率いるのは初めてではあるものの、その下についた者たちは美濃や近江時代からの古馴染みが多い。主だった顔ぶれを集めて細かな打合せをするにも、よどみがなかった。
「戦になったら、真っ先に斬り込んで名を揚げてくれ」
吉成の指示は明快だった。
「銃戦では話にならぬほどこちらが優勢だ。秋月方は岩屋城や鶴賀城の戦訓を得て長く守ろうとするだろうが、そうはさせぬ。射すくめられているところを一気に行くぞ」
物見によって、城の守りは既に明らかとなっていた。山城らしく、峰や尾根に曲輪や出城を設け、要所に銃卒と弓兵が詰めている。大手の添田からは長い尾根筋を駆けあがらなければならず、搦め手の赤村からの道は険しい。
「蒲生と俺たちが大手、前田が搦め手と決まった。もちろん、蒲生勢に遅れる理由は何もない。戦が始まれば、我ら一丸となって、城主熊谷久重の首を挙げるのみだ」
吉成の言葉に、将兵は力強く頷く。
「出立は深更とする。今のうちにしっかり腹を満たし、休んでおけ」
そう言うと、吉成は陣屋に入った。大将に必要な武具は、黒田孝高がはなむけに全て揃えてくれた。
「さすが官兵衛どのだ。測ったようだな」
秀吉から拝領した水牛の角をかたどった兜は、これまで揃いだった黄母衣衆の無骨なそれとは違う華やかさであった。
「大将の貫禄が出てきたな」
顔なじみの近江衆が覗いてはからかっていく。太郎兵衛から見ても、漆黒の鎧に勇ましい兜は随分と立派に見えた。別人のようですらある。
「重いな」
何度か首を振って、吉成は兜の感触を確かめた。緒を締め終わると振り向き、どうだ、と太郎兵衛に訊ねる。
「随分と男ぶりが上がったように思います」
世辞をいうでもなく太郎兵衛が言うと、吉成はつかつかと近寄ってきて拳骨を振り下ろした。頭を抱えた太郎兵衛が涙目になりつつ父に食ってかかろうとすると、世にも珍しいものを見た。
「そうか、男ぶりが、上がったか」
吉成が片頬を上げて笑っていたのである。
合戦が近づくにつれて、太郎兵衛は落ち着かなくなった。吉成が軍勢を率いて、しかも先陣を切るなど、これほど晴れがましいことはない。体の火照りを抑えようと、彼はそっと城を抜け出す。
寅の刻には出陣すると言い渡されている将兵の多くは、鼾をかいて眠っている。城のすぐ傍らを流れる紫川に沿って、太郎兵衛は南へと馬を走らせた。夜気に当たれば少しは心も静まるだろうと考えたのだ。
紫川をしばらくさかのぼると、各地から送り込まれた軍勢があちこちに陣を張っていた。竜造寺の旗印が見える辺りに、小さな池がある。万葉の歌に詠まれたこともあるという紫池の畔に馬を止め、大きく息を吸う。
しっとりとした水辺の空気が心地よい。細道をゆっくりとたどっている間に、熱くなっていた心と体が落ち着いてきた。だがその時、何かの気配を感じて茂みへと身を隠す。
耳を澄ますと、水の跳ねる音が微かに聞こえてきた。音のする方へ顔を向けると、どうやら誰かが沐浴をしている。こんな夜更けに、と近づきかけて太郎兵衛は足を止めた。
星の光を受けて腰まで水につかり、豊かな黒髪を池の清水で洗っている。水面に映る星影全て吸いこんだような、白く輝く肌をした少女だ。声をかけることも忘れて見惚れる太郎兵衛の首すじに、冷たい刃が突き付けられる。
「姫さまの水浴びを覗こうなんて、いい度胸しているじゃないか」
掠れた、老いた猫のような声である。
「姫さま……、いずれの?」
「お前のような下郎に教える義理はないね。死ぬ前にいいものを見たと感謝しな」
喉元に当てられているのは、巨大な鉄の爪であった。首筋を引き裂かれる寸前、太郎兵衛は腰を落として足を蹴りあげ、相手と距離をとる。
そこには巨大な猫がいた。両手に鉄の爪をつけ、背筋を丸めて牙をむき出しにして彼を威嚇している。太郎兵衛は腰に吉光の短刀を挿しているだけだ。
「覗くつもりはなかったんだ」
「でも姫さまの体を見たろ?」
頭の中に白い肢体が甦った刹那、鉄の爪が一閃した。懸命に抜き合わせ、激しい音が鳴る。だが、不思議なことに、池に入っている少女はうろたえることもなく、沐浴を続けている。太郎兵衛はその剛胆さに感心する。もう一度、その姿を見たかったが、
「二度と見せないからね!」
と化け猫の鉄の爪が襲いかかり、振り返ることを許さない。何度か二人が火花を散らしているうちに、
「お玉、帰るよ」
と声がかかった。太郎兵衛が声のする方に目をやると、ほっそりした体つきの若武者が栗毛の馬に跨っている。侍の格好をしているが、その顔は間違いなく、先ほどまで沐浴をしていた少女のものだった。
「命拾いしたね」
お玉、と呼ばれた怪物のような娘は爪をしまうと、若武者の後に続いて姿を消す。太郎兵衛はただ呆気にとられて見送るばかりであった。
七
寅の刻となった。
夜明け前の闇がもっとも深くなる瞬間、先に銃火を放ったのは、岩石城の方であった。それを合図に、吉成は鬨の声をあげさせた。攻める側も、守る側も、完全に目覚めていた。
「蒲生勢も動き始めています」
物見の兵が報告すると、吉成は銃卒たちに火縄をかけさせた。
「闇雲に撃つな。柵や門に当たっても弾の無駄だ。向こうがどこから撃っているのか見極めて、よく狙え。そして一度狙いを定めたら、今度は相手の気が萎えるまで撃ちまくれ」
そう命を下す。
双方の激しい銃撃が続く間、槍兵たちは押し黙って折敷いている。功に逸る蒲生氏郷の部隊が森隊の横を駆け上がっていくのをじっと見守っていた。
「父上、我らも早く行きましょう」
このままでは城攻めの手柄が全て蒲生側に奪われてしまう。太郎兵衛はそれを心配した。氏郷は清洲会議の時から秀吉に味方すると旗幟を鮮明にして寵愛を受け、伊勢十二万石を与えられている。動員している兵数も森隊よりずっと多かった。
「まだだ」
吉成は本陣でじっと腕を組んだまま動かない。
部隊の先頭に並べた銃隊は激しく城の守兵と撃ちあっている。蒲生隊から激しい喊声が聞こえ、声の源は徐々に山の上へと上がっている。
「小三次」
他の将領たちも、吉成に迫った。
「四国勢の過ちを繰り返してはならん」
仙石、長宗我部など四国から豊後に攻め入った者たちは、中国勢や筑前を守った者たちに比べて大いに面目を失った。戦機を失っては、一番隊の栄誉もなかったことになる。
だが、周囲がどれほど迫っても、吉成は突撃の命を下さない。
「太郎兵衛、様子を見てこい」
吉成は後ろに控える息子に命じた。そして、
「蒲生隊は勇敢に戦うだろうが、必ず一度は押し戻される。その気配を察したら報告するのだ」
と耳打ちした。
「俺も行こう」
犬飼九左衛門も立ち上がり、吉成は頷く。
太郎兵衛は父の指示に首を傾げながら、銃火が行きかう正面を避け、蒲生隊からも距離を取って城に近づいた。戦は激しさを増しているとはいえ、尾根を一つ越えれば静かな闇が広がっているばかりである。
「落ち着いていますな」
九左衛門は太郎兵衛の武芸の手ほどきをしてくれていたが、太郎兵衛が吉成について土佐に行って以降、稽古をつけていない。
「二年ほど見ない間に気配が変わった。強き者たちに会われたな」
太郎兵衛はこくりと頷く。石合戦に明け暮れている頃は、周りが弱く見えて仕方なかった。だが、天下には強き者が多くいた。そうなりたい、と思う男たちが綺羅星のごとくいる。真の戦の中で鍛え上げられた男たちには、全く敵わない。
だから太郎兵衛は、戦に何があるのかを知りたかった。
「どうして父上は、蒲生の軍が一度退くと言ったのだろう」
吉成が暗闇の中で、味方の動きを読めるのは何故か、わからなかった。
「殿の凄さは、少ない手掛かりから正しい答えを導き出す力です」
しばらく考え、九左衛門は吉成の力をそう評した。
「黄母衣衆として大名たちと交渉し、使者として敵陣へ乗り込み談判を行えば、過ちは許されない。一つの過ちが何千という命を散らすことになりかねない。敵や味方の機微を読みながら、正しき方へことを進める術を極めているのでしょう」
「まだわからない……」
「俺だってそうです。だが、あなたは殿の子だ。できぬ筈がない」
尾根を登りきると、蒲生隊が城の大手に迫り、激しく撃ち掛けているのが見えた。城からの反撃も激しい。夜襲だけに松明を焚いているわけではなかったが、城のあちこちには篝火が煌々と輝き、寄せ手を照らしていた。
城の銃卒は蒲生隊に砲火を集中させている。多くの兵が柵に取りつく前に倒れ、柵を登りかけた者たちは上から矢で射られるか槍で突かれるかして息絶えていく。
しばしそのような攻防が続き、攻め手の気が挫けたように見えた。
「戻ろう」
太郎兵衛が尾根を下りようと九左衛門を促した。
「波を見ましたか」
「そんな気がする」
木立の中を駆け抜けて父のもとに復命すると、吉成は腕組みを解いて全軍に命じた。
「蒲生隊が一度退いた頃合いに城大手の直下まで足音を潜ませて進め。そして一気に攻め込むぞ」
吉成は激しく続けさせていた銃撃を止めさせ、全員の足もとに藁を巻かせて山を登り始めた。喧騒に包まれていた岩石山に一瞬の静寂が訪れる。
「父上、あれは……」
太郎兵衛は山の下から伝わってくる微かな地響きに気付いて振り返る。巨大な光の塊が添田一面に広がっていた。
「殿が尻を叩きに来ているのだ」
吉成は振り返ることもしない。
「あの光を見れば、蒲生と前田は奮起して再び攻勢に出るだろう。城方もあの本隊が攻めのぼってくるまでに束の間の休息を取ろうとするはずだ。そこを狙う」
城の搦め手からひっきりなしに喊声が聞こえてくる。秀吉本隊の動きに気付いた前田利長が突撃を再開しているらしい。吉成は後方から蒲生隊が再び山を登って来ているのを確かめると、初めて大音声で攻撃を命じる。
搦め手に気をとられていた大手の兵たちが慌てている間に、多くの兵が門にとりついていた。激しい銃火の中を、門が内側から開く。
「先陣は森小三次吉成の隊がいただいた!」
兵たちがそう叫びながら城内へと躍り込む。城方も懸命に防戦する中を、太郎兵衛も吉成も槍をふるって突き崩す。だが、その中を別の大音声が響いて来た。
「岩石城への先陣、蒲生松ヶ島侍従氏郷なり!」
太郎兵衛が驚いて振り向くと、鯰尾の銀兜が間近に見えた。蒲生氏郷が大槍を担ぎ部隊の先頭となって城内へ走り込んでいく。
「小三次どの、ご苦労!」
爽やかに声をかけると、近習たちと共に敵兵の群れの中へと雪崩れこむ。それはいいのだが、口々に先陣は蒲生と叫び続けるのが太郎兵衛には不快である。太郎兵衛が氏郷の後を追おうとした刹那、苦笑した吉成の口から出たのは、
「退け」
という命であった。
八
岩石城は、一日のうちに落ちた。
島津に味方することで三十万石相当の領土を勝ち得た秋月種実は、天下の力を思い知らされた。彼は反撃の機会をうかがって、古処山城を出て、秀吉の本陣に近い益富城にまで軍を進めていた。
岩石城が堅く守っているうちに、秀吉の側面を衝くつもりであった。だが、堅城と自負していた城が落ちたことに驚いているうちに、十万を超える兵が益富城に迫っていたのである。その報を聞いた種実は、島津に救援を求めると共に本拠地の古処山に戻った。
当然、益富城には火をかけ、敵に使われないようにすることも忘れない。だが翌日、種実は目を疑った。焼き払ったはずの益富城がそのままの姿で建っていたからである。それははりぼてと松明の灯りによってできた幻の城であったが、種実には真実を確かめる術もなかった。
一夜城だけでなく、その周囲を埋め尽くす大軍勢が彼の心をへし折ったのである。
「何とか一族の命を助けていただけないか」
内々に黒田孝高に問い合わせがあった時、吉成と太郎兵衛もその陣屋にいた。孝高は先陣を切って岩石城の大手を破ったのは吉成だと知っていたが、蒲生氏郷から先陣の功績は我らだとの申し出があったので真偽を確かめるために二人を呼んでいた。
吉成は、先陣の功について何も言わず、太郎兵衛にも余計なことは言わせなかった。ただ、
「蒲生どのには養う者も多いでしょうから。私は殿の兵をお借りして働いたのみだ。我が兵たちの功だけは認めてやって欲しい」
そう孝高に告げた。その言葉を聞いて含むところを悟った孝高は頷く。
「表立っては、蒲生と前田の功とするが、よろしいな」
と念を押す。
「まだまだ先は長いですからな」
孝高は片眉を上げ、そうとは限らん、と言う。
「小三次どのは、関白さまが何故岩石を一日で落とせと仰ったかご存じか」
「もちろん。九州が平らげば東国が残っておりますからな」
満足げに頷いた孝高だったが、太郎兵衛は妙な気分だった。まだ豊前の入り口で一勝を挙げたのみである。だがもう、九州の戦は終わったような話を二人はしている。
「太郎兵衛、これが関白さまの戦いだ。一戦で全てを終わらせる。これほど美しい戦をする方はいない。よく憶えておくがいいよ」
孝高は上機嫌であった。
「さて、秋月からの申し入れをどうするかな」
楽しげに、その書状を吉成に見せた。
確かに、孝高の言った通りになった。
北九州に猛威をふるった秋月種実はわずか数日で降伏し、秀吉が快く許したことも話題となっている。散々な目にあわされた大友宗鱗や立花弥七郎の気が済むわけがなかったが、秀吉は二人の膝を抱くようにして宥め、不満を言わせなかった。
秀吉の秋月種実に対する穏健な態度は、島津についた諸将の心を大いに動かした。逆らえば数日で滅ぼされるが、降れば必ず許される。となれば許される方を選ぶのは当然である。
日向や肥後では散発的な戦闘があったものの、秀吉軍は瞬く間に豊後、日向、肥後の諸城を抜いて薩摩へと軍を進めた。島津義久は本拠地の薩摩で頑強な抵抗を試み、確かにある程度の足止めには成功した。だが、兵力差は圧倒的で敗北は免れない。
秀吉は島津を滅ぼすか、迷っていた。
「追い詰められた島津は厄介だ」
と考えていた。秀吉からすると、苦境と見るや惜しげもなく命を捨てるように見える島津の戦い方は脅威であった。肥後を経由して川内に入っていた秀吉は、まだ島津義久の本隊とは戦っていない。
豊後の府内にいた義久は秋月種実が降伏すると見るや薩摩に撤退し、守りを固めていたのである。
秀吉の帷幕でも、意見は分かれていた。だが、島津との取次を務めていた石田三成は島津を討ち滅ぼさぬように進言した。島津は信頼するに足ると弁じたのである。
秀吉は一通り意見を聞いたうえで、三成の案を採った。
「ここで島津を滅ぼしてしまえば、確かに九州は静かになるかもしれんが、どれほどの損害が出るかわからん。島津は腹を括れば歯だけになろうと噛みついてくるぞ。平佐城のような戦いぶりを薩摩全土でやられてはかなわん」
平佐城には桂忠昉が篭って最後まで頑強に抵抗し、秀吉を手こずらせた。
秀吉はもちろん、硬軟両面で準備を進めている。根来攻めの際に仲介の労をとってくれた高僧、木食応其を使者に立て、義久に降伏の打診をしていた。木食応其からは、
「関白さまの慈悲を見て降るかもしれません」
との感触が報じられていた。
島津が求める「慈悲」の内容は、もちろん一族の助命だけでなく、領土の安堵も意味していた。
「図々しい」
と最初は秀吉も怒ったが、
「毛利や長宗我部も我らと激しく遣り合っていましたが、恭順な態度を示せば許すのが殿のやり方ではありませんか」
九州で交渉に当たっていた三成にそう言われて、秀吉も考えを変えた。
「なるほど。義久もそのあたりを見抜いて、したたかに交渉しておるのだろう。こちらの言い分はただ一つだ。反抗を止め、義久が出家すれば、薩摩、大隅を安堵する。それ以上のことを望むのであれば談判は無用である」
これが秀吉の出した最後の条件であり、島津義久もついには受け入れた。薩摩の各所で抵抗する動きが出たが、義久は自ら説得して回り、双方ほとんど出血することなく、薩摩は平定されたのであった。
秀吉は薩摩の国内を悠々と巡検して力を見せつけた後、国分けを行った。
薩摩、大隅を島津、日向を古処山で降伏した秋月種実、その際に攻城の先鋒を務めた高橋元種、丸目長恵の旧主である相良氏に分け与えた。
それを皮切りに、肥後を佐々成政、豊後を先だって死去した大友宗鱗の子、義統に。小早川隆景に筑前、筑後の二カ国を授けた。
黒田孝高に豊前六郡、立花宗茂には筑後柳川、肥前は古くから力のあった大村、竜造寺、松浦の諸氏に分け与えられている。戦で混乱をきたした博多の復興は、石田三成らに任された。
そして森吉成には豊前小倉を中心とした二郡、およそ六万石、そして太郎兵衛にも、豊前の一万石が与えられることとなった。
九
秋七月になって小倉に入っても、父の馬丁から万石もちの大名になるという大出世の意味が、太郎兵衛には今一つわからなかった。
吉成は秀吉の命に従い、権兵衛吉雄に一万石、犬飼九左衛門を一門に加えて香岳山城を与えるなど足元を固めつつあった。杉助左衛門、宮田甚之丞は侍大将となり、麗々しい陣羽織を太郎兵衛に見せにきたほどである。吉成は博多から師を招いて茶の湯を始めた。
「お嫌いなのかと思っていました」
太郎兵衛がからかうと、
「付き合う相手の間に流行っているからな。それに殿のお許しも得た」
苦々しい顔つきながら、見事な手つきで点前をこなしてみせた。
「あとは碁と将棋だな。お前には茶の湯はまだ早いが、盤上では一人前にふるまえるようにしておけ」
と命じた。だが吉成は、茶の湯も碁もする暇がない。秀吉は反抗的だった国人たちの領地を没収し、吉成に与えた以外は蔵入地として直轄地にした。検地の備えを行い、そこからもたらされる米などの産品を大坂に送るのも、吉成の仕事である。
だが、いずれも太郎兵衛にはまだ難しすぎる仕事ではある。まさか父親の馬の世話を続けるわけにもいかず、手持無沙汰であった。
「どうすればいいの」
一番身近な城主の跡取り経験者といえば、近侍に加わってくれた利光統久である。
「普段通りにしておけばいいんじゃないの」
太郎兵衛の戸惑いを楽しむかのような顔つきで統久は答えた。
「一万石を与えられた、とはいっても実際は小三次さまが政を行うんだから、あまり気負う必要はないよ」
「そ、そうかな」
秣と馬糞のしみついた馬丁の服は、もはや捨てられている。代わりに着せられたのは、紺地の小袖である。肌触りからしてまるで違い、くすぐったいほどだ。
「でも太郎兵衛はこれから大変だよ」
統久は気の毒そうに言った。
「俺たちは太郎兵衛と小三次さまが豊前でどれほどの働きを見せたか知ってる。でも、多くの国人や大名たちは、無名の武者がいきなり万石の大身となって、豊前の、いや九州の要を治めるようになったことに驚いているはずだ。注目を浴びるよ」
人目を気にして暮らすべきだ、と統久は説いた。
「俺も一応城の跡取りだろ? だから馬鹿にされないように励んだものだよ。鉄砲がこれからくるだろうと思ったから、懸命に鍛えたもんさ」
確かに統久の射撃は誰もが認める腕前である。
「武芸だけがあればいいってもんじゃない。太郎兵衛の印地打ちは大したもんだけど、それよりも四国勢退き陣の時に軍を率いたとか、土佐侍従さまに刀を授けられたとか、そういう経歴の方がものを言うから、言いふらすといい」
「やだよそんなこと」
太郎兵衛は顔をしかめた。自慢するようなことではない。
「だったら、俺たちが言いふらす」
「止めてくれ」
「悪い事じゃない。豊前の国人たちは、関白さまから送り込まれた森小三次親子がどんな人間か知りたがってるんだ。どうせなら良く知ってもらう方がいい。妙な噂が流れて国が乱れたら、それこそ厄介だ」
ただし、
「これから一気に金回りがよくなるけど、身を持ち崩すなよ」
と統久は付け加えた。
最初は意味がわからなかったが、すぐに理解した。小倉城の前には商人たちが市を成すようになり、周辺から集まる物資や人でごった返すようになった。城には秀吉からの使者や、蔵入地の検地に出張ってきた役人たち、港に入ってきた明国の商船長や、はては南蛮人までもが出入りし、吉成はその応対で茶を飲む暇もない。
それに加えて、あらたな大名のもとで一旗揚げようと牢人たちまで集まってくるのだから、喧騒はとどまるところを知らなかった。
しばらくして吉成は、
「街が騒がしい。お前は先頭に立って騒動が起きないよう見て回れ」
と太郎兵衛に命じた。
馬に乗り、小倉の街をゆく少年武将を、人々は眩しげに見上げていた。そんな視線がくすぐったくて仕方がない。新しい町は血の気の多い男たちを呼びよせ、喧嘩騒ぎも後を絶たない。だが、太郎兵衛の姿を見ただけで、多くがこそこそと逃げ出す。
店をかけている者は口々に寄って行けと誘い、茶なり菓子なりをご馳走してくれる。中には金や銀をこっそり袖の下から渡そうとする者もいた。
「受け取っちゃだめだ」
あまりの心地よさにぼうっとしていた太郎兵衛の背中を、統久は叩く。
「くれるって言ってるのに」
「何故くれるんだ。小倉城主の跡取りになるはずのお前がそれを受け取れば、渡した方は当然のように見返りを要求する。一つ賄賂を受け取って応えてしまえば、あの若君は袖の下で動くという評判がたつぞ。よその地から来た者への目は厳しいんだ」
そうだった、と太郎兵衛は慌てて金を返した。袖の下を贈ろうとした商人は苦々しい顔で統久を睨みつけるが、
「太郎兵衛さまを賄賂でたぶらかそうなど、無礼千万。殿は公平無私、関白さまの命によって小倉をお治めなされ、偏りなく政を行われる。勘違いするな」
と一喝した。
その一喝は自分に向けられたものだ、と太郎兵衛は背筋を伸ばしたが、気分がいいことには変わりなかった。

第六章 国持ち
一
九州を屈服させた秀吉は、既に先を見ていた。
小早川隆景に筑前、筑後など三十七万石、立花宗茂に筑後柳川を中心とした十三万石、森吉成、太郎兵衛に豊前小倉周辺合わせて七万石、黒田孝高に豊前中津など十二万石を置いた。
九州の出入り口を固める一方で、薩摩は島津義久、大隅は島津義弘に与えて安堵し、そのすぐ北に位置する肥後には、古豪である佐々成政を送り込んで支配の強化を進める方針を示した。
懸案の東方に対しても秀吉は抜かりなく手を打っている。島津攻めの前に家康を伏見に招き、彼が応じるという形で天下に関係の改善を喧伝できた。だが、東海から東の関東には北条、そして東北には伊達と、秀吉に服従を誓わない大勢力がまだ存在した。
戦いを進める経済的な基盤は、領土である。秀吉は直轄領である蔵入地を西日本を中心に広くおき、その石高は二百万石に近づく勢いであった。
九州でも敵対した国人たちの領土を没収し、さらに味方した者たちにも国替えを命じたり、秀吉が派遣した武将の直接の家臣、給人になるよう奨めている。そうして得た蔵入地の管理も、九州に派遣された武将たちの使命であった。
豊前小倉は長州下関から関門海峡を越えて間もなくのところにある、九州の玄関にあたり、まさに要地中の要地であった。北に九州と本土を隔てる海、東に妙見山、西に石峰山、南西から南方にかけても山並みが続いて天然の要塞ともなっている。
九州での論功の席で、秀吉は吉成の働きを激賞した。四国勢を導いて最後まで九州に残り、先鋒を務めては岩石城の攻略に力を尽くし、肥後表でも先頭に立ち続けた功は、数万石に値すると言って、小倉を与えたのである。
「殿は見ていないようで、見逃すことがない」
岩石城での功第一は、蒲生氏郷ということになっていた。秀吉もそう公言していたし、吉成も不平を態度に出していない。
だが、吉成のこれまでの働きを知る者たちは、一躍六万石を得たことを我がことのように喜んだ。真っ先に訪れたのは、黒田孝高で、
「どうだ。あなたの働きはもっと大きいのだが、見えない功績を誉めたたえることは難しくてね」
まるで己が口を利いたおかげとでも言わんばかりの得意顔を見せた。吉成は素直に礼を述べる。一方で、さらに無邪気に喜んでくれたのは後藤又兵衛であった。
「もう軽々しく太郎兵衛なんて呼べないな。関白さまから直々に一万石をもらうとは、なんて果報者なんだ」
又兵衛は仙石秀久の失脚と共に、黒田家に帰ってきていた。
黒田家も城井氏ら国人衆が治めていた豊前六郡十二万石を与えられて日の出の勢いである。秀吉は自らの手で育て上げた諸将を積極的に登用するようになった。加藤清正、福島正則、石田三成、小西行長、大谷吉継など秀吉の小姓上がりが秀吉の名代となって諸大名の拝跪を受けたり、大軍勢を率いるようになっていた。吉成親子が一足飛びに見えるほどの出世を果たしたのも、その流れの一環であった。
「六万石、か」
と吉成は呟く。
「殿もいきなり大きな荷を背負わせるものだ」
首を左右に倒して音を鳴らした父の横顔は、これまでになく疲れていた。
「大きな荷?」
「郎党百人ほどの黄母衣衆がいきなり親子合わせて七万石の城主だ。殿から預けられた蔵入地も含めれば十万石を超える。それだけではない。ここ小倉に俺を置いた理由は、九州全体に目を配れということだ」
「誇らしいことです」
大名となることが決まった後の森家の喜びようは、尋常ではなかった。叔父の権兵衛と一族となった九左衛門はいつもの謹厳な顔を崩して酔いつぶれ、二人して城の濠に落ちたほどである。
「誇らしい?」
吉成は無精ひげをばりばりと掻いた。
「畿内や東海は総見院さまや殿のおかげで随分と治めやすくなった。だが九州は無数の国人がいて、その相手もせねばならん」
吉政が頭を痛めているのは、国中に散在する国人領主たちである。一村、一郷を守って代々に土地に根付いてきた彼らと、秀吉が進める天下統一とは衝突せざるを得ない。特に秀吉の行った検地は、貢租の取り立てを円滑にするために、複雑だった村落の境界線や飛び地を整理した。
国の隅々にまで検地の網を張り巡らせ、年貢の納入先は秀吉から認められた領主とされたことで、これまで何代にもわたって守ってきた権益を損なわれた、と反発する国人も少なくなかった。
秀吉が目指しているのは、安定した貢租の徴収であり、領国化である。一方で、服属を誓った国人衆には本領安堵の朱印状も多く出している。安堵を約束されれば、これまでと変わらず、国人領主として振舞えると思うのはある意味自然だ。
その両者の思惑のずれが軋轢の種となるのは、吉成にもよくわかっていた。
「検地をどう納得させるか……。名案はあるか?」
吉成が太郎兵衛に訊ねるほどだから、いい案は出ていないようだ。
「我らはこのあたりに馴染みがないしな。馴染みがなければ、中々素直に言うことを聞いてはくれん。お前もこのあたりの娘を娶って、地の者の心をほぐしていかねばならん。竜造寺家から娘を娶らないか、という話が来ている。豊前の戦いで我らに与力した軍勢を率いていたな」
吉成はふと考え込んだ。
「お前、その娘のことをどう思う」
「どうにもこうにも、知らない人です」
「嫁をもらうのは嫌か」
太郎兵衛が首を傾げていると、吉成は何か一人納得した様子で、城へと戻って行った。
二
国人衆としては、従属はするが臣従はしないというのが本音である。秀吉から本領を安堵されている以上、協力して兵を出し、役務も果たすが、その家臣になった覚えはないのである。
それはもちろん、吉成と太郎兵衛が配された豊前小倉でも状況は同じだった。名が必要だ、と吉成は考えた。
「これから小三次は毛利を名乗れ」
と秀吉が言い渡した時は、さすがの吉成も仰天した。
「森は毛利と似ているからな」
吉成は、豊前の国人衆を家臣へと組み込むにあたって、秀吉と慎重に策を練っていた。新しい主と政への激しい拒絶が、九州の国人たちにはあると彼は見ていた。だから、
「馴染みと重みのある姓をいただきたいのですが」
と吉成が秀吉に願い出てはいた。すると即座にそう答えが返ってきたのだ。
「豊前を島津から救ったのは毛利だ」
秀吉の言葉に吉成は大いに感服した。
「しかし安芸中納言は私のような無名の人間に、姓を貸し与えてくれるものでしょうか」
「小三次よ、お前は己の名を小さく見過ぎている」
こうして話している間にも、何人もの小姓が出入りしては使者の口上や報告を上げてくる。それにすぐさま答えを与えながら、吉成に対しているのである。
「小さく、ですか」
そうは言われても、実際にこれまでほとんど無名だったのである。
「わしの名代として長く働いていたのだから、小倉の城主になってもそれは変わらぬ。お前はわしの代わりとして振舞い、己の言葉をわしの言葉と思って人々に対せばよい」
傲慢に聞こえる言葉だが、そうではないことを吉成は誰よりも理解していた。秀吉は気遣いの人である。敵であろうと味方であろうと、相対する者が何を求めているかを瞬時に理解する。信長のような主君に尽くした秀吉ならではの技量であった。
「豊前の衆がもっとも敬愛しているのは、島津と勇敢に戦った者だよ。毛利にはわしからよく頼んでおくが、小三次は太郎兵衛を連れて挨拶に行け。あと、息子には竜造寺の娘を嫁がせるがいい」
そう指示した。竜造寺は武名を馳せた隆信が戦死を遂げてから、家運は衰える一方であった。かつて九州北部を席巻した勢いは消え果て、今では家老の鍋島直茂に権力を握られていた。
「小倉七万石、九州探題としてわしに信任されている小三次と姻戚になるのは、竜造寺家にとっても悪いことではあるまい」
吉成は黙って頭を下げた。太郎兵衛の結婚など考えたこともなかったが、秀吉の許しも出たなら何も言うことはない。
ともかく、吉成は太郎兵衛を伴って吉田郡山の毛利輝元のもとへと向かった。
吉成は道中でも毛利家の使僧である安国寺恵瓊と頻繁に書状を取り交わし、手順を詰めていく。恵瓊は、
「何か取っ掛かりがあると話が進めやすいのですがな」
と言ってきたが、吉成が自家が大江氏の末裔と称していると返事をすると大いに喜んだ。毛利氏も大江氏の裔ということになっていたからである。その後は、万事障りのないように、輝元と話を進めてくれていた。しかし、問題が一つ起こった。
「又二郎どのが反対しているのか……」
又二郎とは吉川広家のことである。周防と安芸の境まで来た辺りで受け取った手紙を見て、吉成は顔をしかめた。九州征伐において、吉川家は当主の元春、嫡男の元長が陣没したために、三男の広家が跡を継いでいる。
「不都合があるのですか」
「どうにも、御坊と仲が悪いようだ」
広家は毛利家を支える両川、小早川、吉川の一翼を担う武将として重きをなしている。毛利家当主の輝元は従兄にあたる。月山富田城を拠点に十六万石を領している彼は、安国寺恵瓊のような坊主に政を牛耳られているのが面白くない。
「恵瓊師が賛成することには反対したくなるらしい」
「子供のようです」
太郎兵衛は思わずそう評した。
「子供でも力を持てば無視するわけにはいかん。ただ、子供には子供の対し方がある」
吉成は考えた末に、恵瓊に一通の手紙を送った。内容は、吉田郡山を訪れる前に、秘かに月山富田城に広家を訪ねる、というものであった。
「順序が逆では……」
「一人前の男なら道理を尽くせば納得する。安芸中納言も恵瓊師もそうであろう。だが、幼い者は道理よりも目の前の喜びを大事にするものだ。我らがまず挨拶に来たとなれば、満足する」
という吉成の言葉は見事に的中した。
「ひそかに、ということであれば大したおもてなしもできないが」
広家は厳めしい顔に嬉しさを隠しきれない様子で二人を出迎えた。
「まずはこちらに挨拶に出向かれるとは、毛利の家中のことをよくご存じだ。さすがは黄母衣衆にその人ありと言われた毛利小三次どのである。いや、まだ森どのであったな」
そう誉めたたえた後に、
「恵瓊師はさぞやお怒りではないか」
と上目遣いに訊ねた。
「いずれ郡山に着くのであるから、道中どこに立ち寄ろうと気にしないと」
「そうか、そうか。あの渋面が目の前に浮かぶようであるな」
愉快そうに広家は哄笑した。興が乗ってきた広家が、一軍を出して護衛をつけるというのを何とか断って、吉成たちは静かに郡山に入った。
「何度見ても手強そうな城だな」
と吉成が呟くほどの堅固な城である。江の川と多治比川の合流点を天然の掘割とし、独立峰一つを二百を超える曲輪で守った一大城塞だ。
「これが中国の覇者の城……」
太郎兵衛も百万石を超える力を大坂以外で初めて目にし、大いに驚いた。
「この力を我々が自由に使えるとなれば、天下も安らかになろうものだ」
先に広家を訪ねたことに対して、輝元も恵瓊も何も言わない。丁重に挨拶をし、姓を使わせてほしいと願った。
「関白さま入魂の仰せであり、数ある名家の中から我らを選んでくれたのは喜ばしいことである」
遅れてやってきた広家も含め、反対する者はいなかった。
「小三次のような勇者がわが一門に加わってくれて、我らも誇りに思う」
その輝元の言葉は吉成を感激させた。
いきなり姓を貸せと言われて、愉快なはずはないのだ。だが輝元も一門衆も、吉成に対して決して嫌な顔を見せなかった。中国の覇者の度量を見せつけられた思いで、吉成は丁重に礼を述べる。
「もし安芸中納言さまに事あれば、我ら一族命を賭して駆けつけまする」
との言葉に、輝元は鷹揚に頷いた。
「毛利の名はめでたくいただけた。次は実だ」
吉成が太郎兵衛にまずやらせたのは、新しき小倉城の縄張りであった。
「そんなのやったことないですよ」
慌てて太郎兵衛は手を振る。これまでとは違う、肌触りのいい絹の小袖が肌にくすぐったい。麻の粗末な服はもう着るな、と父に命じられている。
「やったことのないのは知っている。俺だって初めて持つ城だ。だがやれ。お前はもうあちこちで城を見てきただろう。長浜、姫路、大坂、土佐、豊前の鶴賀、筑前の岩屋、立花と見聞は広まっているはずだ」
父は命じるだけ命じると、小倉を出ていった。九州のことで秀吉と協議せねばならないことは山ほどあった。
一方の太郎兵衛は城の縄張りをせよと言われて途方にくれた。留守を任されている叔父の権兵衛と家老の九左衛門に泣きついてみるが。
「お前に城の縄張りをしろと兄上は言ったのか。それはさすがに無茶だな……」
叔父も首を傾げた。しばらく難しい顔をして考え込んでいたが、はたと手を打った。
「命じられたからにはやって見せねばならん。だが、一人でやれとも言われていないはずだ。城のことに詳しい者に訊けばいいではないか。誰か心当たりはないか」
そう言われて太郎兵衛も考え込む。
「父上は長浜から始まって、大坂や鶴賀や立花の名前を出していたけど……」
「小倉は言うなれば、関白さまの出城だ。九州の諸将にその強さを見せつけるものでなければならない。だから大坂みたいな城がいいのではないか」
権兵衛はそう言ったが、
「いや、城を守るには山城が有利だ。立花や岩屋の奮戦ぶりから見ても、山に拠るのがいいと思う」
九左衛門はそう言って反対した。
小倉は周囲を海、山、川と囲まれているが城自体の守りは堅くない。半日考えても結論が出なかった太郎兵衛は、宮田甚之丞と杉助左衛門に帯同を頼み、豊前中津へと向かった。
「城とは胸が躍りますな」
最近豪傑ひげをたくわえ始めた宮田甚之丞が楽しげに言った。
「あくまで関白さまにお預かりしたものであることを忘れてはならぬ」
と杉助左衛門がたしなめる。そう叱りつつも、助左衛門も嬉しそうではある。
中津は黒田孝高が本拠としているところで、瀬戸内の海岸線に沿って馬を走らせれば半日ほどで着く。中津へ至ると、こちらもちょうど城を築いている真っ最中であった。まだ塀や矢倉は完成していなかったが、その縄張りはわかる。
中津川を背にして本丸があり、その左右を守るように二の丸と三の丸が南北に設けられている。ちょうど広げられた扇のように、攻め手を防ぐ構造となっていた。
「その地にあった城というのがある」
孝高は忙しい手を止めて、城の隅々まで案内してくれた。
「ここ中津は水が豊かに使える。川は天然の要害であるし、本丸と二の丸、三の丸の間に濠を巡らしておき、矢倉に銃卒を置いておけば敵は本丸に至るまでに全て討ち取ることができるだろう」
自らの縄張りに絶対の自信を持っている、という顔である。だが、小倉のことは知らん、とにべもない答えである。
「城はその地を任された者の器量で造る。城を見れば、戦わずして将の力がわかるというものだ。大坂を見よ。関白さまのお人柄が明らかにわかるだろう」
壮大にして周到、そしてきらびやかな秀吉の性分そのままの城といえた。
「小倉は太郎兵衛とその父で造る城なのだから、お前たち自身を城にすればいいのだ」
そう助言した。
「俺たちを城にする……」
「何のために小倉に来て、何を為すかを考えれば、自ずと形は見えてくるはずだ」
「父上は関白さまの名代として小倉にいて、九州で戦が起こらないようにしたいと言ってました」
「だったら、まず諸将にその気を起こさせないような造りにすべきだな」
小姓に帳面を持ってこさせた孝高は、小倉の地形をざっと描いた。筆に慣れている彼らしい、流麗な筆致である。たちまちのうちに小倉の山河が再現されていく様を見て、太郎兵衛たちは感嘆した。
「こんなことで感心されては困る」
と言いつつ孝高はまんざらでもなさそうである。続けて、小倉の城に小さな丸を描いた。城の本丸がある位置にほぼ違わない。
「よく憶えていますね」
「わしは中国勢の仕切りをしながら九州に上陸したんだぞ。小倉は路地の隅々まで頭の中にある」
筆尻で己の頭を指した後、筆先を太郎兵衛に向けた。
「さあ、どう縄張りする。できるかできないかは別だ。太郎兵衛が思う通りに言ってみよ」
父と合わせて七万石の城といっても、どの程度の大きさにすればいいのかわからない。だが、戦となれば百姓たちが右往左往しているのが印象に残っていた。府内では島津が攻め込んでからひどい略奪にあった家々も目にしている。
「攻められた時に、皆が城に篭ることができたらいいです」
「となると、諸篭りか。小倉は大きな町だから、そうとう大きな構えを作らねばならんぞ」
「町ごと囲ってしまうのは?」
筆を止めて驚いた孝高だったが、
「確かに、大坂は町の半ばを囲っているな」
そう言いつつ本丸を中心に大きな円を描いた。だが、ただ円を描いているようで、川や地形などを考えて微妙に形を整えてある。
「となると、やはり水を上手く使った方がよかろう。曲輪を一から盛り上げていくのは人手も時間もかかる」
小倉城の西に流れる紫川から三本の線を引いて見せる。
「こんな感じでどうだ。中津の城と大きさを揃えてみた」
だが太郎兵衛はもっと大きくとせがむ。孝高が何度か描き直したものを見て、太郎兵衛はようやく頷いた。初めの絵からは随分と大きくなり、紫川と市街の西に流れる板櫃川に至るまでのほぼ全ての地が濠によって囲われた形となった。
「随分と大きくなったな」
孝高は絵図面を持ち上げると、向きを変えたりして何度も何かを確かめていた。
「本当にこれだけの城が築けるかどうかは小三次どのの采配だから置くとして、わしならここに櫓を置いて、狭間はこうやって……」
と孝高の方が城の指図に夢中になり始める。太郎兵衛も横からあれこれ口を挟んでいるうちに、城の見取り図は何枚も床に散らばっていた。外を見れば、日が暮れようとしている。
「興に乗っているうちに一日を無駄に使ってしまった……こともないな。小倉城の縄張りを手助けしたというのは、十分に務めを果たしたと言えるな、うむ」
誰に言い訳をしているのか、そう口にした孝高は、今日は泊って行くように言った。
「城もまだ造りかけゆえ、城下の寺を宿にしてくれ。おおい、又兵衛」
孝高は後藤又兵衛を呼ぶ。どすどすと廊下を踏み鳴らして、熊のような大男が現れた。
「太郎兵衛、殿について城造りを学ぶとは殊勝だな。殿の縄張りは大したもんだぞ」
「城の良し悪しもわからん男が偉そうなことを言うでない。ともかく、太郎兵衛たちを格林寺に連れて行ってやってくれ。あそこなら部屋が空いているだろう」
と城下の寺に案内させた。
「法華の寺だよ。あそこの坊さんはもともと侍だったらしいが、仏門に入って今は辻説法三昧だ。小僧もあまりいないようだから荒れているかもしれんが」
荒れていようが、屋根のあるところで眠れるだけありがたい。太郎兵衛は小倉に来てからの出来事を楽しく話しつつ、中津の城から数町離れたところにある寺に向かった。
だが、薄暗い黄昏時だというのに、寺の前で人だかりができている。
「なんだなんだ、喧嘩か」
又兵衛が嬉しそうに身を乗り出そうとするのを止めながら太郎兵衛が様子をうかがうと、やけに背の高い侍と僧侶が激しく言い争いをしている。
「あれ、明石のおっさんじゃないか」
「明石のおっさん……、ああ切支丹の人だ」
太郎兵衛も一度だけ、京の今井邸で伴天連の神を称える調子はずれな歌を耳にしたことを思い出した。十字架を手に口から泡を飛ばしているのは、明石全登であった。
三
又兵衛はしばらく口論を面白そうに見ていたが、
「何を言っておるのかよくわからん」
とすぐに飽きた。人ごみをかきわけて二人の間に入ると、
「宇喜多のご家老がこんなところで争論とは、お戯れが過ぎますよ」
僧侶を庇うように又兵衛が立った。巨体の二人が向かい合うだけで、やじ馬たちはどよめいた。
「又兵衛か。この坊主、辻に立って邪教を声高に触れまわっておるものだから、我慢できずに争論を持ちかけたら逃げおってな。寺から引きずり出してやり合っておったところだ」
そこから延々と伴天連の教義を説き出したが、又兵衛は耳に指を突っ込んでやり過ごした。
「どれほどありがたい教えかは知らんが、格林寺は客人の宿に使うのだ。そこに立たれていては中に入れぬ」
又兵衛の言葉に、全登はこれは失礼と道をあける。そして太郎兵衛の顔を見ると、ぱっと表情を輝かせて、
「森どののご子息か。九州では父子でいたくお働きになったそうだな。小倉七万石へのご出世、祝着至極であります」
と大声で祝いを述べた。太郎兵衛はやじ馬たちの前で大仰に誉められて恥ずかしいやら照れ臭いやらで、思わず顔を伏せてしまった。
「しかも祝言間近だそうだな。重ねてお祝い申し上げる」
そう全登が言ったものだから、今度は弾かれたように顔を上げた。
「祝言? 誰のですか」
「知らなかったのか? 太郎兵衛のだよ」
「誰と?」
「これはしまった。まだ内密にしておかねばならなかったか」
全登は河童の頭のようなてっぺんを叩いて困った表情を浮かべて見せたが、又兵衛にここまで言ったら全て教えろと迫られ、白状した。
「竜造寺の娘ですか……。島津にやられて、今や肥前の一郡を領するだけになってしまいましたが、確かに九州中に聞こえた名家ではありますな」
と又兵衛は鬚をしごいて感心した。
この当時は親が決めた相手と結婚することはごく自然なことであり、年若くして妻を娶ることもおかしなことではない。又兵衛もなるほどと頷いている。だが、太郎兵衛の知る竜造寺の娘は、年若いというのに男勝りに甲冑を身につけ、薄刃の中国刀を振って敵陣に斬り込んでいくような女である。
鶴崎城を守った妙林尼や日出生城で夫と共に戦って名を馳せた鬼御前など、武略に長けた女性も、これまた珍しくない。
「どうした太郎兵衛、具合でも悪いのか」
又兵衛が心配そうに顔を覗きこむ。
「いえ……」
吉成は確かに妻を娶ってはどうかと口にはしていたが、本決まりになっているとは太郎兵衛も思っていなかった。
「私が祝言だなんだと言ったばかりに、驚かせてしまったな。このような大事は一家の主である小三次どのから直接申し渡されるべきところを、横からなし崩しに教えるようなことになってしまい、まことに申し訳なかった」
全登は丁重に詫びた。宇喜多家家老に頭を下げられては太郎兵衛も何も言えない。
「だがな太郎兵衛、竜造寺と縁を結ぶことは決して悪いことではない」
謝罪のつもりなのか、今度はその婚姻の意味を滔々と話しだした。
「先ほどの国人どものこととも繋がるのだが、九州はやはり彼らの力が強い。かつて信長公が明智光秀や丹羽長秀などの諸将に九州由来の姓を名乗らせたのも、彼らに気を遣ってのことだった」
太古の昔から、たとえ中央の権力であっても本土の強権で支配されることを嫌うのが、九州諸侯の特徴だった。島津は乱暴ではあったが、それでも「九州の流儀」をよくわかっていると全登は言う。
「彼らが守りたいものは、実に明快だ。土地と一族だよ」
「それなら我らも同じではないですか」
又兵衛が口を挟む。
「一所に命を懸けて戦うのが侍です」
「その通りだ。官兵衛どのは播州から豊前中津に移されてきたし、四国や中国にも美濃や畿内から移って来た者も多い。そこで与えられた地を守るという天下さまの指図に従うことに慣れている。だが、九州で代々一所を守ってきた者たちは、他所に行くというあたりが理解できない」
「言われてみればそうですな……。だから力のあるこちらの方が辞を低くしてわかってやらなきゃいけないってことですか。図々しいにも程がある」
又兵衛は不愉快そうだが、全登はそれは違うとたしなめた。
「関白さまがお前や官兵衛どのを播州の田舎者と蔑み、兵を送ってきたらどうする」
「それは、死力を尽くして戦ったでしょうな」
「住む地や習わしは違えど、武者である以上己を蔑む者に牙を剥くのは同じだ。毛利が関白さまとあれだけ激しく遣り合ったのに結局は従っているのも、大友どのが最後まで救援を信じ続けて戦ったのも、そこだ。だから九州でも、中国、四国勢に任せず直接手をかけて欲しかった」
だが、秀吉は多忙だった。
「もう御年五十三になる」
既に、主君信長が世を去った年齢を超えた。
「どうも私には、関白さまが焦っておられるように見えるな」
「焦り? あれほど悠然とした戦をされるお方がですか」
「関白さまの恐ろしさは、あの余裕だ。何があっても、もう一段、二段の構えがあると思わせることだ」
中国攻めの際に本能寺の一件を知った時も、毛利方との交渉では一切そのようなそぶりを見せなかった。清水宗治の切腹を検分した時は涙ぐみさえしてのけたのである。それを見た小早川隆景は、京都での一件を知った後も追撃をかけることを躊躇した。
「明智どのも余りの速さと手回しのよさに、己の手が全て封じられている恐怖の中で冷静さを失った。柴田どのもそうだった。駿府の大将ですらも、戦場では決して敗れていなかったのに、このまま長い戦に引きずり込まれては不利だと思うほどのゆとりが関白さまにはある」
だが、天下に敵なしの秀吉にも恐ろしいものが一つある。
「それは時の流れだ。九州でも自ら薩摩に入ってゆったりと回られて行ったように思えるが、後の始末は諸将に任せたきりで東国のことに取りかかってしまった。東でも周到に事を進めておられるが、頭の中は唐入りで占められているように思える。そのようなことでは、必ず過ちが出る」
秀吉は、天正十五年に九州の仕置きを一段落させた後、関東一円を勢力下におく北条氏の対応に追われていた。何とか軍を出すことなく屈服させようと手を尽くしていたが、関東に覇を唱える北条氏側もなかなか従おうとしない。
秀吉の目が東を向いている間に乱が起きるのではという危惧を抱いて、全登は中津へやって来たのである。
「小三次どのは関白さまをよくご存じだ。どうすれば良いか、要点をよく掴んでおられるはず。太郎兵衛に竜造寺の娘をもらい、毛利の姓を頂戴したこともその一環だろう。だが官兵衛どのがあれほど短兵急な方だとは思わなかった。これでは禍根を残すぞ」
矛先が主に向いて、又兵衛はくちびるをへの字に曲げた。
「殿の悪口を言うのは止めていただきたい」
「悪口ではない。国を誤らぬよう、力を貸して欲しかったのだ。九州の国人たちを納得させるのに時間をかけなければ必ず暴発するというのに、官兵衛どのは従わぬ者たちは根こそぎにすると言う」
吉成と官兵衛の方針は随分と違うようであった。
「ああ、関白様を含め、全ての大名がでうすに帰依すればこのような憂いもなくなるものを。でうすの前では皆が等しく、どの地、どの立場にいても胸襟を開いてわかりあえるものを」
全登は大仰に天を仰いだ。
四
城の縄張りの次は姻戚だ、と吉成は続けざまに手を打った。だが、竜造寺の娘を太郎兵衛の妻にするのには、手こずった。
「嫁ぐことは家のことゆえ承りますが。私には妖が取りついておりますゆえ」
と花嫁になるはずの娘が、吉成に対して物怖じもせず、きっぱりと断ったからである。
もちろん吉成は、あらかじめ何度も肥前に使者を送って、竜造寺家の実権を握っている鍋島直茂に頼んではいた。竜造寺の当主である政家も同意している、という報は直茂からあったが、肥前に行ってみるとどうにも話が違う。
「困ったことだ」
大して困った様子も見せず、鍋島直茂は肩をすくめた。
「うちの姫さまはどうにも嫁入りがおいやと見える」
鍋島直茂は肥前三十万石を治める竜造寺家の柱石である。
先代の竜造寺隆信とは義理の兄弟であり、竜造寺家が九州一円に名を轟かせるにあたって大いに働いた。隆信が死んだ後も、後継ぎの政家を守って島津の攻撃を耐え抜き、秀吉を九州に呼びこむに功績があったが、そのうちに政家から心が離れていった。
「わしは阿呆が嫌いでな」
客人である吉成に、隠すことなくそう言った。
「隆信さまは年を経てから阿呆になったが、その子は若くしてもう駄目だ。もう肥前は関白さまにお譲りした方がよいとすら考えている」
これからその娘を嫁にもらおうとしている人間に向かって随分なことを言う、と吉成は呆気にとられた。だが、直茂はそんな単純な人間ではない。吉成は直茂が強い言葉を使ってこちらの意図を探ろうとしていることに気付いた。
「殿は竜造寺家と鍋島どのが肥前をよく治めておられるとお喜びです。うまく治まっているところをわざわざ替えたりはしませんよ」
「駿府の大将は関東に国替えをされたようだが?」
「それは北条の後で余人が治めるのは難しく、致し方のないことでありますゆえ」
吉成の言葉に、直茂は表情を少し和らげた。だが吉成はこの竜造寺家の家宰に対して警戒を強めていた。
「わが子におあんさまを嫁がせることに、鍋島どのは……」
「あなたは関白さまの黄母衣衆として長年働き、九州での戦ぶりも見事だった。ご子息の評判も聞いている。おあんさまの嫁ぎ先として大賛成でござるな」
と直茂は言いきった。
「しかし妖とはおかしなことを言うものですな」
「私への精いっぱいの反抗でござろう」
直茂が苦々しげに舌打ちする。
「何が気に入らないのです」
「私が関白さまと結託して、おあんさまを肥前から追い出そうとしている、とお考えだ」
「追い出す? 何故ですか」
「肥前を奪われると思っているのだよ。だから化け物がついているなどと、馬鹿げたことを口にする」
直茂はため息をついた。
「肥前を簒奪するおつもりは?」
吉成の思い切った問いに、直茂は悪びれることなくそのつもりだと答えた。
「これからも難しいかじ取りが続く。なのに、殿のようなうつけに肥前を任せていては、民たちが苦労するばかりだ。民が苦しめば国は弱くなる。弱くなれば、また蹂躙される。そうはさせぬ」
と言い切った。吉成はむしろ、このような男が肥前にいることに安堵した。吉成の表情をじっと見つめていた直茂は、
「ともかく、あのじゃじゃ馬は乗り手を選ぶでしょうな」
そう吉成に告げた。
「毛利どのが談判をなさってもいいだろうが、ご子息に直接口説かせてはいかがか」
と、驚くようなことを言った。だが吉成は、しばらく考えて頷いた。
「本当になさるおつもりか」
自分から言いだした癖に、直茂は意外そうに言う。
「我らはよそから九州に来た者です。おあんさまも不安でございましょう。その心を動かすためなら、どのような労も厭いません。鍋島どのが助言して下さったことならなおさらのことです。妖を払って見せるほどの気概を見せねばなりますまい」
吉成の言葉に、直茂は本当に驚いた表情を見せた。
そうして小倉に戻った吉成は、太郎兵衛が妻を迎えるために肥前を訪れるよう告げたのであった。太郎兵衛はおあんが妻となることが事実だと知って、目が回る思いだった。
「向こうが嫌がってるんですから……」
と言いかけて凄い一瞥を食らって口を噤む。もちろん、己の結婚について文句を言うことなど許されない。せめて大人しく来てくれれば気も楽だが、嫌がられている。だったらこの話はなしにしてもいいのでは、と太郎兵衛は考えたのだ。
「娘の心一つ掴めずして、豊前の、いや九州の人々の心を掴めるか」
吉成は厳かに言った。
「豊前の国人たちは、今のところ殿の朱印を得ておとなしくしてくれている。だが、心から従ったとは到底言えない。肥後で佐々陸奥守がなかなか無茶をしてくれているおかげで、九州の国人たちは疑心暗鬼に囚われている。豊前でも官兵衛どのは相当に厳しく臨んでいるようだ。殿の命は曲げられぬが、元からいる者たちから信を得るのは大切なことだ。だから嫌がっているのなら尚更、心を尽くして迎えなければならん」
困り果てた太郎兵衛は、叔父たちに助けを求めるように視線を向けるが、誰もが困ったように目を逸らした。毛利家の男たちは揃って謹厳で、女遊びをするという風ではない。もちろん、吉成も例外ではない。
「そ、そんなのどうしたらいいんですか……」
「妻を娶るということは、他家の娘をいただくということだ。娘だけをもらうのみではなく、家ごと引き受けてくる覚悟で話をしてこい」
否応なく、太郎兵衛は城から追い出された。又兵衛に訊こうかと思ったが恥ずかしくてできない。さすがに気の毒に思ったのか、叔父の権兵衛が城の外までついてきてくれた。
五
肥前の村中城は、太郎兵衛の暮らす小倉から五日ほどの距離にある。有明海に面した平城で、城を高く盛り上げるのではなく、周囲に土塁を築き、樹木を植えて城の姿を隠すという一風変わった姿をしていた。
竜造寺氏の居城であったが、今や鍋島直茂が本丸の主として振舞っている。太郎兵衛が向かったのは、城の二の丸である。竜造寺一族は本丸ではなく、そこで暮らすことを余儀なくされていた。肥前七郡三十二万石を任されているというのに、どこか暗い空気が漂っている。
「おあんを貰ってくれるのか。それはもの好きがいたものだな。ははは。わしは一向に構わんよ。どうせ肥前も鍋島のものになるのだ。家臣に言うことも聞かせられぬわしが、太閤さまの命に逆らえるわけがなかろう。持って行け」
体が弱いのか、青白くむくんだ顔をした当主の政家が力なく笑う。
「父が挨拶に参ったのですが、断られたようです。それで、直に話をまとめてくるようにと」
政家は何がおかしいのか、話を聞いているのかいないのか、乾いた笑いを発し続けている。
「それはそうだ。あおんには化け物がついているからのう」
「化け物?」
「そうだ。我が竜造寺家が鍋島づれに操られておるのも、主であるわしが二の丸に押し込められておるのも、全てそのお玉という猫の化け物のせいだ。おあんはたいそう可愛がっているようだが、それもまた気味が悪い。そうだ、お前はおあんが欲しいのであろう? では一つ頼みを聞いてくれ」
その化け物を退治し、竜造寺家を闇から救ってくれと言うのだ。
「そうすれば我が一族も、再び父の代の栄光を取り戻すであろうよ。ひ、ひひひ」
政家には近習もいないようであった。広間の窓は全て閉じられ、饐えた臭いが漂っている。蝋燭が数本揺らめいているだけの二の丸の広間には、主の笑い声だけが響き続けていた。
太郎兵衛は退出すると、ほっと息をついた。重い空気に包まれた二の丸の中でも、政家が閉じこもる広間は異様だった。
猫の鳴き声がした。
はっとして頭上を見ると、一匹の黒猫が大きな鼠を咥えて太郎兵衛を見下ろしている。鼠から血が滴って、慌てて避けた。
「こちらへ」
奥向きで働く老女なのか、気配も感じさせず太郎兵衛の背後に立っていた。返事も聞かず、広間のさらに奥にある一角へと案内する。二の丸の庭は殺風景で、つつじがまばらに植えられているだけだ。そして庭全体が、どことなく獣臭い。
「姫さまはこちらにおられます」
一室の前で足を止めた老女は、そう言い残して去っていく。声をかけると、
「どうぞ」
という声がした。静かだが、二の丸の中では唯一生気のある声だ。障子を開けると、中は暗かった。蝋燭すら点けていない。そこにはただ、真っ白な顔が浮かんでいるようで太郎兵衛は息をのむ。
「いかがされましたか」
その声で我に返る。部屋の奥に座っているのは、白き肌の少女だった。黒く豊かな髪は丁寧に櫛を入れられ、薄暗い部屋でもぬめらかな光を放っている。
「森……いえ、毛利太郎兵衛です」
「竜造寺肥前守の娘、おあんです。どうぞお座り下さい」
当主の政家と違って、堂々とした態度だった。
「ご用向きは」
と問われて、自分がこの娘に求婚しに来たことを思い出す。顔に血が上り、言葉が出てこない。何とか絞り出したのが、
「化け物に取りつかれているのですか」
という間の抜けた問いだった。目を丸くしたおあんは袖で口を覆う。何か香を焚きしめているのか、ふわりと柔らかい香りが鼻腔をくすぐった。獣臭さは、この部屋に入った途端に消えていた。
「化け物、ですか。私に取りついているとして、それが何か?」
おあんは袖から口を離し、太郎兵衛を見つめる。
「その化け物を何とかすれば、おあんどのを妻にしてもよい、と肥前守さまは仰いました」
とようやく本題を口にする。既に用向きを予見していたのか、おあんは驚きを面に表すことなく、
「それがお家の決めたことなら、従いますが、太閤さまに取り入り、私を父上から引き離せば肥前を我が物にできるという鍋島あたりの魂胆ならば、面白くありませんね」
否定しようとして、太郎兵衛はおあんの強い視線に射すくめられた。
「ですが、私についているという化け物を、あなたにどうにかできるのでしょうか」
と静かな口調で問うた。
「……やって見せます」
「あなたが化け物と呼ぶ者は、誰よりも純な気持ちで私に仕えてくれています。それを忘れぬよう」
太郎兵衛には、おあんがごく正気であるように思われた。化け物がついているのは、むしろ政家や二の丸自体であるような気がしたが、挑まれた以上は応じなければならない。
それから数日、太郎兵衛は村中城の二の丸廊下で、寝起きすることになった。左文字の太刀を抱き、夜になっても横になることはない。
おあんに取りつくという化け物の正体を見極めるべく、じっと待っていた。五日が経ち、雨となった。庭に漂う獣臭さはさらにひどくなり、耳元を飛ぶ蚊の羽音が不愉快だ。だが太郎兵衛は、庭に立つ影を見て立ち上がった。
その影は背中を丸め、顔を突き出して太郎兵衛の様子をうかがっている。
「化け物というのは、お前か」
と太郎兵衛が問うと、その影は背を伸ばして立った。腕が柳の枝のように長く垂れ下がっている。腕の先に一尺はありそうな爪があることに気付いた瞬間、影が飛んだ。体を丸め一気に跳躍する力は人間業ではない。
だが、太郎兵衛は左文字を抜き放つ。肩が痺れるほどのその一撃に、彼は憶えがあった。
「小倉の紫池にいた……」
島津攻めの際に、各地の軍勢が小倉に集結した。太郎兵衛は父が一軍を任されるのが嬉しくて、小倉城のすぐ側を流れる紫川沿いに走り、池のほとりで気を静めていた。その時に沐浴していた美しき少女には、長大な鉄爪を持った護衛がいた。
「あの娘がおあん……」
「沐浴を覗き見するような奴が姫さまの夫だなんて、片腹痛いね!」
その掠れた声を聞いて、疑問は確信に変わった。
「竜造寺の軍を率いていたのは、やはりおあんだったのか」
「当主がぼんくらだとね、娘まで苦労するんだ。だが姫さまだけに苦労はさせないよ。あたしが一生守ってあげるんだ」
光が縦横に走り、鉄爪が太郎兵衛の皮膚を斬り裂く。
「姫さまは誰にも渡さない。鍋島にも、あんたにも」
太郎兵衛は視線を感じて後ろを振り返る。そこにはおあんが立っていた。
「姫さま、心配いらないよ。こんな奴に指一本触れさせないんだからね」
「お玉……」
おあんが微かに頷いているのが見えた。
「独りおあんどのを守るため、敢えて妖となったのか」
「お前に姫さまの、竜造寺家の何がわかる! よそ者が大きな顔をして、ずるい奴が成り上がって、そんなこと絶対に許さない」
鉄の爪が突き込んでくるところを寸前でかわし、両脇でお玉の腕を挟みこむ。牙を剥いた凶暴な顔がすぐ前にあった。
「お前も小倉に来い」
「寝言を言ってるんじゃないよ!」
強烈な頭突きが太郎兵衛の鼻にめり込む。だが、太郎兵衛はお玉の腕を放さない。
「おあんも、お前も、竜造寺の血も、全部引き受ける。二の丸に閉じ込めることもしなければ、化け物扱いすることもない。だから、俺の妻とその侍女として小倉に来るんだ」
「それは姫さまに言え」
「違う! お前の心にかかっている」
太郎兵衛は鼻と口からおびただしい血を流している。
「お前が認めねば、おあんは動かない」
「だったらどうだって言うんだい。姫さまは誰にも渡さないって言ってるだろう! 姫さまに仇をなす奴は、あたしが未来永劫呪ってやるんだ」
お玉は太郎兵衛の首筋に噛みついた。血しぶきが飛び、庭に流れ落ちる。
「その気持ちのまま、小倉に来るんだ」
「いい加減に……」
血で滑った拍子に、太郎兵衛の腕に挟まれていたお玉の腕が自由になった。鉄爪を振りかざし、止めを刺そうとするところを、穏やかな声が止めた。
おあんが庭に降り、お玉の手を取る。
「私たちのために、これほど血を流してくれた人はこれまでいなかった。おじい様が討ち死にされてから、鍋島も他の者たちも私たちを都合のいいように使うだけだった」
「でも、こいつは姫さまの沐浴を覗くようなやつですよ」
「お玉、実を言うとね」
おあんは少し躊躇ってから、口を開いた。
「この人に体を見られてしまった時、嫌じゃなかったの」
お玉は顔を真っ赤にして鉄爪を外すと、素手で太郎兵衛を引っ掻いた。
六
天正十五年八月吉日、太郎兵衛とおあんの婚礼が執り行われた。十歳と十二歳の、まだあどけなさの残る二人の婚儀だ。
豊前小倉から肥前村中まで、吉成の弟、権兵衛や次郎九郎、九左衛門ら一族、そして宮田甚之丞、杉助左衛門ら太郎兵衛の側近衆が迎えの使者として赴いた。
そして肥前からおあんを乗せた輿の傍らには、お玉がぴったりと寄り添っている。竜造寺家の代表として来たのは、鍋島直茂であった。
一行が小倉に着いたのは黄昏時で、そのまま婚儀は始まった。
柔かな秋風が微かに吹く小倉城の大手門前で、鍋島直茂が朗々と挨拶を述べ、吉成はやや緊張した面持ちでそれに応える。太郎兵衛とおあんの新居となる城の二の丸に花嫁道具が運び込まれ、そのまま宴となった。
小倉には吉成父子にゆかりのある武将たちが招かれている。
黒田官兵衛と後藤又兵衛はもちろんのこと、柳川からは立花宗茂、毛利輝元の名代として安国寺恵瓊がやってきている。相良家からは丸目長恵も訪れ、楽しげに諸将と言葉を交わしている。九州の国分けと検地の指揮を執っていた石田三成も秀吉の名代としてかけつけた。
他にも、秋月や大友といった北九州の名家から次々に祝いの品が届けられ、宴は盛大なものとなった。だが、肥前の佐々成政の所からは祝いの使者もこなかった。吉成たちは怪訝に思ったが、婚儀の忙しさにしばし忘れていた。
おあんは切れ長の目を大きく見開いて、男たちが笑いさざめく様子を見ていた。
「怖い?」
「いえ、私は竜造寺の娘ですよ」
とおあんはきっと太郎兵衛を睨み、すぐに表情を和らげた。
「お祖父さまは肥前の熊と恐れられた方だったね」
「肥前にも勇者は多いのです。祖父や又二郎を前にすると、体が震えるほどでした。優れた武人は、そこにいるだけで風を震わせ、人の心を動かしてしまうものだ、と学びました」
「又二郎殿を誉めるなんて、珍しい」
「嫌いですよ」
おあんはむっとした顔をした。そんな顔も美しい、と太郎兵衛は見惚れていると、
「そこな色男! 花嫁の麗しき顔を己がものとした嬉しさに、客人をないがしろにするか」
と声をかけられた。色男には好色な男、という意味もある。はっとして向き直る。どのような豪の者が相手でも、堂々と返さねば恥となる。だが太郎兵衛は驚いた。端整な細長い顔を真っ赤に染めて太郎兵衛に絡んだのは、石田三成であったからだ。
九州各国から来た豪の者たちは、三成に対して複雑な気持ちを抱いている。秀吉の名代であり、その意思を左右できるほどの側近だ。秀吉への取次を誠実に務めてくれる恩義を感じる一方で、国分けや検地を容赦なく行っている。招待客の中にも、三成とはあからさまに距離を置いている者もいる。
太郎兵衛はきっと前を向いた。吉成たち一門も、客たちも見つめている。大きく息を吸い口を開いた。
「妻を迎えた喜びも、日頃厚情給わったる、皆さま迎えた喜びと、軽重問うはでき申さず。妻は遠く肥前より、それがし遠く近江より、まず互いの容貌を、確かめ合ったその先に、いやめでたし九州の、人の和こそありと存ずる」
と腹の底から声を出し、かつ芝居気たっぷりに言い切って見せた。
「天下一の口上だ!」
後藤又兵衛が大声を上げて誉めると、皆が一斉に喝采した。硬い表情で三成を見ていた国人たちも、笑顔になっている。再び杯が回り始め、立花宗茂の剣舞や後藤又兵衛の謡なども出て座は大いに盛り上がった。
「おあんどの、愛しい背の君の隣で、ちょっと話してもいいかな」
三成の丁重な態度に、おあんはびっくりしながらも頷いた。腰を浮かせかけたおあんに、
「いやいや、お邪魔虫は私の方だ。気にせずにいてもらいたい。私はただ、太郎兵衛どのに礼を言いにきただけだ」
どうぞそのままで、と言うと太郎兵衛の横に座った。
「又兵衛どのも言っていたが、見事な口上だった」
「小倉にきたかぶき者の口上をとっさに真似ました。場にふさわしかったかどうかは自信がありません」
太郎兵衛は最初、三成が叱りに来たのかと思って身構えた。いつもぴりぴりとして、冷たく近づきがたい印象だと思っていたが、愉快そうに微笑をたたえた横顔は、武人の爽やかさを持っていた。
「さすがは小三次どののご子息だ。あなたは絡んでいった私を上げ、己を上げ、そして招かれている諸将と任地の九州も上げた。私一人を上げるのであれば、それは術だ。取り入ろうとする情でしかない。だが、一事を材料に大事を成すのは略だ。大きな目を持ち、理で動いているということだ。その理で動きながら人の心を無にせぬことは、簡単そうで難しい。私は殿に大きな恩を受け、その戦略を無にせぬよう力を尽くしている。その広い目と心に続こうとしているが、なかなか」
三成は自ら杯に酒を満たすと、豪快にあおった。
「いやぁ、いい若武者に会うと気分がいい」
と広い額を叩いた。
「私は殿が願う惣無事をやり通す。そのためなら天下の礎石となって永劫の苦しみを味わってもいい」
「俺だってそうです」
「太郎兵衛には私の築いた礎の上に、永久に崩れない城郭を造ってほしいなぁ。そして豊臣家を盛りたてていって欲しい」
夢を語る少年のように、その瞳は澄んでいた。
「いや、見事な口上に釣られて余計なおしゃべりを。これだから吏僚だ青びょうたんだと陰口を叩かれるのだ。よし、又兵衛どのと相撲でも取ってくるかな」
と三成が立ち上がった。堂々と又兵衛に挑戦すると、九州の諸将も三成に向かって喝采を送った。
その時、早馬が駆けこんできた。使者は吉成を捜して膝をつくと、
「甲斐氏をはじめとする肥後の国人どもが手を結び、兵を挙げました!」
と大声で報じた。宴は沈黙し、しらばくの間誰も身動きすらしなかった。
中巻に続く